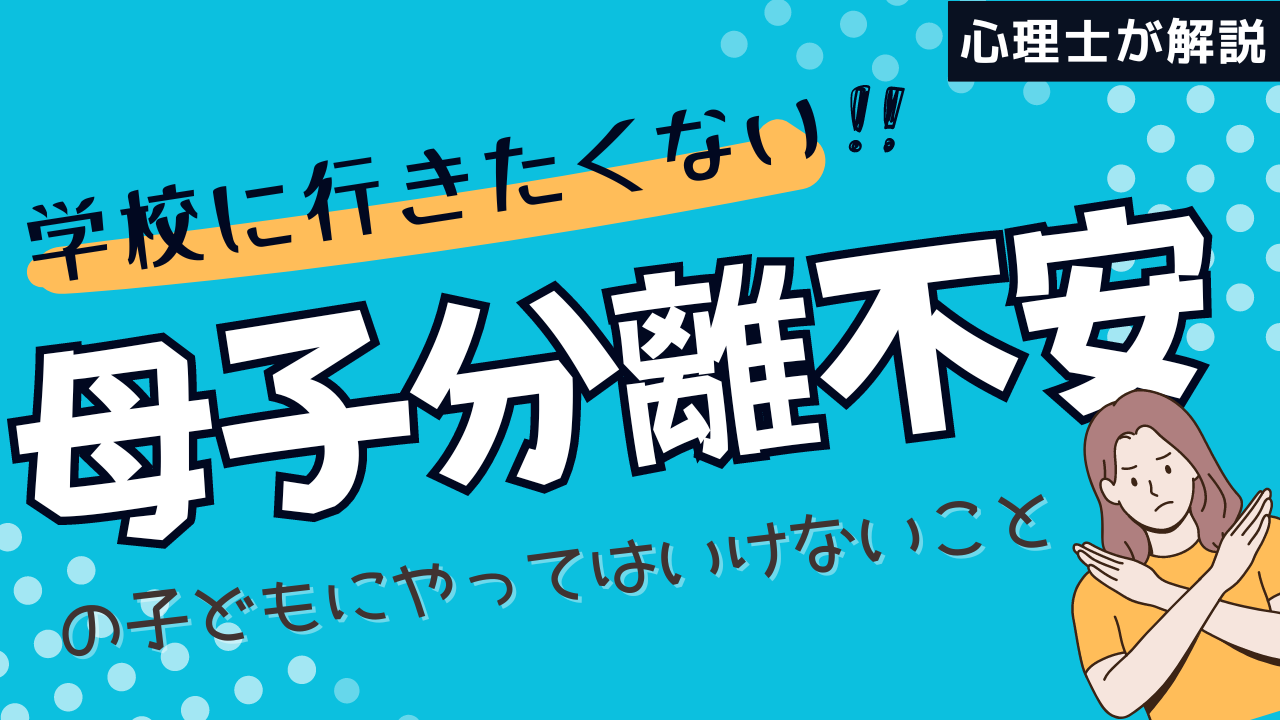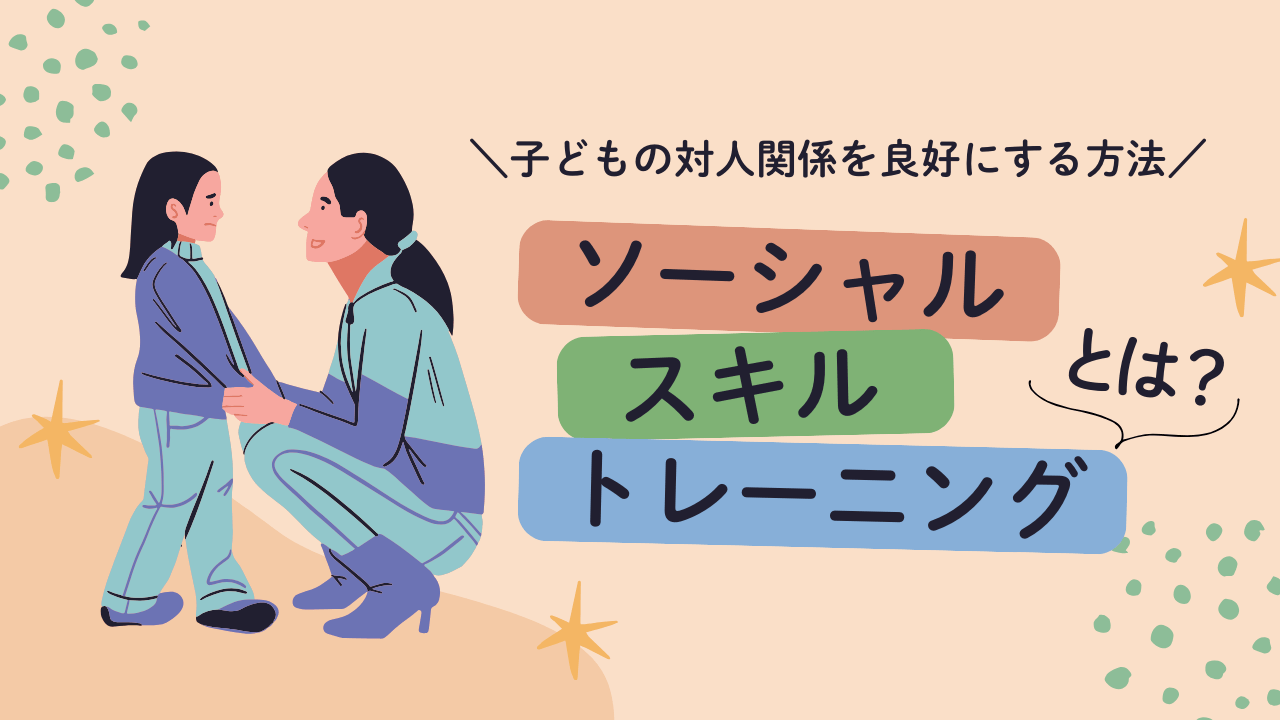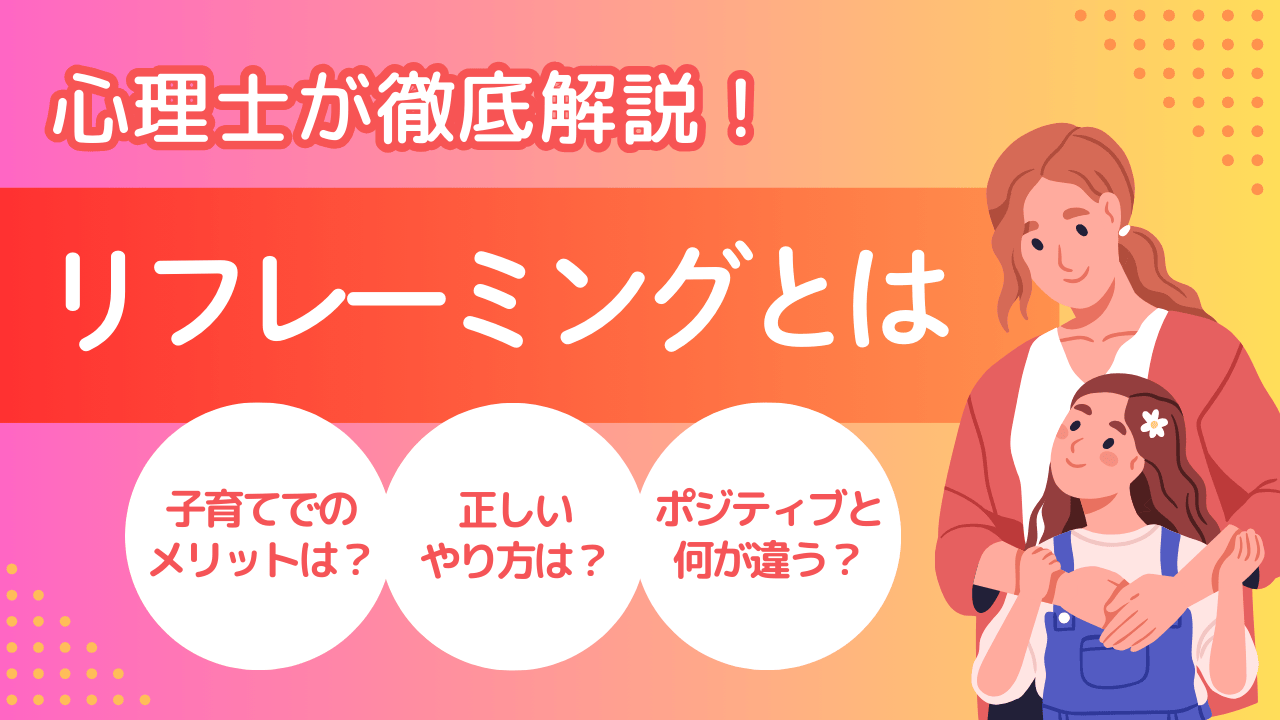お子さんの生活習慣、うまく整っていますか?
夜更かしや不規則な食事、運動不足によって、子どもたちの生活リズムが崩れがちになっている今、親としてどのようにサポートすれば良いか悩むことも多いのではないでしょうか。
睡眠不足や体調不良は、子どもの情緒や集中力に大きな影響を与えます。
この記事では、子どもの生活習慣の乱れが引き起こす問題点と、その改善方法について、具体的なステップとともに詳しく解説します。
今日から実践できる方法で、子どもたちの健やかな成長をサポートしましょう。

執筆:水谷 愛
公認心理師・臨床心理士
精神障害者デイケア、スクールカウンセラー、就労支援、療育現場など約25年間、心理士として医療・福祉・教育分野に従事。子どもから成人までの発達障害、精神障害の方のサポートを行う。
子どもの生活習慣の乱れ
睡眠不足や体調不良など、子どもの生活習慣がうまくいっていないことで問題が生じることがあります。
中には、情緒的な不適切問題が生じる場合もあります。以下で、項目別に見ていきましょう。
睡眠不足
子どもたちは夜遅くまで、または、明け方まで起きているということも珍しくはありません。
ゲームをやっていたり、SNSでネット友達と趣味について話していたりして、夜中起きていて朝方寝る、ということもあります。
そのようにしていると、朝起きることができなくなり、体内時計が狂っていきます。
例えば、もちろん全員ではないですが、フリースクールやオルタナティブスクールに通っている子どもは、日によって夕方まで寝てしまう子や、全然寝ずに登校する子も少なくないでしょう。
睡眠不足は、大人でもイライラや集中力の低下、怒りやすさにつながりますが、子どもではそれがさらに顕著に出ます。
スッキリ目覚めるということが少ないので、情緒的にも不安定になりがちです。
食事の問題
睡眠リズムが定まっていないと、朝食を抜いたり、昼食を抜いたりすることがあります。
夜起きていると、夜にお腹がすいてしまい、夜食を食べることもあります。
このような不規則な食事が子どもたちの生活リズムを崩し、慢性的に便秘になったり体調に不良をきたすこともあります。
特に、最近は夜起きていたいからと、エナジードリンクなどのカフェインを飲む子どもたちも増えてきています。
エナジードリンク自体が子どもの体に過剰なくらいのカフェインが入っていたり、カフェイン依存を起こしやすいので、これもイライラなどの情緒不安定につながっていきます。
運動不足
また、体育の授業が定期的にあったとしても、運動の苦手な子はそれを避けて登校することもできます。
適度な運動をしないと、子どもたちは体力がありあまってしまい、夜なかなか寝つけません。
運動不足が夜更かしにつながり、それが朝寝坊につながり……と、生活リズムを狂わせる要因のひとつにもなります。
また、最近の子どもたちは「遊ぶ」というと、公園に行っても一緒にデジタルのゲームをしていたりすることが多く、体を動かすことが少ない傾向があります。
それが続いて体調が悪くなったり、子どもの肥満につながることもあるのです。
生活習慣の乱れにともなう子どもの情緒的な問題
生活習慣が乱れてくると、体調がだんだん崩れていきます。
体調が悪い日が続くと、大人でも情緒不安定になることが多いでしょう。
同じように子どもたちも情緒不安定になることが多くあります。
そして、子どもの場合、それを言語化するほど成長していないこともあり、さらに情緒不安定になることがあります。
イライラ
十分に眠れていない、栄養がとれていない、というだけでも人はイライラします。
眠れない等から生じる体調不良により、人はさらにイライラが増します。
子どもたちも同じで、体調不良が続くと子どももイライラします。
頭痛、腹痛、吐き気、めまいなど、具体的に症状を呈する子もいますが、言葉にはできないけれど何となく調子が悪くてイライラしているという子も多いです。
子どもなので、特に低学年になればなるほどイライラの原因が説明できず、「なんかムカつく」などの抽象的な表現で困っている親御さんも多いことでしょう。
集中力の低下
当然ですが、睡眠が十分にとれていないと、集中力が低下します。
これは大人でもそうなのですから、子どもの場合はなおさらです。
子どもに必要な睡眠時間は、大人よりも長く、8時間以上寝ても良いくらいです。
子どもも寝不足だとボーっとしてしまい、集中力が続かなくなり、居眠りしてしまったり、「心ここにあらず」な状態になってしまいます。
また、朝ご飯を食べていないことによって、お腹が空くため、さらに集中力が低下してしまいます。
遅く起きて朝ご飯を食べないとなると、ダブルパンチで集中力が落ちます。
キレやすくなる
夜更かしをして、ご飯を十分に食べていないと、イライラがひどくなり、キレやすくなります。
また、それに伴う体調不良で頭痛、めまい、腹痛、便秘などがあると、イライラを突き抜けてキレることもあります。
ちょっと自分がイヤだなと思うことを言われると、子どもが怒鳴ってくることも実際にあるのです。
また、子ども同士でもケンカに発展したり、暴言が出てしまったりします。
子どもたちは自分の気持ちを大人よりも言語化しづらい分、イライラの吐き出し方がわからず、キレるという表現に出てしまうこともあります。
不適切行動への対応について
睡眠と食事を決まった時間にとる
適切な睡眠と食事は、やはり子どもの心を安定させます。
特に、きちんと夜寝て、朝日を浴びるという行為はセロトニンを増やし、人を幸せな気持ちにします。
朝気持ちよく起きることができると、朝食もおいしく食べることができるので、さらに気分が良くなりますね。
家族の出発時間がバラバラなおうちもあるかと思いますが、少なくとも子どもと一緒にいる家族だけでもご飯を一緒に食べられると良いですね。
朝食を食べながらコミュニケーションがとれれば最高です。
ストレスへの対応
子どもが夜更かしをするのはなぜなのか、しっかり把握しておく必要があります。
リアルなコミュニケーションに飢えているから、ネットの友達とコミュニケーションをとりたくなるのかもしれません。
また、ネットの友達だと、関係を切りたくなったらスイッチを切れば切ることができますが、リアルだとそうはいきません。
子どもの本当のストレスをしっかり知って、適宜親が相談にのってあげられるようにしましょう。
コミュニケーション
普段から親子で密にコミュニケーションをとりましょう。
子どもは学校に行くこと、または行けないことでストレスを感じているかもしれません。
子どものコミュニティに関する記事はこちら。
子どもたちの人間関係も、お互いに何らかの傷を持っている関係なので、お互いに人間関係の結び方が苦手かもしれません。
そのことによるストレスも子どもは抱えているかもしれません。
そして、子ども同士のコミュニケーションに詰まったとき、具体的にどう伝えればお互いに解決につながるのかなど、子どもがアドバイスを求めたときに親がそっとアドバイスしてあげられると良いですね。
具体的なコミュニケーション方法を親がそっと教えてあげられることで、子どもがうまく日常や学校生活での人間関係を維持することもできるかもしれません。
規則と制限をつける
子どもが年中スマホを自分の隣に置いて過ごしていると、夜中ずっと友達と会話し続けて、結局寝不足になってしまいます。
パソコンも同じく、夜中ずっと使っていることによってゲームやネットサーフィンがやめられず、夜更かししてしまうことになるでしょう。
夜決まった時間になったらスマホを親に預ける、パソコンは消す、という決まりを作っておきましょう。
親子での決まりがないと、子どもは制限なくダラダラとスマホやパソコンで遊んでしまいます。
そして朝起きられず、体調不良になり、まさに「悪循環」です。
電子機器の規則や制限は子どもに守らせるようにしましょう。
まとめ
いかがでしたか。
子どもの生活習慣の乱れが体調不良を招き、そこから情緒不安定になる、という悪循環になってしまうということがおわかりいただけたかと思います。
特に最近は、登校時間が柔軟になっている学校も少なくないため、どうしても朝必ず起きなくてはならないという制約がありません。
子どもの生活習慣が乱れそうになったら、まずは睡眠と食事だけでもしっかりとらせることが大事です。
そして、親子でしっかりコミュニケーションをとることで、子どものストレスを少なくしていけると良いですね。

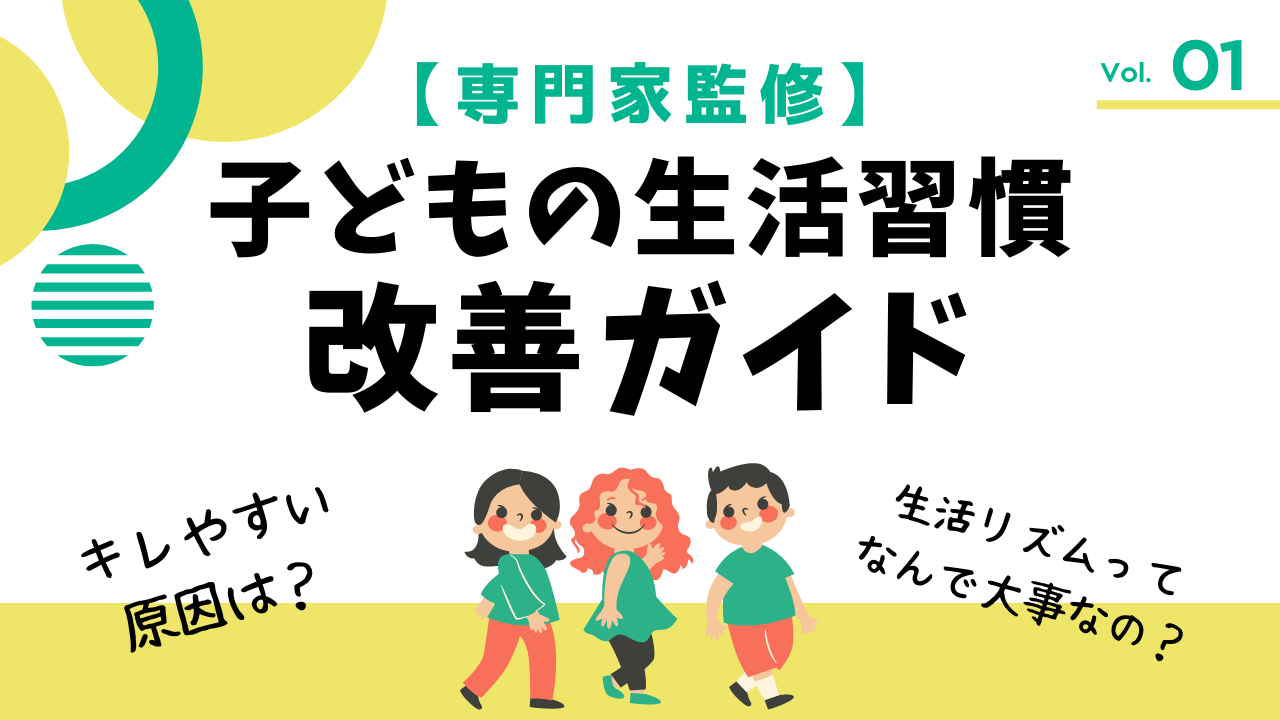
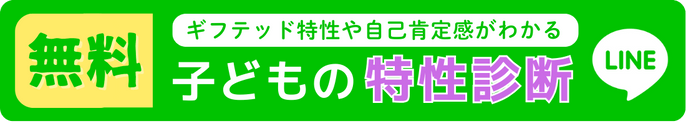


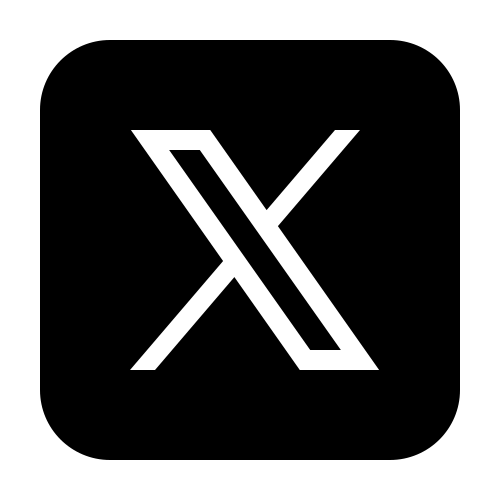

」入門.png)