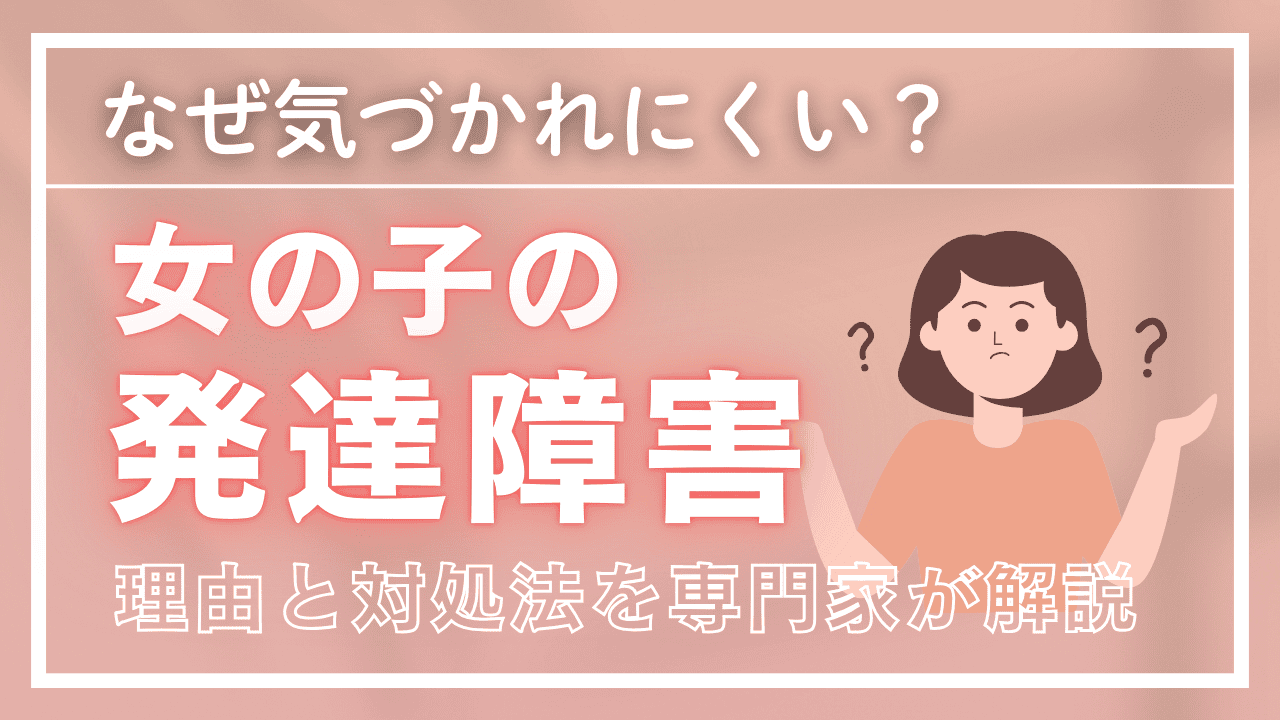小学生のお子さんが、お母さんから離れないとき、皆さんはどうされていますか?
「母子分離不安(分離不安)」という言葉がよぎる人もいるかもしれません。
べったりだから分離不安とは限らないですが、「うちの子はどうなんだろう?」「どう対応すればいいんだろう?」と思いますよね。
今回は、小学生の子どもを持つ親御さんに向けて、分離不安と年齢別の愛情表現の方法、べったりさんへの対応法方法などをご紹介します。

執筆:いけや さき
公認心理師・臨床心理士
精神科病院、療育施設、心療内科・児童精神科クリニックなど主に医療と福祉領域にて心理士として従事。発達障害の子どもたちや保護者、女性のメンタルヘルス等のサポートを行う。
お母さんにべったりの小学生は母子分離不安?
母子分離不安とは
「お母さんも一緒に行こう!」
「え~!どこ行くの?行っちゃだめ!」
お母さんを求める子どもの声に、対応し続けるのは大変ですよね。
「もしかしてうちの子、分離不安なの?」と思っているお母さんへ。
べったりだから分離不安とは限りません。
分離不安とは、養育者(お母さんなど)から離れるときに、強い不安感があるときに当てはまります。
べったりであっても、ただ仲良くしたいだけであることもあるからです。
下記の記事では、母子分離不安について詳しくお話しています。参考にしてみてくださいね。
幼少期と小学生:愛情表現の違い
幼少期にママにべったりの状態と、小学生になってママから離れられない状況には違いがあります。
幼少期と同じように愛情表現しても、子どもは求めていない可能性もあるのです。
以下では、心理学者エリクソンの提唱した発達段階理論をもとに、年齢別の対応方法を解説します。
知っておきたい!子どもの自立と発達段階
エリクソンの発達段階理論は、人が生涯経験する心理社会的発達課題や危機(困難)を、8段階に分けたものです。
ここでは、幼児期後期(3歳〜6歳)と学童期(6歳〜12歳)について説明します。
幼児期後期の分離不安の子どもの特徴
幼児期後期は、言語も運動も発達していく時期です。
この時期の発達課題は「自発性」、心理社会的危機は「罪悪感」とされています。また、この時期に得られるとされる力は「目的」です。
想像力や好奇心で活動したくなる時期であり、自らどんどんチャレンジしたい気持ちが育ちます。
しかし、チャレンジ精神が旺盛なときに頻繁に叱られてしまうと、子どもは「罪悪感」を抱きやすくなります。
罪悪感を抱きやすいと自分の意見を言えなくなったり、自己否定しやすくなるので、危険なことには気を付けつつ自主性を伸ばしていきましょう。
小学生の分離不安の子どもの特徴
学童期は、小学生の時期に当てはまります。
この時期の発達課題は「勤勉性」、心理社会的危機は「劣等感」とされています。
また、学童期に得られるであろう力は「有能感」です。
学童期はさまざまな経験を通して、他者との関係の築き方やルールを守ることの大切さを身につけていきます。
適切な人間関係や社会性が育まれることで「勤勉性」が身につきます。
しかし、集団行動でうまくいかなくなったり、なじめずに自分の居場所がわからなくなったりすると「劣等感」を抱きやすくなるといわれています。
分離不安を防ぐために
幼少期はスキンシップ多めに
幼児期後期に子どもへ愛情表現をする際は、スキンシップを多めに用いると効果的です。
スキンシップは愛情ホルモンといわれる「オキシトシン」が分泌されます。
オキシトシンが分泌されると、子どもがイライラしたり不安になったりする状況を適切にコントロールしやすくなるのです。
お母さんとのスキンシップを通して、他者を信頼する心も育まれますよ。
幼児期後期なら次のようなスキンシップはいかがでしょうか?
なかにはスキンシップの苦手な子どももいます。
そんなときはアイコンタクトを増やす、身体を優しくさするなど、子どもが嫌がらないものからはじめましょう。
小学生は言葉も用いて表現
身体を使ったスキンシップをすべてやめる必要はないですが、成長過程に合わせて表現方法を工夫するのはいかがでしょうか。
下記に小学生のお子さん向けに考えられる愛情表現方法をまとめてみました。
低学年なら、抱きしめるのもとても素敵です。
ほかにも、頭をわしゃわしゃっとするのは高学年でも意外と喜ぶ子もいます。
子どもの反応も見つつ、わかりやすく愛情表現しましょう。
特に「ありがとう」「うれしい」は日常で伝えやすい言葉です。「〇〇くんすごいね!」とやっていることを具体的に褒めるのもいいでしょう。
ほかには「大好き」「愛してる」も伝えられるときは伝えてみてくださいね。
小学生が親にべったりのときの対応方法3選
愛情表現方法を実践しても、親からなかなか離れられないべったりさんもいると思います。
べったりさんのままになっている子に対して、お母さんたちができることを紹介します。
1. 言葉と見本で伝えましょう
人との距離感が近くて、すぐにべったりになってしまうなら、適切な距離感を伝えていきましょう。
「近いよ」「離れて」といわれても、子どもにはわかりにくく、むしろ傷つく可能性もあります。
次のような伝え方はいかがでしょうか?
「〇歳になったら、ぎゅーじゃなくて握手ね」
「腕を伸ばした分だけ離れても、聞こえるから大丈夫よ」
具体的な方法や段階的に離れていくやり方を伝えてみましょう。イラストなどを用いる方法もあります。
ほかには、「ぎゅーはびっくりするから、ママって声かけてね」と伝えたり、嫌いではないけどびっくりしたり、お友達には嫌がる子もいる可能性も伝えたりするのもいいでしょう。
2. 2人きりの時間をつくりましょう
特にきょうだいがいる場合、独り占めする時間がなくなってべったりさんになる子もいます。
下の子の子育ては大変かと思いますが、送り迎えや買い物、どんなシーンでもいいのでお子さんと2人きりの時間をつくってみるのはどうでしょうか。
数分でも満足できる子もいます。そのときに、「いつも○○ちゃんばかりで寂しいよね」と気持ちを代弁したり、「ママは○○くんのことも大好きだよ」と安心できる声掛けをしてみるのもおすすめです。
3. 徐々に離れる練習も
徐々に離れることは自立につながります。
たとえば、友達と遊ぶことに不安があって「ママも一緒~」といわれたとします。
一緒に行くだけじゃなく、次のように段階的に一人で行けるようにしてみてもいいですね。
「公園の入り口まで一緒に行こう」
「あの電信柱まで一緒に行くね」
友達と遊んで帰ってきたら、どうだったかを聞いたり、楽しめた部分に注目してあげるのもおすすめです。
「案外楽しかった!」「ママと離れても楽しめた!」という体験と、ママが家で待ってくれている安心を伝えましょう。
分離不安は発達障害あるある?
分離不安の子が全員発達障害ではありませんが、関係は深いといわれています。
自閉スペクトラム症(ASD)の子は、環境の変化に適応することが苦手です。
新学期や夏休み明け、学校行事などは不安になりやすい傾向があります。
ルーティンが変わることで予測できない状態になること、対人関係や社会性が苦手になりやすいことなども不安のきっかけとなるでしょう。
注意欠如多動症(ADHD)の子は、感情のコントロールが苦手な子や人との距離感がつかめないことがあります。
情緒が不安定になって、不安をコントロールできずにお母さんにべったりとなることもあるでしょう。
発達障害傾向のあるお子さんの場合でも、上記で紹介した対処法を試してみてください。
分離不安は不登校になる?
結論からいうと、不登校になる可能性もありますが、ならない子もいます。
特徴など明確な違いがあるわけではありません。
心配になるかと思いますが、親御さんが自分自身を大切にする時間をつくり、子どもと穏やかに関われるようにするのはいかがでしょうか。
不登校になる原因はさまざまで、子どもの性格や周囲の環境などによっても異なります。
子どもが安心して相談できる関係性を作ることで、対策も一緒に考えていけるといいですね。
小学生で親にべったりな子の相談ならGifted Gazeへ
子どもがお母さんにべったりする理由はさまざまです。
今回紹介した対応方法を実践しつつ、お母さんたちも一人で抱えないことが大切になるでしょう。
Gifted Gazeでは、小学生の子育て相談のプロである医師や心理士がオンラインで相談を承っています。お気軽にお問い合わせくださいね。