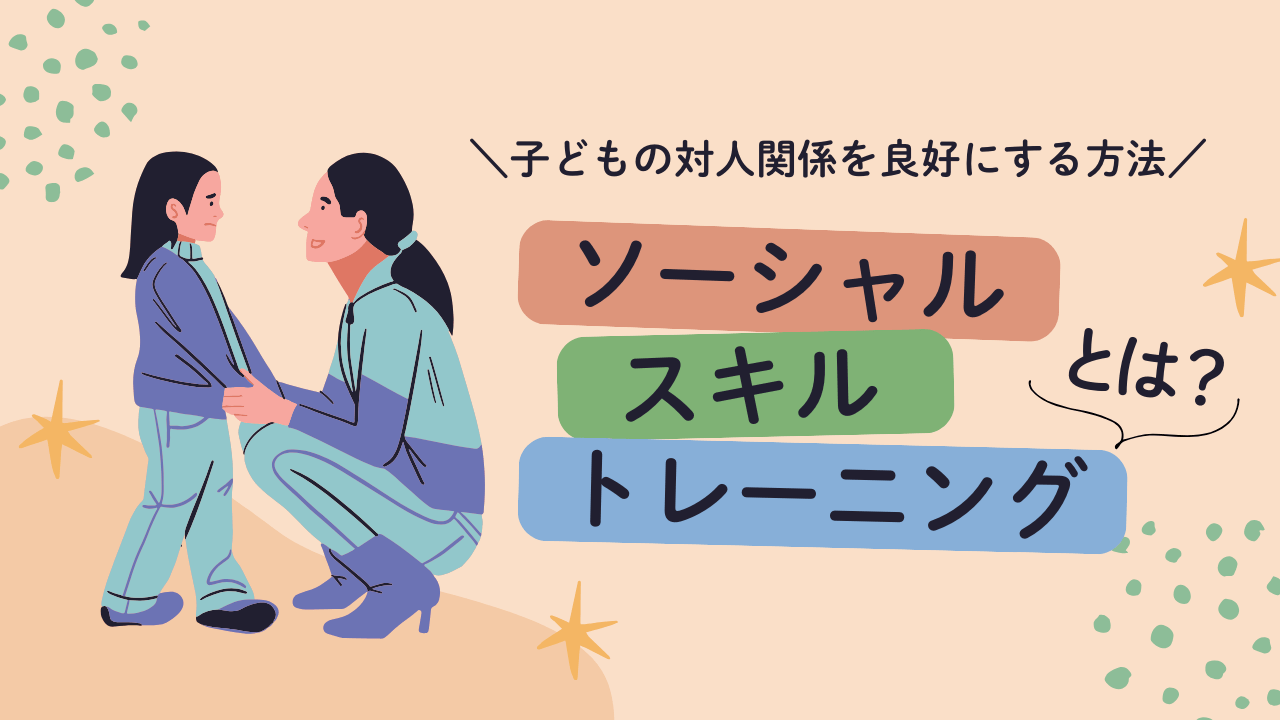「うちの子、何が得意なんだろう…」
「ついテストの点数や結果ばかり見てしまう…」
こんな風に悩んだことはありませんか?
この記事では、小学生の子どもを育てる保護者向けに臨床心理士が、「子どもの強み」や「長所」の見つけ方をわかりやすく解説します。
子どもの強みを見つけるのは、子どもが過ごしやすくなるだけでなく、親子関係を良好にすることにも役立ちます。
プロセスや特性に目を向け、子どもの魅力をたくさん見つけましょう。
この記事を書いた専門家

いけや さき
公認心理師・臨床心理士
精神科病院、療育施設、心療内科・児童精神科クリニックなど主に医療と福祉領域にて心理士として従事。発達障害の子どもたちや保護者、女性のメンタルヘルス等のサポートを行う。
子どもの「強み」とは?
子どもの強みとは、「できること」や「結果が出せること」だけではありません。
たとえば、「人の話をよく聞ける」「発想がユニーク」「コツコツ継続できる」など、日常の中にその子らしい長所が隠れているものです。
このようなスキルは「非認知能力」と呼ばれています。
学校のテストや成績では測ることのできない、社会で生きていくためにとても大切な力です。
子どもの強みに目が向きにくい理由
子どもの強みに親の目が向きにくい理由は次のようなことが考えられます。
以下で、それぞれ詳しく解説しますね。
テストや評価に目が向きすぎる
目に見える「点数」や「順位」などに意識が向きすぎると、本来の“個性”や“プロセスで頑張ったこと”が見えにくくなることがあります。
親として、子どもの学習状況や成果が気になるのは当然のことです。しかし、次のように勉強面以外に注目するのも大切です。
「失敗したけど最後までやりきった」
「友達を励ましていた」
「相手に体を向けて話せていた」
このような日常の中に溶け込んでいる場面に、子どもの大切な強みが隠れているかもしれません。
「当たり前」に子どもができている
子どもの強みは、親から見ると「普通のこと」「当たり前のこと」に思えてしまうこともあります。
たとえば、「毎朝きちんと準備して学校へ行ける」「家族に優しい言葉をかけられる」「ごちそうさまが言える」など、毎日の中で当たり前にしていることが子どもの長所なのです。
誰かと比べる必要はありません。子どものありのままを認めることは、子どもの自己肯定感アップにもつながりますよ。
子どもの強みの見つけ方3選
ママやパパも毎日仕事や家事育児に追われていると、子どもと向き合う時間も取れないですよね。
この記事を見てくれたことが、子どもの強みに気づく第一歩です。子どもの強みを見つける具体的な方法を消化します。
子どもの強みの見つけ方①子どもの性格傾向を観察してみる
子どもによって、強みが発揮される場はさまざまです。たとえば、以下のようなタイプごとに見てみましょう。
このように、子どもの「好き」や「よくやっていること」に注目してみると、自然と強みのヒントが見えてきます。
親子でもタイプは違いますよね。自分と違うと、いいところと認識しにくいこともあります。
子どもが楽しそうにしていること、好きなことなどをよく観察してみましょう。
子どもの強みの見つけ方②夢中・熱中しているものから見つける
子どもが夢中になっていることを観察するのもおすすめです。
家の中でいつも絵を描いている子もいれば、ゲームに夢中になっている子もいますよね。
同じゲームでも街を作るゲームやシューティングゲーム、謎解きや冒険ものなど、はまっている種類によって「強み」は変わります。
たとえば、街づくりゲームが好きな子は「オリジナルの発想力がある」「作り上げることが得意」などの強みを持つことが多いです。
シューティングゲーム好きなら「集中力が高い」「攻略するために考える力がある」などの強みを持っているでしょう。
子どもの強みの見つけ方③日常の言動からヒントを得る
家族との会話での役割や、よく話す話題などからも強みを見つけられます。
「なんで?どうして?」と質問が多い子なら、探究心や論理的思考がある可能性があるでしょう。
パパやママの言葉をまねしている子は、観察力があるかもしれません。
また、妹や弟のお世話をしたり、話しかけたりする子は共感力やサポート力があると考えられます。
子どもの強みをどう伸ばす?
見つけた長所を伸ばしたいと思っても、学校の勉強に直接活かせるものではないとどうしたらいいかわからないですよね。
以下では、見つけた子どもの強みの伸ばし方をご紹介します。
ありのままを受け止める
子どもを良し悪しで評価せず、ありのままで受け止めてみましょう。
社会的なルール違反などはよくないので教える必要はあります。
そうではない限り「○○できたからすごい」ではなく、「○○しようとしたね」「やってみようとしてえらいね」とプロセスを認めてあげるのはいかがでしょうか。
また「ここまでできたね」「よく考えたね」もプロセスの1つです。
途中であきらめたり、失敗しても怒らず「まずやってみた」という気持ちや工夫を尊重しましょう。
尊重された経験は、子どもの自信や自己肯定感アップにつながります。
小さな成功体験を積み重ねる
心理学では、小さな成功体験を積み重ねるために「スモールステップ」という方法を活用します。
「ちょっとできた」という経験を増やすことも、自己肯定感を育てる大切なカギです。
たとえば、子どもがゲームに夢中で自分の部屋を片付けないとしましょう。
実は子どもにとって部屋はものすごく大きな環境なんです。
まずは次のようにエリアやタスク分けをして、ゲームをクリアするかのように設定してみるのはいかがでしょうか。
このように具体的かつ小さなタスクを作ることで、徐々に部屋を片付けていくことができます。
少しでも取り組めたら「自分でできてすごいね」「きれい!すっきりしたね」と伝えてみてください。
「また明日もやってみようかな」「確かにすっきりしたかも」と、行動する気持ちになりやすくなります。
強みを活かす場をつくる
強みを発揮できる場を大人が提供しましょう。
人と話すのが好きな子なら、積極的に子どもが話をできたり、意見を言えたりする場をつくってみるのはいかがでしょうか。
「学校でどんなことがあったか」「楽しかったことはなにか」など、悩みだけでなく、うれしい感情の共有もできるといいかもしれません。
子どもが話してくれたら「それは面白いね!」「ママ知らなかった!」など、話に興味を持って会話を楽しんでみましょう。
子どもの強みを客観的に把握したい
日常生活でも、子どもの強みや長所を見つける手段はたくさんあります。
しかし、いずれも親の視点であることに変わりありません。
ギフテッド診断テストの「ギフテッド」は、高知能や天才を表すものではなく、子どもにはみんな宝のような才能があることを意味しています。
ギフテッド診断で見つかる子どもの強みは、次の4領域です。
ネットですぐに申し込みと回答ができ、結果もオンラインで受け取れるのでお忙しい親御さんにもおすすめです。
詳しくはギフテッド診断のページをご覧ください。
子どもの強み発掘ならGifted Gazeへ
今回は子どもの強みの見つけ方を紹介しました。
学校のテストや成績だけでなく、次の3つの視点から強みや長所を見つけられると説明しましたね。
①子どもの性格傾向を観察してみる
②夢中・熱中しているものから見つける
③日常の言動からヒントを得る
紹介した方法で普段の様子から見つけることもできますが、客観的データとして把握できる「ギフテッド診断」もおすすめです。
また、Gifted Gazeでは、小学生の子育て相談のプロである医師や心理士がオンラインで相談をおこなっています。
子どもの特性を知り、接し方に役立てたい保護者様はぜひお気軽にご相談くださいね。