「IQが高いはずなのに友だちとうまくいかない」
「トラブルを起こしがちでこれからが心配…」
このようなお悩みを抱える親御さんへ。
もしかしたら、悩みの背景には非認知能力(社会で生きるためのスキル)の影響があるかもしれません。
IQが高い子やギフテッド、2Eの子どもは、論理的思考や芸術的才能を持っているけれど、非認知能力の発達はゆっくりになりやすいと言われています。
今回の記事では、高IQの子に起きやすい友だちトラブル、非認知能力がなぜ大切なのか、日常生活でどのように育めるのかを公認心理師が具体的に解説します。
この記事を書いた専門家

いけや さき
公認心理師・臨床心理士
精神科病院、療育施設、心療内科・児童精神科クリニックなど主に医療と福祉領域にて心理士として従事。発達障害の子どもたちや保護者、女性のメンタルヘルス等のサポートを行う。
非認知能力とは
非認知能力とは、学力や数値で測れない「社会で生きるための力」です。
協調性や意欲、精神的安定などが含まれ、社会性や対人関係の土台となる力。IQが高い子どもは、この力が未発達になりやすく友達とのトラブルやストレスを感じることがあると言われています。
非認知能力の基本的な考え方については、以下の記事で詳しく紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
学力でもIQでもない!子どもの非認知能力がなぜ大事なのか|”ビッグ・ファイブ”についても解説
IQが高い子に起きやすい友だちトラブル3つ
IQが高い子どもは、脳の前頭前野という部分の発達がゆっくりになりやすいと言われています。
その影響で、次のような友だちトラブルが起きやすいのです。
1. 悪気なく指摘してしまう
IQが高い子どもは、持っている知識や正しいと思う物事と異なる現象が起きると、悪気なく相手に指摘することがあります。
正しいことを教えることを優先してしまうため、相手の表情が曇っていたり、困った様子になっていたりしても気がつきにくいのです。
その結果、友だちが「意地悪を言われた」「バカにされた」と受け取ってしまうことがあります。
IQが高い子どもにとっては「教えてあげた」つもりでも、相手に伝わっていないのです。
このようなすれ違いが続くと、友だちとの関係に自信をなくしたり「わかってもらえない」と孤立したりするケースもあります。
2. 相手に同じレベルを求めようとしてしまう
知識が豊富だからこそ、自分の理解したことを前提に話す傾向があります。
自分が理解していることを相手も知っているだろうと思い「そんなの簡単だよ」「なんでわからないの?」と素朴な疑問を抱くことがあるのです。
相手からすれば、マウントや見下しと受け取られやすいこともあります。
非認知能力がまだゆっくり発達している段階だと、対人関係で誤解や孤立につながることもあるでしょう。
3. 言葉の選び方や発想が伝わらずすれ違う
高IQの子どもは、論理的で明確な表現を好む傾向があります。
得意なことはたくさんあるけど、相手の気持ちを想像し、やわらかく伝える言い回しや表現が苦手な子もいるのです。
また、比喩やユーモアをそのまま真に受けてしまうこともあり、冗談や場の空気がうまく読めずに誤解を招くことがあります。
こうした「伝え方や考え方のズレ」も、対人関係の壁になりやすい要因の1つです。
高IQの子の中には、大人と話した方が楽しいと思っている子もいます。
後半で紹介する非認知能力の育て方を実践しつつ、子どもが自分らしく過ごせる環境をつくることも大切です。
非認知能力が対人関係に与える影響
非認知能力のなかでも、共感力や自己調整力は対人関係を築くうえで欠かせない力です。
自分の気持ちを落ち着ける力や、相手の立場になって考える力、うまくいかないときに気持ちを切り替える力が、共感力や自己調整力の具体例となります。
このような非認知能力は、友だちと意見が食い違ったときや、思いが伝わらなかったときに役立つ力なのです。
非認知能力が育つことで、子どもは「わかってもらえた」「うまく伝えられた」といった安心感や達成感を得られます。
ただし、2E(ギフテッド×発達障害)の子どもやASD、ADHDの子は、発達特性の影響も考慮しながら、非認知能力を育てていきましょう。子どもの特性は1つとは限りません。
あらゆる可能性を考えつつ、「その子本人」を見つめてみてくださいね。
高IQの子の非認知能力の育て方
IQが高く知的理解が早いけれど、感情や心理面とのギャップを感じやすい子どもたちに向けた非認知能力の育て方をご紹介します。
非認知能力についてさらに詳しく知りたい人は、以下の非認知能力特集ページもあわせてご覧ください。
非認知能力の記事特集〜5大要素からEQとの違い・育み方まで〜 – Gifted Gaze
得意な能力を活かして自信をつける
非認知能力のなかでも自己肯定感は、子どもが物事に取り組むために必要なスキルです。
得意なことを活かして「できた!」という経験を積んでいきましょう。
高IQの子どもは、好きなことや得意な分野に対して強い集中力や理解力を発揮します。
強みを日常生活の中で認めたり、発表や紹介の場をつくったりすることで、自己肯定感を育むことができますよ。
たとえば興味のあることを楽しそうに話してくれるけど、親からしたら理解しにくいときがあるとします。
「すごく詳しいね!〇〇のこと教えて!」と、知識を認めながら聞きたいことを1つに絞って、子どもが説明しやすく導くのはいかがでしょうか。
「その説明すごくわかりやすい!」「そうやって考えるんだね」と伝え方や発想を理解してもらえることで、子どもの自信が育ちます。
自信が育てば、対人場面でも「伝えてみよう」という意欲につながりやすくなります。
得意なことを伸ばすのは、非認知能力を育てる第一歩でもあるのです。
コミュニケーションの”リカバリー”力をつける
未然に防ぐだけでなく、子ども誰かに何かを言いすぎてしまった時、自分自身でフォローする力が欠かせません。
高IQの子どもは頭の回転が早いため、次々と正論が出ることがあります。その結果、相手を傷つけるような発言になってしまうことも。
ご家庭で「もし言いすぎちゃったら、どう言い直せるかな?」とリカバリーの言葉を考えておきましょう。
たとえば、「さっき言い方きつかったよねごめんね、〇〇って意味だったんだ」と言い直す練習をしておくと、実際の場面でもお友達に対して落ち着いて対応できるようになります。
失敗したあとにやり直す力”リカバリー”力は、対人関係だけでなく、人生全体を支える大切な非認知能力です。
同世代に伝わりやすい言い方の練習をする
IQが高い子どもは同世代よりも、年上と話が合う子が多いです。
しかし、学校生活は同世代と過ごしますよね。同世代に伝わりやすい話し方を知って、トラブルをできるだけ回避しましょう。
どれだけ子どもの考えが正しくても、伝え方ひとつで相手に伝わらないことがあります。
高IQの子どもは論理的な表現が得意な反面、感情やニュアンスに寄り添った言い回しが苦手な子もいるからです。
親子で「今の言い方、〇〇ちゃんだったらどう受け取るかな?」と振り返ったり、他の言い方を一緒に考える時間を持つことで、相手に合わせた表現力が育ちます。
その一方で、年齢に限らず話の合う友人を見つけることも大切です。
信頼できる相手との関係は、子どもなりに社会性を身につけるきっかけとなるでしょう。
高IQの子どもの非認知能力を調べてみよう
ここまで非認知能力について解説しましたが、見えないスキルを可視化する方法があります。
それが「ギフテッド診断」です。
「ギフテッド診断」は、信頼性のおける「ビッグ・ファイブ」理論と「多重知能理論」に基づいて、子どもの非認知能力や個性、得意・不得意を客観的に理解できるだけでなく、IQ(知能指数)も把握することができます。
高IQの子どもならではの特性を見つけて、一人ひとりに合った支援や関わりを考える上で活用してみてください。
高IQの子どもの非認知能力を育てよう
非認知能力は特別な子だけでなく、すべての子どもに必要な「生きる力」です。
IQが高いからこそ、見落とされがちなスキルに目を向けて、子どもの可能性を広げていきたいですね。
非認知能力の育て方を意識した関わり方は、子どもの強みを伸ばすことにもつながります。
Gifted Gazeでは、小中学生の子育て相談のプロである医師や心理士がオンラインで相談を担当しています。
IQが高い子どもの対人トラブルにお悩みの保護者様は、ぜひ専門家への相談も活用してくださいね。
我が子はギフテッド?と思ったら
わが子がギフテッド(Gifted)かもしれない、と思ったら、まずは「ギフテッド診断」テストを受けてみることもおすすめです。
「ギフテッド診断」テストでは、子どものIQ(知能指数)や行動特性、才能のバランスを多くの側面から確認することができます。
\申込みから結果までオンライン完結/
ギフテッド診断とは
子どもの才能は、多くの側面に光を当てながら総合的に判断することが重要です。
ギフテッド診断は、4領域・全27種類の項目を測定し、子どもの才能を多面的に把握します。
より多くの方にご利用いただける価格※と内容を実現しました。
※”4領域”のうちの一つ、例えばIQテストだけでも診断項目がきちんと揃ったものを受けるためには15,000円〜50,000円程度の費用がかかります。(弊社独自調査)



診断テストの結果が活用できるように、結果についてわからないことがあれば、LINEで質問※1することができます。
さらに、お子さまの状況と必要に応じて、子どもの発達と子どもの心の専門家である医師・心理士に相談※2することもできます。どんな些細な質問でも大丈夫です。
※1 月間の質問回数の条件があります。
※2 別途料金がかかります。
\申込みから結果までオンライン完結/
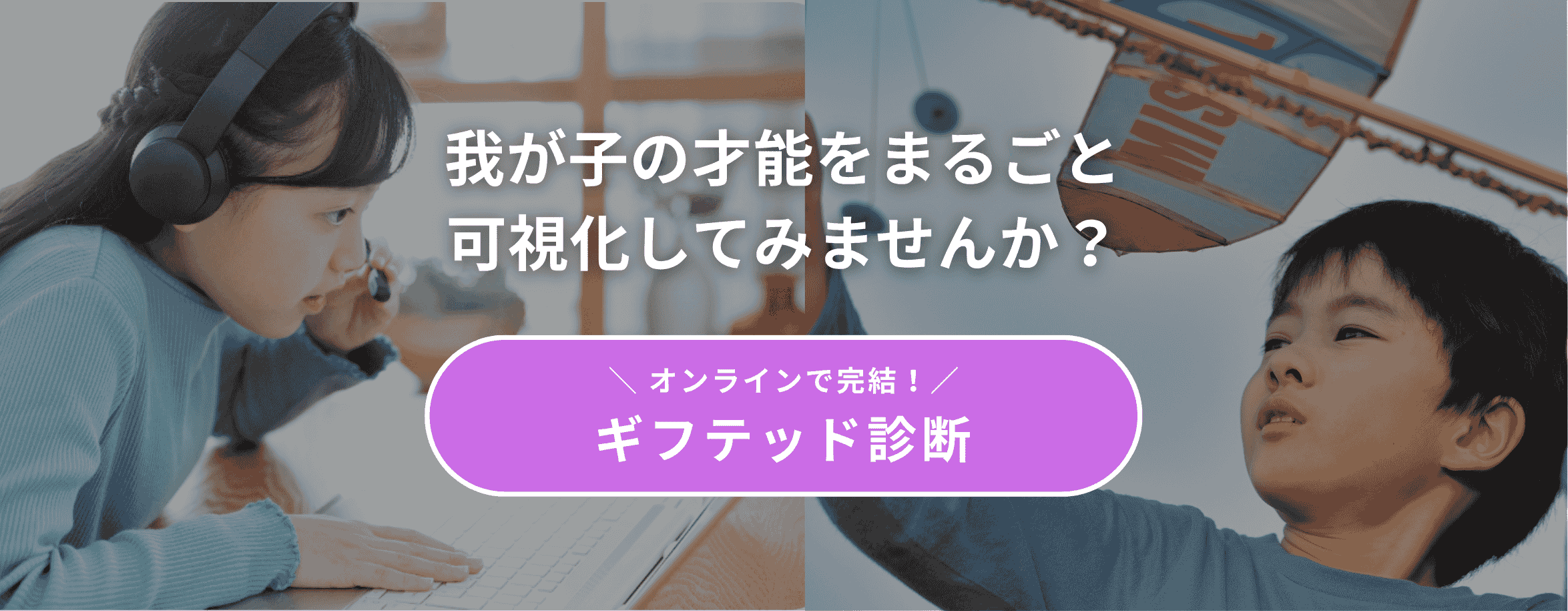

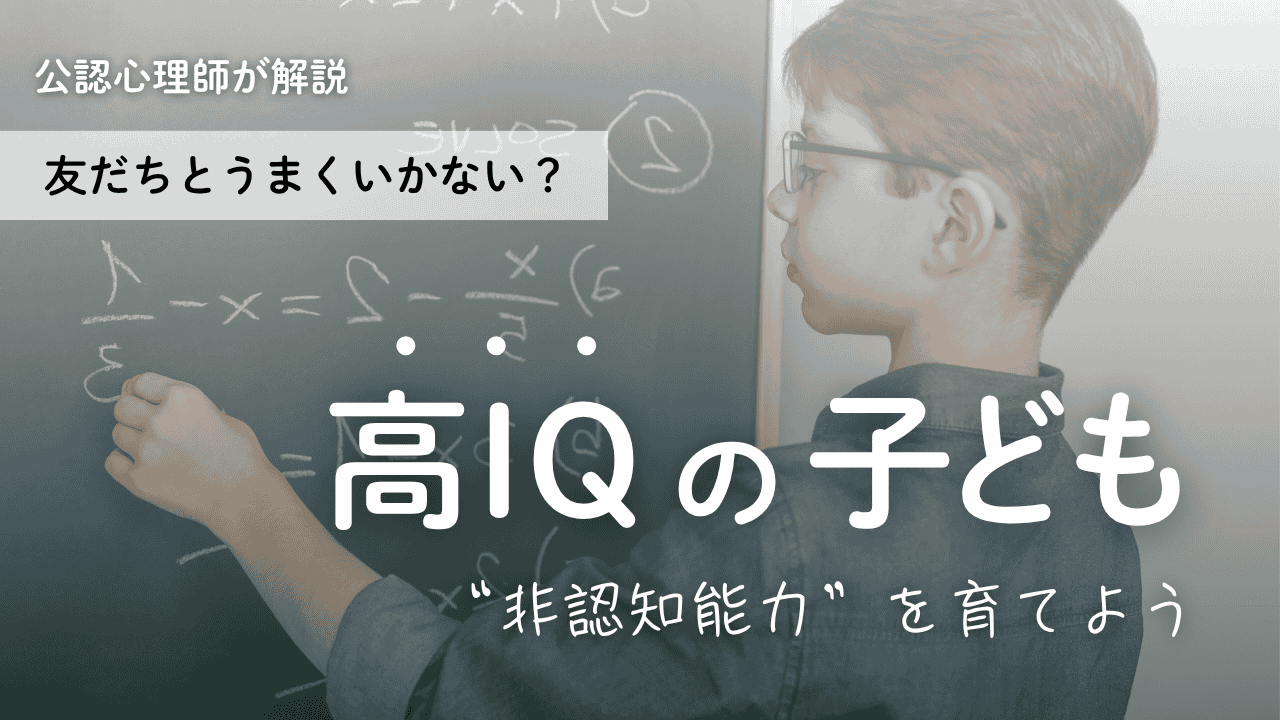
を専門家が解説.png)
