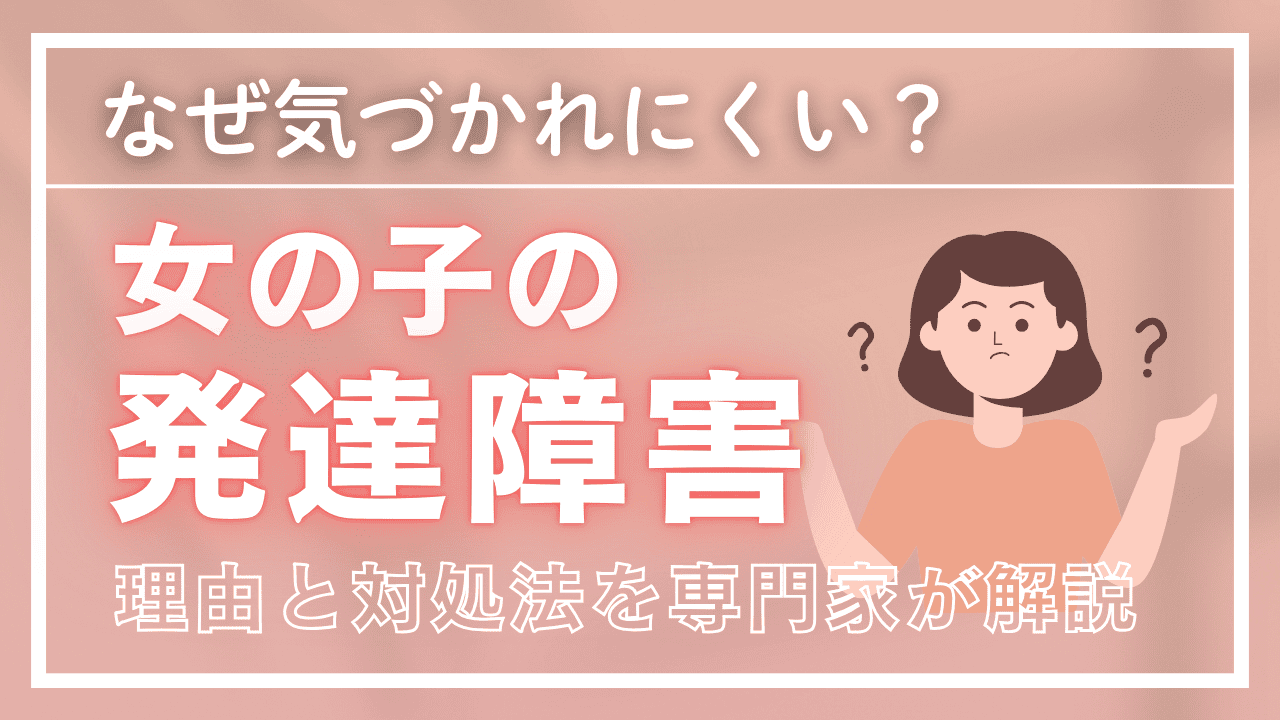ただでさえ「親」という立場は、非常にやることが多くて責任が重くて、試行錯誤しながらがんばっている方が多いと思います。
特に、ADHDやASDなどの発達障害を持つ父親・母親は、子育てにおいても周りにはわかってもらいにくい悩みを抱えていることがあります。
今回は、大人とと子ども両方の発達障害の方と多く関わってきた臨床心理士・公認心理師である筆者が、親が発達障害の場合の子育てについて気をつけるべきことを詳しく解説します。

執筆:いけや さき
公認心理師・臨床心理士
精神科病院、療育施設、心療内科・児童精神科クリニックなど主に医療と福祉領域にて心理士として従事。発達障害の子どもたちや保護者、女性のメンタルヘルス等のサポートを行う。
親が発達障害でも子育てはできるの?
結論からいうと、発達障害だから子育てができないということはありません。
筆者は、これまで約10年さまざまな親子と出会ってきました。子育ての中では悩むことは発達障害であろうとなかろうたくさんありますよね。
ただ、発達障害の親御さんは、「困った」「どうしたらいいんだろう」「私だけ?うちの家庭だけ?」と思うことが多くなりやすいでしょう。
以下でご紹介する“小学生の子育てで気をつけること”を参考にしてみてください。
小学生の子育てで気をつけること3選
今回は「小学生」と書いていますが、小学生ではない子どもの子育てでも役立つものばかりです。
3つのポイントをご紹介します。
気をつけること①話を否定せず聴く
小学生以降の親子のコミュニケーションは「対話」や「外出」がメインになり、印象に残ります。
しかし高学年以降は、徐々に子どもの外出や会話の相手は友達へと移行するでしょう。対話は小学生に限らず、大人になってからも重要なコミュニケーションです。
親子の雑談時間を大切にしてみましょう。たとえば「今日はどんなことをしたの?」「難しかった授業は?」「休み時間は誰といるの?」など、学校のことを聞いてみるのもいいです。
そのとき、子どもが親の価値観とは違う行動をしていても否定せず、まずは気持ちを受け止めてあげることが重要です。
気をつけること②プロセスを認め、具体的に伝える
親自身が、失敗を怒られた経験はありませんでしたか?
発達障害の方は、どうしても苦手な面に注目されやすく、自身もネガティブな面や結果に目が向きやすくなるのです。
自分自身と子どもの行動のプロセス(過程)を認めましょう。
たとえば、「毎日○○してたもんね」「音読よくがんばってたもんね」など何がどうしててすごいのかを、具体的に伝えてみてくださいね。
また、できたときだけじゃなく上手くいかなかったときも「悔しかったね」「また次やってみよう!」と感情に寄り添って言葉で伝え、過程を認めていきましょう。
気をつけること③親自身が自分への理解を深める
同じ発達障害でも、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)では症状が違います。
ほかにも、同じASDやADHDでも出現する症状にグラデーションがあったり、抱えている悩みが異なるのです。
子どものことだけでなく、親自身も自己理解を深めて対処法を考えていけるといいでしょう。
カウンセリングを受けている保護者の方もたくさんいますし、日常生活に支障をきたしている場合はクリニックでの受診も検討してみてください。
父親・母親が発達障害の場合に子育てで困るポイント
ここからは、親が発達障害だと子育てにどんな影響を与えるかについて解説します。
1. 家事育児・時間管理が苦手
家事育児や予定の管理など、段取りが必要になる作業が苦手な方は多いです。
パートナーや周りの人から、あれこれ指摘されることもあるかもしれません。
「できなきゃいけない」というわけではないので、自分なりの工夫を見つける必要があります。
たとえば、火を使う調理はほかの作業をしない、アラームやリマインドなどを活用するなどはおすすめの方法です。
2.子どもとの接し方がわからない
特にASD傾向のある親が悩みやすいかもしれません。
「何を話したらいいか」「何をして遊べばいいか」など、行動に移せない場合もあるでしょう。
相手の感情や「してほしいこと」を察することが苦手な人も多いといわれています。
3.子どもの提出物管理が苦手
時間管理と似ていますが、提出物や予定管理が苦手な方もいます。
その場の同時進行の作業と異なり、長期的に計画立てて覚えておく必要もあり、特にADHD傾向の親は苦手になりやすいです。
受け取ったものを入れる専用のボックスや、家族全員がわかるところにカレンダー貼って書いておくなど、みんなで把握するといいかもしれません。
4.ママ友づきあいで悩みやすい
ASD傾向の親も悩みやすいですが、ADHD傾向の親も悩みやすいといわれています。
ASD傾向だと、上の②と同様に接し方に悩んだり、関心のない話題に入ることへ苦労する人が少なくありません。
ADHD傾向では、距離が近すぎてしまったり、失言してしまったりすることがあります。
対人コミュニケーションがつらく感じる人も多いです。
ADHDとASDどちらの傾向もあると、自分でもどうしたらいいかわからなくて混乱する人も少なくありません。
5.完璧を求めやすい
発達障害の特性として、高い理想やこだわりを持つところがあります。
家事育児を「きちんとしなくてはいけない」と捉える人も多く、育児書通りにいかないことへ思い悩む人も少なくありません。
また、子どもへの影響につながりますが、家族に完璧を求めてしまうこともあります。
父親・母親が発達障害で生じる子どもへの影響
親が発達障害だと、絶対に影響が出るということではありません。
しかし、生じる可能性のある影響を知っておくだけでも、子育てで問題に直面しても対処しやすくなると考えられます。
親の二面性による戸惑い
発達障害を持つ親の態度や感情の違いに、子どもが混乱したり、戸惑ったりすることがあります。
発達障害の人のなかには大人になるにつれて、社会適応のために行動を身につけていく人がいるのです。
しかし、家庭では意識せず過ごすことが多いため、家庭内と外でのギャップが生じることがあります。
また、感情のコントロールが難しいと感情的になることがあります。子どもは萎縮してしまい、傷ついたり、次からは何もできなくなったりしてしまうのです。
子どもの自己肯定感が低くなる可能性がある
不本意に注意されたり、否定されたりし続けると、子どもの自己肯定感は低くなります。
自己肯定感とは、自分の存在価値を理解し、肯定的に受け入れられる感覚のこと。みなさんはありのままの子どもを受け入れ、愛情表現をしていますか?
子育てをしているとなかなか難しい場面もあると思いますが、積極的に子どもの良いところや楽しそうにしているところへ目を向けてみてください。
普段から愛情を伝えていれば、必要な時に注意したとしても自己肯定感が低くなるリスクは少なくなるでしょう。
関連ページ:子どもの自己肯定感のホントのハナシ
子どもが過剰適応するようになる
親の感情のコントロールが難しい場合、機嫌をうかがう子どもになりやすいといわれています。
「大人しくていい子」「言うことを聞く子」が困ってないとは限りません。言いすぎていないか、求めすぎていないか考えてみてくださいね。
関連記事:学校では「いい子」。なかなか理解されない「過剰適応」とは?
問題行動化する
お互いに思うような親子関係が築けず、子どもが注目を求めるようになることもあります。
最初は自分のできたことを伝えてきますが、親の反応によっては問題行動化して注目を集め始めるのです。
悪いことをしたときにすぐ怒っていませんか?がんばっていることや楽しそうにしていることに関心を示していますか?
「試し行動」とも言われますが、悪さをして親の反応を獲得しようとする子は一定数います。
親とのコミュニケーションが減る
上でご紹介したような親の言動により、親と積極的に会話しようとしなくなる子がいます。
親を恐れているパターンもあれば、親の言動によって会話を諦める子もいるのです。
「最近子どもの方から話しかけてこなくなったかも…」と感じたら、ご自身の言動を振り返ってみることで気づくことがあるかもしれません。
親が発達障害のときの子育て相談は
発達障害を持つ親は、周りと共有しにくい悩みを抱えていることがあります。
基本的には症状の影響で悩みますが、周りの人にあれこれ言われると抑うつ状態になる可能性も少なくありません。
『発達障害+抑うつ状態』となると、さらに子育てで苦しくなることが増えていきます。
1人で抱えず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
Gifted Gazeでは、子育て相談のプロである医師や心理士がオンラインで相談を承っています。お気軽にお問い合わせくださいね。


とは?サインや特徴などを徹底解説-2.png)