学校行事が好きな人にとって、学校に行くことを「嫌」と思う気持ちは不思議に感じるかもしれません。
しかし、特に運動会や遠足、音楽会、修学旅行などを「嫌」と感じる子どももいます。
そんなとき、話を聞かずに「行けば楽しいから」と言うことや、「行事は参加するもの」と強制することはオススメできません。行事がますます嫌な思い出となり、親に相談しにくくなる可能性を増やすからです。
では、どうすればいいのでしょうか?
今回は、学校行事を嫌がる小学生の子どもを持つ保護者さまに向けて、原因と対策を紹介します。発達障害以外にも原因は考えられるので、ぜひ最後まで読んでみてください。
発達障害/発達凸凹とグレーゾーンに関する記事一覧はこちら。

執筆:いけや さき
公認心理師・臨床心理士
精神科病院、療育施設、心療内科・児童精神科クリニックなど主に医療と福祉領域にて心理士として従事。
子どもに学校行事を「休みたい」と言われたら?
子どもが学校行事を「休みたい」と言った場合に保護者さまができることは…
1.受け止めたうえで話を聴く
2.安心感を与える
3.身体への影響も考える
このようなものが考えられます。
まず、「休みたい」「行きたくない」に対して否定したり、怒らないようにしましょう。その代わり、受け止めて聴くことを意識してみてください。
ただし「どうして?」「なんで?」という聞き方は、子どもにとって詰問や尋問となります。
「行きたくないんだね、わかった」など、本人の想いを一旦受け止めましょう。
そのうえで「気持ちを話せそう?」「嫌なことや怖いこととかがあるのかな?」と落ち着いて穏やかに聴くこと。それが安心感を与えることにもつながります。
特に子どもの場合は、不安や恐怖心が身体症状となって表れやすいです。
理由はうまく話せないとしても、食欲や睡眠、腹痛、頭痛などの症状がないか気にかけてみましょう。
参加させず、休ませることも長期的に見ると必要な選択肢です。
学校行事を嫌がるのはなぜ?
ここでは、学校行事を嫌がる原因として考えられることを解説していきます。
なお、発達障害を思い浮かべる方も多いですが、「行事を嫌がる=発達障害」とか、「不登校=発達障害」ではありません。
– 子どもが行事を嫌がる主な原因 –
発達障害(神経発達症)
普段の授業と異なり、学校行事は特別なイベントです。
発達障害の子どもにとって、学校行事は「未知の世界」にいくようなもの。
ワクワクするよりもドキドキの方が多くなってしまいます。
特に、発達障害の子どもの場合、見通しが立たないことへの不安、集団行動に対する苦手意識、感覚過敏による大きな音や日差しの強さがつらく感じることが多いです。
不安障害や心身症
子どもでも不安障害を発症する子はいます。
発達障害と合併している子もいれば、不安障害のみの子もいます。
特に、低学年なら分離不安が見られますが、ほかにも全般性不安障害や社交不安障害、強迫性障害なども小学生の子どもが発症することはあります。
また、小児心身症(気管支ぜんそく、過敏性腸症候群、アトピー性皮膚炎など)の子もいつもと状況が変わる学校行事に不安を感じやすいです。
アトピー性皮膚炎は発達障害との合併率も高いので、原因を1つと考えずに子どもを見る視点が重要となります。
HSC(Highly Sensitive Child:「繊細さん」)
医学用語や診断名ではありませんが、HSCの子どもも学校行事を嫌がることがあります。
HSCは非常に敏感な子、繊細な子という意味で5人に1人いるといわれる気質の定義です。
HSCの子は不安や緊張を感じやすいものの、無理してがんばったり、人の気持ちに応えようとしてしまう子もいます。「大丈夫」という言葉を鵜呑みにしすぎず、適度に見守りましょう。
HSP/HSCについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
友達が少ない、居場所がない
授業と学校行事の異なる点は“自由時間”や“集団行動”の違いかもしれません。
普段の学校生活なら別のクラスに行ったり、1人で数分過ごせば次の授業時間になりますよね。しかし、学校行事になると基本は集団行動です。
いつも一緒にいない子たちの中に入れてもらう必要も出て、窮屈な気持ちになる子どももいるでしょう。
その際、保護者さまはいじめや仲間外れの可能性とそのほかの理由を思い浮かべながら、話を聞いてみてください。
内気など性格傾向
不安になりやすい小学生や内気であったり、大人しいタイプの子どももいます。
学校行事は、盛り上がることが好きな小学生たちからしたら楽しいでしょう。
しかし、静かにしていたい子にとっては「嫌だな」「行きたくないな」「緊張するな」と思うのは自然なことかもしれません。
子どもは元気に楽しく!と強制させないことが、静かなタイプの子たちの安心感につながります。
該当する学校行事への苦手意識
それぞれの学校行事に苦手意識を持っている場合もあります。
例えば運動会なら「走るのが苦手」「組体操が苦手」、音楽会なら「歌やハーモニカが苦手」など、行事内容への苦手さが嫌がる原因の可能性も考えられるのです。
しかし、練習すればいいという問題ではないこともあります。DCD(発達性協調運動障害)の可能性も考え、理解を示すことも大切です。
ほかにも、周りから「下手」「できてない」と指摘されて嫌になったり、緊張しやすくなった可能性もあります。
参加を嫌がる子どもの気持ちに寄り添ってあげましょう。
子どもが嫌がることなく参加するための準備とは
最後に、子どもが学校行事を嫌がることを防ぐための準備を紹介します。
親が決めつけず、コミュニケーションを取る
日頃のコミュニケーションが、本音の話しやすさやこの後紹介する別の対策の取り組みやすさにつながります。
小学生の子どもでも、自分の中にあるモヤモヤした気持ちや不安を「自分なりに」話すことはできるでしょう。
しかし、話せるようにするためには保護者さまが環境や状況を作り出してあげる必要があります。
きっかけがあると話せる子もいれば、「上手く話せない」と躊躇する子もいるでしょう。詰問や尋問にならないように気をつけつつ、原因を選択肢として「あれかな?」「これかな?」と提示するのもいいかもしれません。
そもそも日頃から学校の話を聴いたり、そのほかにも会話や遊びを一緒に楽しむ時間も大切にしてみてくださいね。
行事は何をするものか伝える
特に発達障害の子どもなど、先の見通しが立たずに不安を抱く子に有効です。
イラストや写真、図面などを用いて伝えるなど、行事でどんなことをするのかを伝えてみましょう。何に不安を感じるか、困りそうなのかをあらかじめ整理することで、「○○のときはこうする」という具体策も考えられます。
一方で、学校によって行事内容が異なることもあるでしょう。
できれば保護者様だけで抱えずに、小学校の先生やスクールカウンセラーと連携をとって、チームとして考えられるといいですね。
現地の下見やシミュレーションをする
学校外の行事は下見やGoogleマップなどを使って、現地を下見しておきましょう。
トイレの位置などを確認するのも、行事参加の安心感につながります。
校内で行われる場合も、実際に足を運んでシミュレーションできるといいですね。過去映像を学校が保存している場合は、映像を見せてもらうのもいいかもしれません。
参加できる形を子どもと一緒に考える
無理にみんなと同じように参加することを目的にしないようにしましょう。
「午前中だけ」「この時間だけ」など時間で区切り、もう少しいられそうだったら延長するのもいいかもしれません。
また、運動会ならクラス席や見学する席に座って、応援する役割を担うのもいいですね。
参加できる形を模索する際は、学校の先生やクラスで協力してもらえる人がいないか声をかけたり、理解してもらえるように事前に説明することも重要です。
おわりに
主に小学生の子ども向けに、学校行事を嫌がる原因や対策を紹介しました。
紹介した内容は小学生のときだけでなく、中学生以降にも活かせます。
特に高学年以降は、宿泊行事や遠方への遠足などもありますよね。
克服させたい気持ちもわかりますが、無理やり参加させたときに嫌な思いをするのは子どもです。
紹介した内容は保護者さまだけでがんばろうとせず、小学校の先生やスクールカウンセラー、医療機関などと協力するようにしましょう。家族だけで抱えないことが保護者さまと子どもの心身にとって重要となります。
Gifted Gazeの専門家相談も相談先の1つとして、ぜひお気軽に頼ってください。
参考文献
高 賢一,学校行事に参加できない生徒の対応に関する事例研究,日本特別活動学会紀要第10号2002.3
天野 菜穂子,不安を抱く不登校児への心理的対応―「学校がこわい」と言う不登校児への理解と支援―,人間福祉学会誌 第21巻 第2号,2022
発達障害/発達凸凹とグレーゾーンに関する記事一覧はこちら。






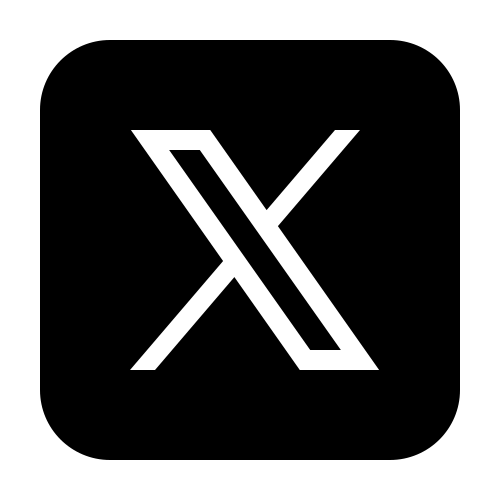




が高い子どもは育てにくい?育て方のコツ5選を心理士が解説-1.png)