自分の意見やアイデアを自由に表現して、伝えた意見が尊重されることは、私たちが人として、社会で価値を感じることができるプロセスの一つです。
特に、私たち大人が子どもの意見に耳を傾けるということは、子どもたちが自分の考えや意見が大切にされていると感じことができるため、社会的スキルや責任感も身につけることができる最高の方法なのです。
一方で、親御さんからすると、子どもの意見を聞いていたら日常での物事が進まなかったりして、尊重することのバランスが取りにくかったりするかもしれません。
教育先進国の一つであるスウェーデンでは、子どもたちの意見を大切にする文化が浸透していて、世界中から注目されています。
本記事では、スウェーデンの教育制度から学べるアプローチをご紹介しながら、大人が子どもの意見を大切にする文化を家庭内で育む方法についてもお伝えしていこうと思います。
目次
子どもの意見を尊重することの効果と重要性
耳を傾けられているという安心感を感じることで、子どもたちが自信を持って自分の考えや感情を表現できるようになり、社会的スキルや問題解決能力などの非認知能力を育むためにも大変効果的です。

具体的に、子どもに耳を傾けることでどのような効果があるのか、その一部をご紹介します:
自己肯定感が上がる
子どもたちが自分の意見を表現する勇気を持ち、それが尊重される環境にあると、子どもたちは進んで新しいことに挑戦しようという気持ちになり、自信につながります。つまり、自己肯定感が高まります。
自己肯定感が高い子どもは、失敗を恐れずにチャレンジするだけでなく、失敗から学び、立ち直る回復力も高いのです。
自己肯定感が高いと、そうでない子どもたちと比較して学習の機会を広げることができることもわかっています。
批判的思考力が育まれる
自分の意見を表現するというプロセス自体が大切です。子どもたちは、意見を述べるために情報を分析し、論理的に考える能力の土台を少しずつ築いています。
こうして集めた情報に基づいて、自分なりの結論を出すことを学ぶのです。
自分の意見を誰かが聴いているという実感があると、子どもたちはより一層目の前にある問題に対して、創造的で実践的な解決策を見つけ出そうとします。そして自然と批判的思考力を育むことができます。
コミュニケーションスキルが上がる
身近な大人が子どもに耳を傾けることで、その子どもたちも同じように周りに耳を傾けるようになります。
そして、意見を交換する中で、周りの人との効果的なコミュニケーション方法を学んでいきます。
周りの意見を理解すること、自分の意見を効果的に伝えること、適切に反応することを統合的に学ぶことができる素敵なプロセスです。
効果的にコミュニケーションが取れると、将来の社会生活において幸福度が高まることもわかっています。
こちらの記事では、コミュニケーションスキルに関連して、非認知能力と幸福度の研究も紹介しています。
子どもに耳を傾けることは、子どもたちの自尊心、社会的スキル、そして批判的思考力を育むための基礎となることがお分かりいただけたかと思います。
親や教育者が子どもの声に耳を傾け、その意見を尊重することで、子どもたちは自分が社会の価値ある一員であると感じ、そのプロセスの中で、多くの重要なスキルを身につけることができます。
スウェーデン教育の具体的なアプローチ
北欧は、元々教育の先進地域としても知られていますが、中でもスウェーデンは、子どもたちの意見を聞くことの効果がよく出ている社会の一つです。
スウェーデンの就学前教育は「Skolverket(スクールヴァルケット)」という機関が担っており、日本の文部科学省に相当します。
具体的にどんなシステムになっているのか、以下で紹介します。
大切にされる「子どもの権利」
スウェーデンでは、学校でも家庭でも子どもたちの声を積極的に取り入れる文化が浸透しています。
大人も子どもも、自らの意志を示すことができるかどうかがとても重視されています。
特に子どもの権利については、子どもの意見表明と参加の権利を定めた「子どもの権利条約」の第12条にも明記されている通りです。
子どもの権利条約(Convention on the Rights of the Child、CRC)は、1989年に国連で採択された、子どもの権利に関する国際条約でスウェーデンもこの条約の締約国の一つです。
(日本も、1994年にこの「子どもの権利条約」を批准しています。)
この条約の第12条は「意見を表す権利」に関するもので、子どもが自己に関わるあらゆる事項において、自由に意見を表明する権利を持つこと、またその意見が考慮されるべきことを定めています。
具体的には、子どもが自分に影響を与える決定や事項について意見を述べ、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきであるという原則を確立しています。
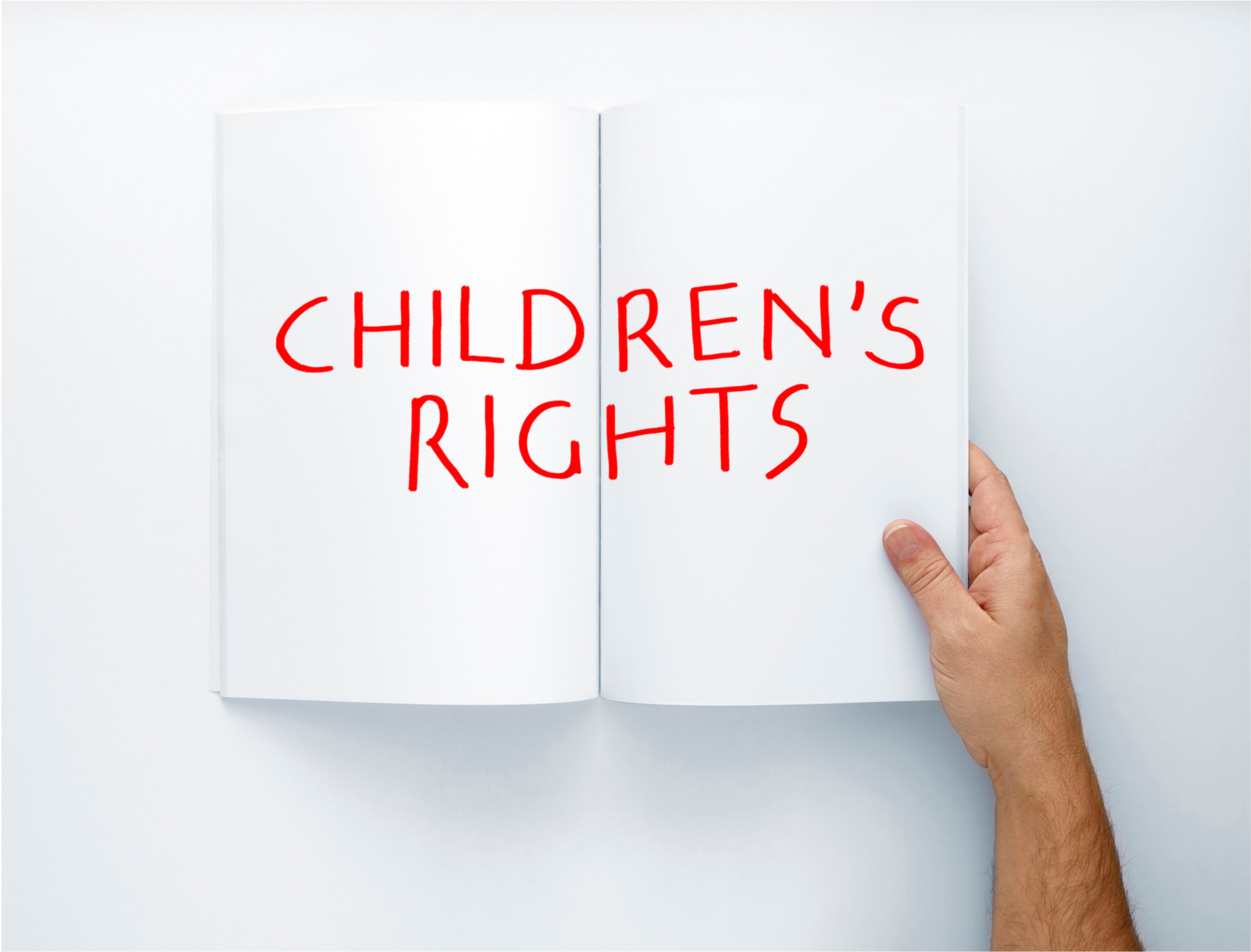
就学前教育のカリキュラム
スウェーデンの就学前教育(5歳ごろまで)は、子ども一人ひとりの学びと発達を支援するための指針があり、子どもの自立、協力、創造的な学びを重視しています。
子どもの意見が、日々の教育活動において尊重されるべきであると明記されているほどで、幼い時から子どもが自分の意見を表明し、参加することの重要性が強調されています。
幼い頃から徹底して教えられているのが、民主主義の基礎と人間の価値の平等さです。
教育現場では、遊びを通じて学ぶことが重視され、物語を作ったり、ものづくりをしたり、グループディスカッションを行うなどの活動もたくさん含まれています。
こうした活動の中で、子どもたちは自分の考えや意見を表現する機会が豊富に与えられます。
言葉を上手に話せない子や、障害を持つ子も含めて、全ての子どもたちが遊びの中で学び、自然に他の子どもたちと交流します。
このような教育方法を「インクルーシブ教育」と言います。
このようにして、子どもたちはお互いを尊重し合いながら学ぶ環境が作られるのです。
また、このようなカリキュラムは、子どもたちが社会の一員として責任を持って、周りと協力して問題を解決できるようになる効果もあります。
こんな幼い頃から、と思われるかもしれません。
将来社会を支える子どもたちが、自分の声が誰かに届いて、そしてその声が何かを変えるきっかけになるかもしれない、と思える心を幼い頃から育む重要性が読み取れます。
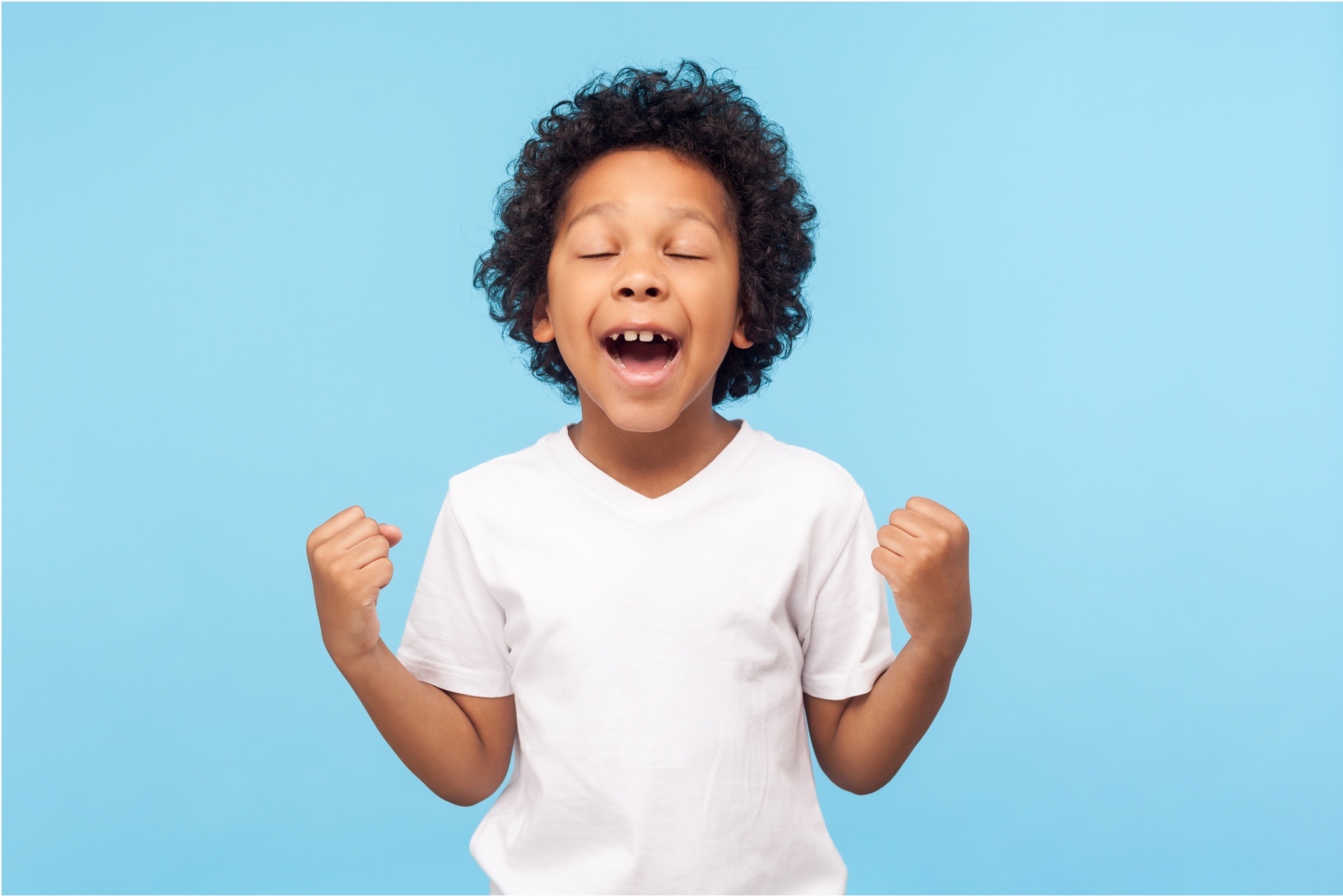
スウェーデンの教育シーン
ここで一つの映画をご紹介しましょう。「ロッタちゃん はじめてのおつかい」です。
本作の主人公、小さくて可愛い女の子、ロッタちゃんの物語です。
ロッタちゃんの物語は、子どもたちが自分の意見を持ち、それを表現することの大切さを伝えてくれるのですが、さらに大人が子どもの意見に寄り添う反応がとても素敵です。
スウェーデンの教育哲学がたくさん盛り込まれているので、ぜひご覧ください。
ロッタちゃんは5歳。ある朝、ママが出してくれたセーターがチクチクすると言って、ハサミで切り刻んでしまった彼女は、なんだか気まずくなってお隣のベルイおばさんの家へ家出をしてしまいます。
https://lotta-eden.jp/
クリスマスのモミの木が売り切れで、ツリーが手に入らないニイマン家。お兄さんもお姉さんも泣いてばかりいるけれど、ロッタちゃんはあきらめません!
復活祭の前日、パパがイースター・エッグを買い忘れてしまいました。けれども、ロッタちゃんには名案がありました。
『ロッタちゃん はじめてのおつかい』(1993年製作)
原題:Lotta flyttar hemifràn
公式サイトリンク
スウェーデンでは、子どもたちが持つ権利と彼らの意見を尊重する文化が、国の教育システムと法律の両方に深く根付いています。
スウェーデンの教育や社会全体が子どもたちの意見を大切にし、彼らが自身の可能性を信じて行動できるようサポートしている様子は、見習うべき点が多くあります。
子どもたちが自分の意見を自由に表現し、さらに自らの意思決定に責任を持つことを学ぶことで、子どもたちは自尊心を高めて、自立した社会人になっていくのでしょう。
子どもの意見を尊重することと甘やかすこと
家庭内では、小さなことでも子どもと意見交換したり、子どもの意見に対して、真摯に耳を傾け、肯定的なフィードバックを与えることが大切です。
一方で、子どもの意見を尊重することが、結果的に甘やかすことになったり、過度に子どもの意見を取り入れることにつながらないか、気をつける必要もあります。
責任感や社会的スキルを学ぶためにも、適度な限界と制限を設けることがポイントです。
大人としては、子どもたちがこのバランスを取れるようにしたいのですが、具体的にはどのようなアクションが必要なのでしょうか。
以下に、いくつか紹介します:
理解を示す
子どもが何かを伝えようとしたときは、話を途中で遮らずに最後まで聞きましょう。
そして、子どもたちの意見や感情を理解し、「そうかもしれないね」「なるほどね」など受け入れたことを示すリアクションしましょう。
子どもは、自分の意見が尊重されていると感じさせることで、自信を持って自分の考えを表現する勇気を持てます。
選択肢を提供する
選択の自由を与える際には、子どもが管理可能な範囲の選択肢としましょう。
例えば、「赤のTシャツと青のTシャツ、どちらを着たい?」と聞くことで、自己決定能力を尊重します。
子どもに選択の自由を与えることで、自立心を養いますが、選択肢を限定することで過度な期待や混乱が生まれたり、危険な状況となることを防ぎましょう。
規則と限界を設定する
家庭内でのルールを明確にし、子どもがこれらの規則を守ることの重要性を理解させ、同意させましょう。
同意させるまでがポイントです。規則を破った場合の結果もあらかじめ説明します。
規則とその理由を説明すること、また自分自身が同意したことで、子どもは社会的な振る舞いや責任感を学びます。
肯定的な強化を行う
子どもが良い行動をしたときには、積極的に認めてその行動を強化しましょう。
ご褒美に何かをあげる時にも、子どものリクエストに応じるのではなく、その内容や行動が家庭のルールや価値観に沿っているかを一緒に考えた上で対応しましょう。
説明する
子どもの意見や要望に対して「NO」と答える場合は、その理由をできるだけ子どもが納得できるように説明してください。
可能であれば、代替案を提案することもいいでしょう。
単に要求を拒否するのではなく、その理由を理解させることで、子どもは思考の過程を学び、納得し、将来的にも子どもたちは自分自身でもより良い決断を下せるようになります。
おわりに
子どもの意見に真剣に耳を傾ける大人たちの姿勢を見て、子どもは「自分の意見を聞いてくれる人がいる」「自分の意見は大切にされていいんだ」と感じることができます。

スウェーデンの教育制度から学べるアプローチを取り入れ、大人が子どもの意見を大切にする文化を家庭内で育むことは、子どもたちが自信を持ち、社会の一員として活躍するための大きなヒントとなります。
子どもの意見を尊重しつつ、適切な規則と限界を設けることで、社会で必要とされるスキルや責任感を身につけながら、自分の声が大切にされていると感じることができます。



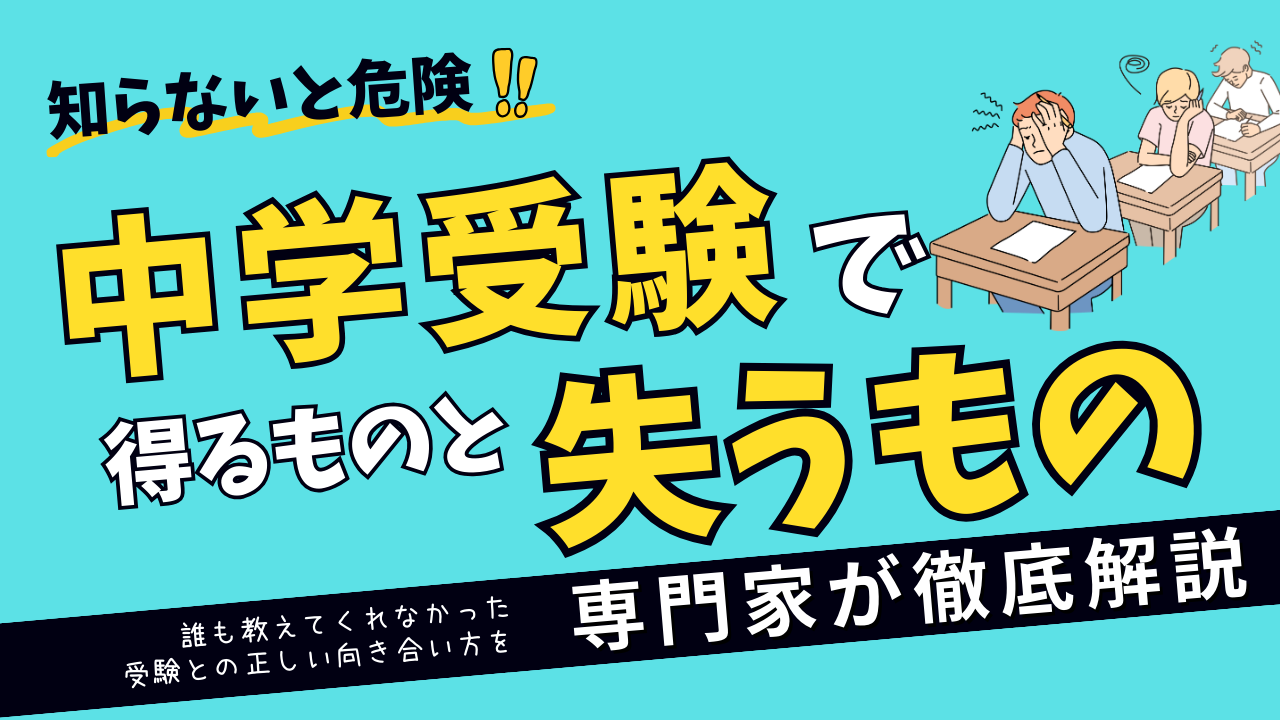



」入門.png)


