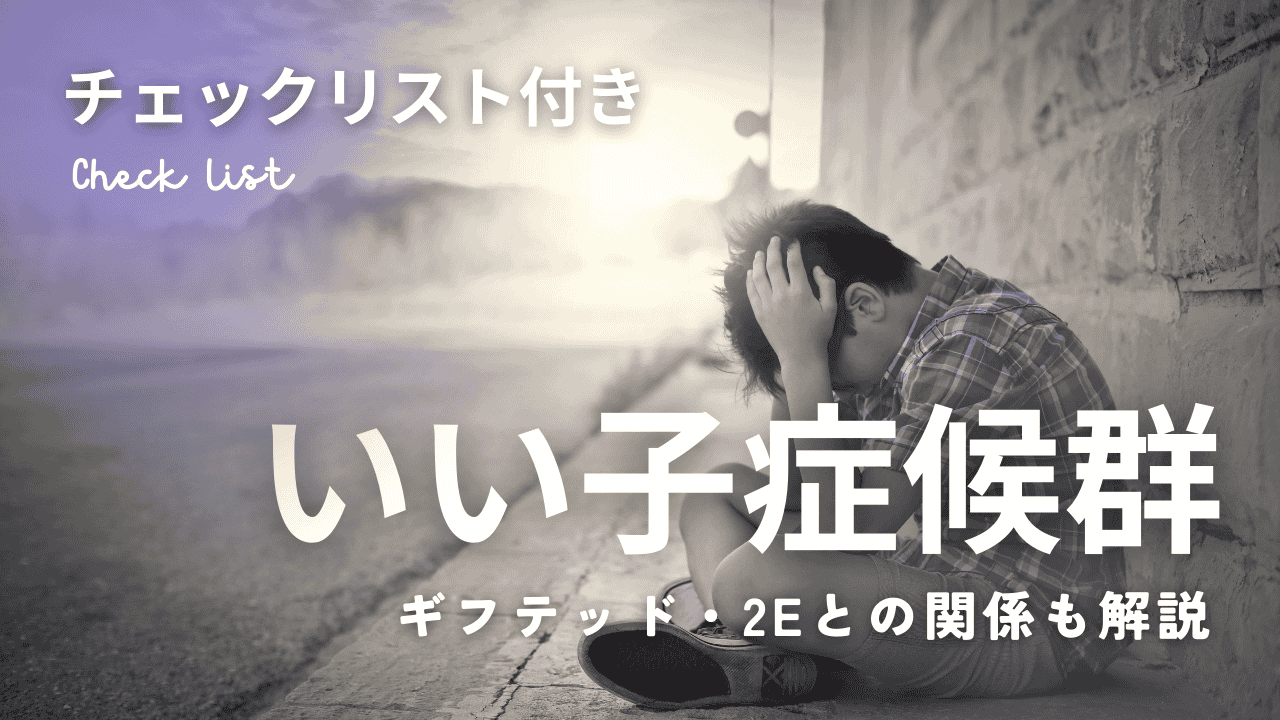学力やIQなどは「認知能力」と呼ばれていますが、この「認知能力」とは異なる、「非認知能力」というものが、子どもたちが将来幸せで充実した人生を送る上で非常に重要な役割を果たします。
最近では耳にする方も増えたのではないでしょうか。
今回は、この非認知能力の要素の一つである「外向性」について解説してきます。
非認知能力とは
「非認知能力」とは、学力やIQなどに代表される「認知能力」以外の能力のことで、人間の内面的なスキルです。
非認知能力は将来の幸せの指標とも言われており、子どもが豊かな人生を歩んでいく上で大切な「力」です。
非認知能力には様々な要素があり、それぞれの要素は周りの人との関わり合いの中で育み、時間と共に発達していくものです。
非認知能力は、能力という位置づけで捉えられたり、性格の一つの側面としても捉えられることもあります。
非認知能力についてはこちらの記事で詳しく説明しています。
「外向性」について
「外向性」とは、社会性や活発さや外界への興味関心の強さを言います。
他人との交流を求める程度、活動的でエネルギッシュである程度、またポジティブな感情を経験する傾向の高さを示します。
外向性の特徴には以下のようなものがあります:
外向性が高いお子さんは、学校や地域の集まりで自然と中心的な役割を果たすことが多く、友達作りも得意です。人とのコミュニケーションを楽しみ、対人スキルが高いと思われることもあるでしょう。
そのため、大きな友達の輪を作りやすく、様々な社交的活動に積極的に参加します。これは親としては心強く、子どもが社会性を身につけている証しとも言えるでしょう。
一方で、外向性が極端に高いお子さんは、時に注意が散漫になったり、衝動的に行動する場合もあります。計画を立てたり、じっくり考えることが苦手である場合に顕著になることケースです。そのため、学校のテストや家庭でのルールが守れないと感じる場面も出てくるかもしれません。
また、外向的なお子さんは自己反省の機会を持つことが多くはなく、一人で静かに過ごす時間が苦手かもしれません。
保護者の方はお子さんに内省的な活動も積極的に取り入れることを勧めると良いでしょう。
例えば、読書や絵を描く時間を持たせることで、心のバランスを整え、感情のコントロールを学ぶことにもつながります。
なお、子ども時代に外向的な特徴を示す個人は、成人してからも多くの場合、社交的で活動的な性格を持ち続けることが多いです。
外向性は、将来特に交渉やチームマネジメント、顧客対応といった場面では、この特性がプラスに働くことが多いためビジネスや経済活動が活発な環境で効果を発揮します。
積極的に人と関わり、効果的なコミュニケーションを取る能力の一つとも言えます。
外向性を高める日常生活での実践方法
大人として、子どもの外向性を高めるために日常生活で取り入れられる具体的な方法をご紹介しましょう:
1. 社交的な活動への参加を促す
子どもをいろいろな社会活動に参加させましょう。
未知の状況に直面することは、子どもが自己効力感も育み、自信を持つきっかけにもなります。
異なる背景や価値観との交流を重ねていくことで、子ども自身も新しいコミュニティでの活動への抵抗も減っていきます。
重要なのは、子どもが興味を持つ活動を選ぶこと、そして、楽しみながら自然に社交的なスキルを磨ける環境です。
初めは不安を感じたり合わない友達もいるかもしれませんが、少しずつチームワークや協力の難しさと重要性を学ぶことができます。
社会に出て、異質なものとぶつかるという経験を乗り越えていくための重要な機会になります。
具体的には、以下のような機会が考えられます。
- 地域のスポーツチームやクラブ活動へ参加する
- 学校外の趣味のクラス(美術、音楽、ダンスなど)参加する
- 家族と一緒に地域のイベントや祭りに参加し、様々な背景の人たちと交流する
- 親子でボランティア活動に参加し、社会貢献の重要性と共に協力する経験を積む
未知の状況への適応能力や、新しい人々との交流を通じて、子どもが自信を得る過程に重要な機会として活用していきたいですね。
2. コミュニケーションスキルの重要性を教える
効果的なコミュニケーションは、社交性を高める上で不可欠です。
子どもに、自分の感情や考えを適切に伝える方法や、相手に耳を傾ける方法と重要性を教えます。
具体的には、目を見て話す、挨拶をする、質問をするなどの基本的な習慣の大切さを伝えることから始めましょう。
日常の会話で、子どもが感じたことや考えたことを共有する時間を持ったり、家庭での夕食の時間を利用して、一日の出来事について話し合う習慣をつけるなどです。
ロールプレイを通じて、異なる社会的場面での適切な振る舞いを得じてみたりすることです。
感謝の気持ちを表現する方法、謝罪の仕方など、感情の健全な表現を教えることも、基本的なことですが重要です。
家庭内での良質なコミュニケーションが子どもの外向性を促進し、社交的なスキルも育まれるでしょう。
非認知能力の調べ方
2012年にハワード・ガードナーが提唱した「多重知能理論」(「MI理論」)は、人間の知能が一つではなく、様々な形で現れると示したものです。
この理論に基づく研究では、子どもたちが様々な活動に参加することで、異なる種類の知能が刺激され、全体的な学習能力と創造性が高まることが示されています。
多様な経験が子どもたちの知的好奇心を養い、新しいスキルの習得に対する意欲を高めることが確認されており、外向性のみならず、他の非認知能力の要素も高められるのです。
「才能発掘診断」では、非認知能力を測定するメジャーな指標「ビッグ・ファイブ」に、子どもたちの学びに向かう姿勢に影響する「自己肯定感」を加え、外向性はもちろん、他の非認知能力の要素の状態も推測することができます。
他にも、上記のMI理論に基づいて、もともと持っている知能のバランスを踏まえて個性や才能を見つけ、効果的な学び方もお伝えしています。
他者と関わりながら成長し、社会の中で生きていくための人間力を育むヒントしてみてください。
才能発掘診断から子どもたちへのメッセージ
現時点の外向性が高くても低くても、それぞれのいいところがあります。
ただ、非認知能力の各要素を一定水準高めていくことで、異なる背景をもつ人々との交流が加速され経験に深みが出たり、価値観が広がり、社会に出た時にいい影響をもたらす可能性が高いと言われています。
子ども自身のペースや性格を尊重してバランスをとりながら身につけていくことがよいでしょう。
外向性が高い子どもたちへ
あなたは、世界に対して開かれた心を持ち、新しい体験や人との出会いに対する好奇心があります。様々な興味や関心を持つことで、学びと成長の幅を広げ、人生をより豊かにするだけでなく、周りの世界にポジティブな影響を与え、人々を引き付ける力になっているでしょう。
また、誰かと一緒にいることを大切にし、楽しむため、友情を深め、あなたの人生を彩るような温かいコミュニティを築くでしょう。押しが強いと感じることがあっても、それはあなたが自分の意見や考えに自信を持っていて、目標に向かって進むための情熱を持っているからです。このような積極性によって、リーダーシップを発揮し、周りの人を鼓舞することも多いのではないでしょうか。
あなたは冒険心も持っていて、新しい挑戦に対して恐れずに取り組む勇気があります。未知のことに対する好奇心と勇気は、自分自身をさらに成長させ、人生においてユニークな経験をもたらしてくれます。
外向性が高くない子どもたちへ
あなたは一人の時間を大切にし、物事をじっくりと考えます。この姿勢は、自分の内面に向き合い、深く思考することを大切にしているからです。あなたが自分自身との強い結びつきを持ち、独立した考えができることも意味しています。
あなたのように、行動する前にしっかりと考えることができる人は、慎重で賢明な選択をすることができ、何が起こりそうか、何にリスクがあるかを考えてから行動できます。また、自分の感情や考えに深く集中し、創造力や独自性を育むことができるでしょう。
一人でいることを楽しむので、自分自身の世界を豊かにし、内面から満たされることができます。あなたの思慮深さ、慎重さは、あなたが独自の視点を持ち、深い洞察力を発展させるための土台となります。これらの特性を大切にし、自分らしいペースで物事に取り組み続けてください。
おわりに
外向性は、チームワークやリーダーシップ能力を育てる上で大きな力を発揮しますが、外向的な特性と内向的な特性の両方のバランスが子どもの健全な成長には重要です。
子どもたちが自分自身の内面と向き合う時間を持つことで、他人とのより深い関係を築く基礎となり、自己成長とバランスの取れた人生を送るための準備ができるでしょう。
私たち大人としては、子どもたちの多面的な成長を支え、子どもたちが自分らしく輝けるように見守っていくことができればいいですね。




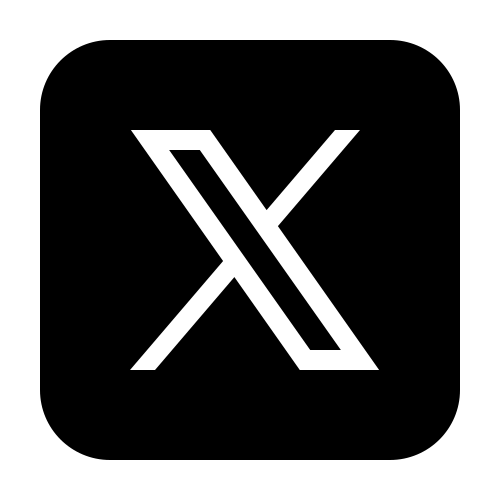
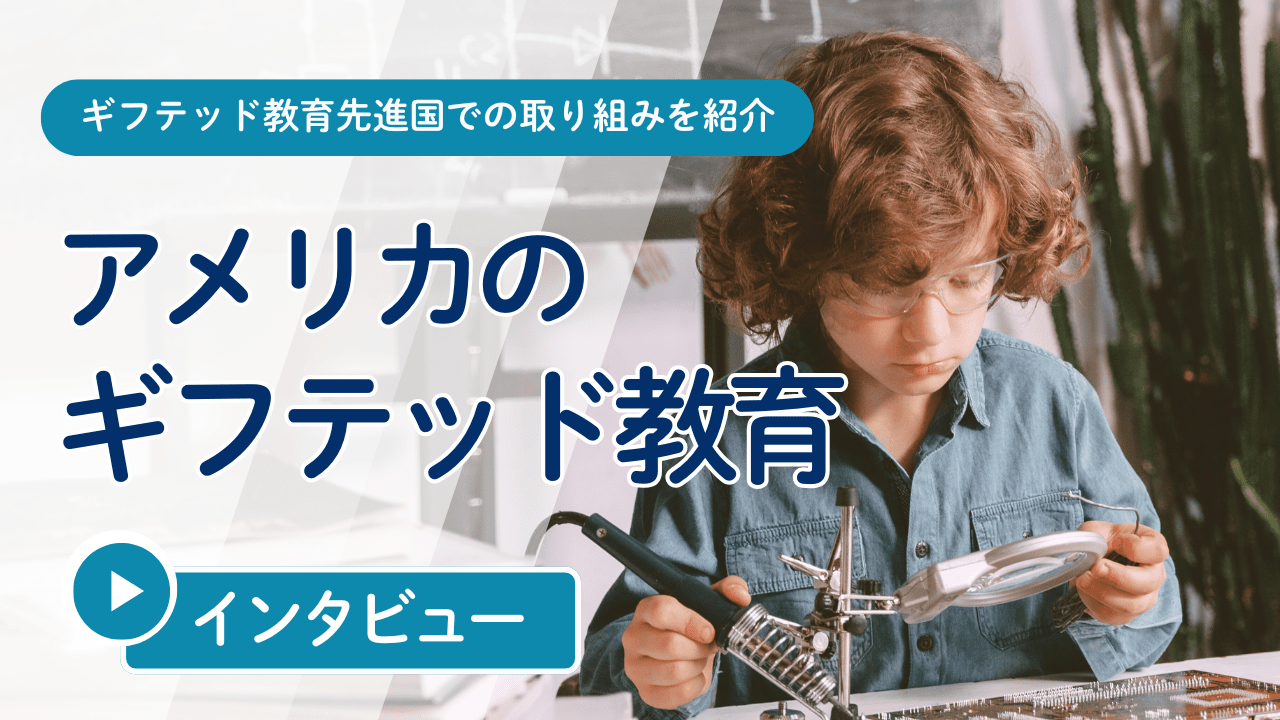


が高い子どもは育てにくい?育て方のコツ5選を心理士が解説-1.png)

」入門.png)