「シュタイナー教育」という言葉を聞いたことがありますか?
シュタイナー教育は、子どもたちの持つ個性や特性を最大限に活かしながら学ぶことを重視した教育方法です。
本記事では、シュタイナー教育の特徴をご紹介しながら、その効果と子どもたちの才能発掘に活かせるポイントをお伝えしていこうと思います。
シュタイナー教育とは
シュタイナー教育は、オーストリア出身の哲学者ルドルフ・シュタイナーによって生み出されました。(厳密には彼はオーストリア=ハンガリー帝国(現クロアチア)生まれで、彼の活動の大部分はドイツで行われました。)
1919年にドイツのシュトゥットガルトで開校された「ワルドルフ学校」が、シュタイナーの教育哲学を実践した第1号校です。
シュタイナー教育は、子どもたちが自身の特性を生かしながら学ぶことを何よりも大切します。シュタイナーは、個々の自由な思考と精神的な成長を促す教育が、社会全体の向上につながると信じていました。
この背景には、第一次世界大戦後の社会的、経済的な混乱があり、シュタイナーはこの状況に対応するための新しいタイプの教育が必要だと考えたのです。
今でこそ、個性を活かすだとか、才能に合った、という教育の重要性が各所で言われていますが、この時代にすでに子どもたちの個性を活かすことにフォーカスした教育哲学が生まれていたことが驚きです。
シュタイナー教育哲学の基礎
シュタイナー教育の特徴は、学問だけでなく芸術や手作業を通じて、子どもの感情や意志に働きかけることです。
そうすることで、子どもたちの創造性や問題解決能力を育て、個性を尊重しながら協調性を高めることを目指しています。
もう少し掘り下げると、シュタイナー教育の根底にあるのが「人智学」(アントロポゾフィー)と呼ばれる哲学です。
人智学(アントロポゾフィー)は、私たちの日常の感覚を超えた深い洞察や理解を目指す考え方で、人間の精神的な成長や進化を特に重視しています。簡単にいうと、肉体以外の目に見えない存在の働きをも含めて成長すべきだとする考え方です。
シュタイナーによれば、教育は子どもたちの成長をただ学問的に支えるだけではなく、身体的、精神的、さらには霊的な面でも全面的に促進すべきだとされています。
シュタイナー教育の特徴と効果
具体的に、シュタイナー教育の特徴とその効果を以下にまとめてみます:
段階的なカリキュラム
子どもたちの成長に合わせて教育内容が組み立てられています。子どもたちの年齢や発達段階に最も適した方法を用いて、自然な学びが促されます。
各子どもの発達段階や興味に応じて教育内容がカスタマイズされることで、子どもたちは自分のペースで成長でき、自己認識と自尊心を強化します。
段階別のカリキュラムの概要は以下の通りです。
早期幼児期(0-7歳)
この段階では、子どもたちの想像力と創造性が中心になります。学びは体験を重視し、物語、遊び、芸術活動(絵画や形作り)、自然とのふれあいを通じて行われます。特に注目されるのは、リズムと繰り返しです。日々の活動、季節の祭り、お話、歌、繰り返されるゲームがリズム感を育み、安心感と世界への信頼を深めるようになっています。この時期の目標は、身体的な発展と健康な基礎を築くことであり、学問的な指導はされません。
児童期(7-14歳)
この段階では、学問的な指導が始まりますが、芸術的で創造的な方法が活用されます。シュタイナー教育では、この時期の子どもたちは感情的な経験を通じて世界を理解すると考えられています。教科は物語や芸術的な活動を通して教えられ、例えば数学は音楽やリズム活動と結びつけられ、歴史は壮大な物語として語られます。
青年期(14歳以上)
この段階になると、より知的で批判的な思考に焦点を移します。カリキュラムは、社会的な問題に対する意識を高めるよう設計されています。科学、数学、文学、社会科学、芸術など、広範囲にわたる主題が扱われますが、それぞれが子どもの個々の発達と関連付けられ、自分自身と外の世界との関係を理解し、自分の役割を見出せるよう支援します。
全人的な教育
ただの知的な学びだけでなく、芸術的、身体的、そして感情的な成長も大切にします。
児童期以降は、長期にわたって共同作業が必要とされるプロジェクトや芸術的な活動は、抽象的思考と問題解決のスキルを養います。
それだけでなく、協調性、共感、対人関係のスキルを学ぶため、将来、学校外の実世界で直面する課題への対応能力を高めることにつながります。
一つ目にご紹介した「段階的なカリキュラム」の内容からも、単に知識の習得だけでなく、全人的な成長と社会への積極的な貢献を促すことに重点を置いていることが読み取れますよね。
芸術を重視
子どもは毎日のカリキュラムの中で絵画、彫刻、音楽、演劇など様々な芸術活動に参加します。例えば、絵画では自然の風景を模写するだけでなく、自ら感じ取った感情を色や形で表現するなどです。
複数のアート展示会や地域コミュニティでの演劇公演に参加することもあります。
こうして子どもたちは多様な表現方法を学び、自己表現のスキルを高めることができます。
自然とのつながり
子どもたちは、園芸や季節の祭りなどのイベントを通じて自然と積極的に関わり、環境への敬意と理解を深めます。
例えば校内に庭園を設け、子どもが植物の成長を日々観察し、手入れをすることで季節の変化を体験したり、野外活動やキャンプを通じて、自然と直接触れ合う活動などです。
自然のリズムと一体感を感じ、持続可能性の重要性と環境に対する責任感を育てます。
教員との持続的な関係
一人の教員が同じクラスを数年間担当し続けることが一般的です。そうすることで教員は子どもたちと深い絆を築きます。
この継続性が、子どもたちに安定感と信頼が生まれ、学びの効果が高まります。
シュタイナー教育のデメリット
以上のように、シュタイナー教育はいいことづくめで、デメリットはないの?と思われる方に、以下にシュタイナー教育のデメリットをあえて挙げてみます:
- カリキュラムの柔軟性:シュタイナー教育は独特の教育理念に基づいているため、他の学校システムや大学受験のための学習については適応が難しい場合があります。
- STEM分野のカリキュラムの不足:シュタイナー学校では科学的な内容のカリキュラムが少ないことがあり、科学や技術分野で才能を発揮したい場合は追加の指導が必要になる場合があります。
- 費用負担:シュタイナー学校の授業料は一般の学校に比べて高いことが多く、経済的な負担が大きくなることがあります。
- アクセス:シュタイナー学校は、世界で拡がりを見せているとはいえ、日本ではまだ広く普及していないため、住んでいる地域によってはアクセスが困難な場合があります。
とはいっても、先にご紹介した効果を踏まえると、シュタイナー教育を受けることの価値は大いにありそうですよね。
シュタイナー教育の広がり
シュタイナー教育は、子どもたちの個々の発達に焦点を当て、多面的な能力を開発し、成熟した一人の人間として社会に貢献できるスキルを育める教育手法として世界で広がっています。
最初のドイツのワルドルフ学校から始まり、今では特にヨーロッパ、北米、オーストラリアでは多くのワルドルフ学校が設立され、現在では全世界で約1,000校以上の学校がこの教育方法を採用しています。
シュタイナー教育は、個々の学校が地域社会のニーズに応じて独自のカリキュラムを開発することが許されていますが、すべての学校がシュタイナーの基本的な教育原理である子ども一人一人の個性や才能を尊重し、それを育成することに重点を置いて運営されています。
日本でシュタイナー教育を受ける
日本にもシュタイナー教育を実践している教育機関があります。その一部をご紹介します。
神奈川県相模原市にあります。6歳(小学1年生)から18歳(高校3年生)までの12年間にわたる小中高一貫教育で、学年ごとの子どもの発達段階に合わせた独自のカリキュラムを実践しているそうです。
全国に7校展開しています。学校によっては0歳から高等部までカリキュラムがあり幅広いお子さんが対象になっています。
おわりに
シュタイナー教育の魅力を掘り下げてきましたが、その根底にあるのは子どもたち一人一人の個性と才能を大切にし、それを最大限に引き出すという哲学です。
芸術的な感受性や社会性、自然との調和など、生徒たちが経験する全面的な成長は、彼らが将来、どのような環境に身を置くかにかかわらず、大きな力となるでしょう。
私たち大人としても、子どもたちが自己実現の旅において自信と共感を持てるよう、支え続けていく必要があります。
シュタイナー教育は単なる学問の提供ではなく、生きる力を育む絶好の機会であることを、この記事を通じて感じ取っていただけたらと思います。
参考文献

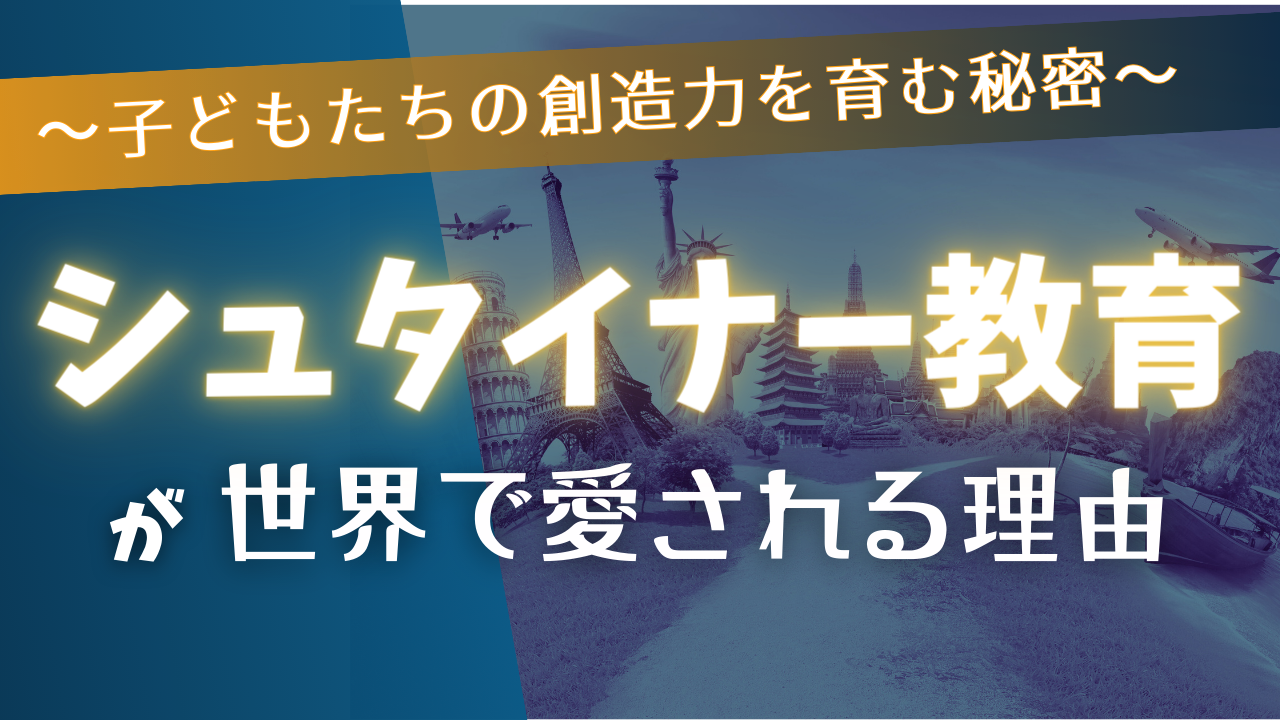
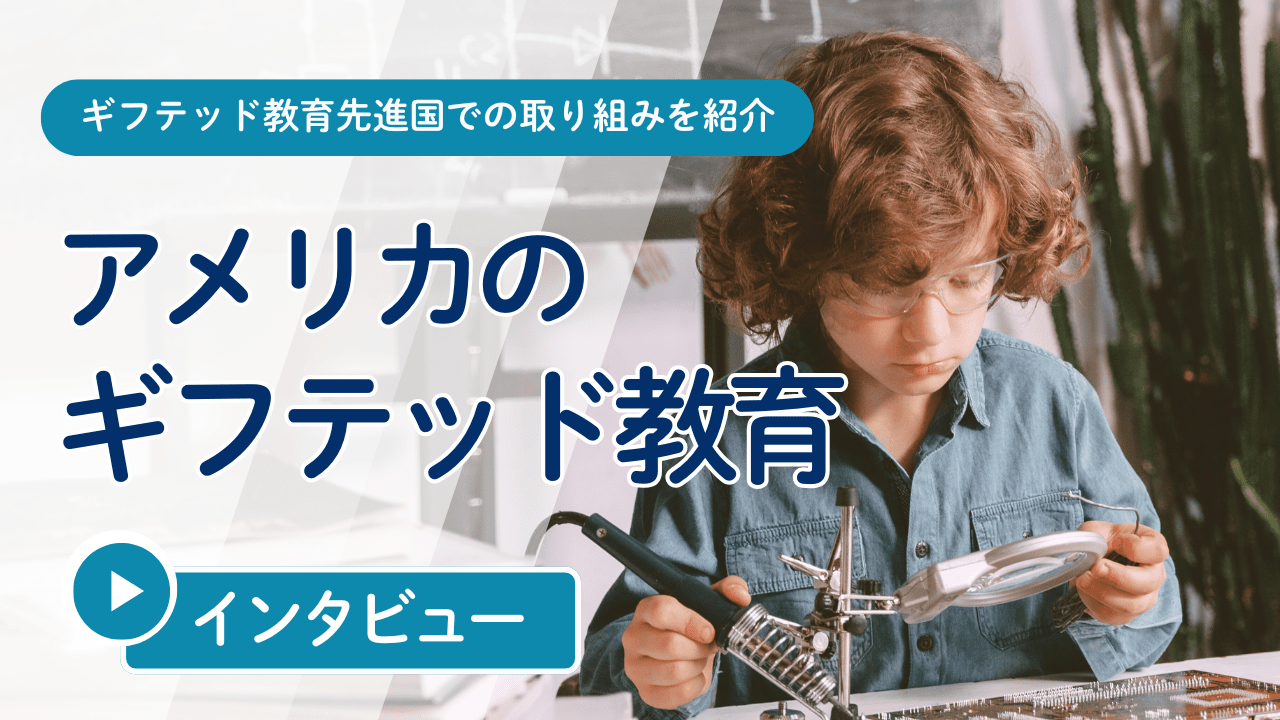


が高い子どもは育てにくい?育て方のコツ5選を心理士が解説-1.png)

」入門.png)

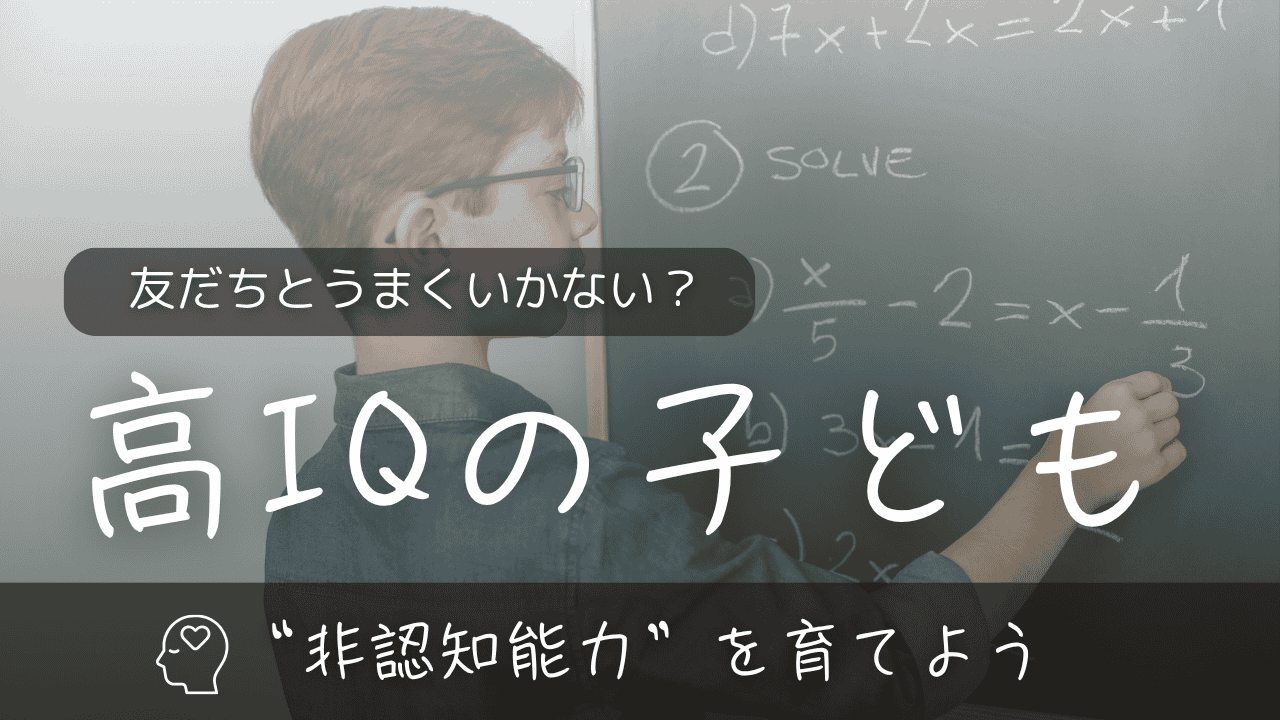
を専門家が解説.png)
