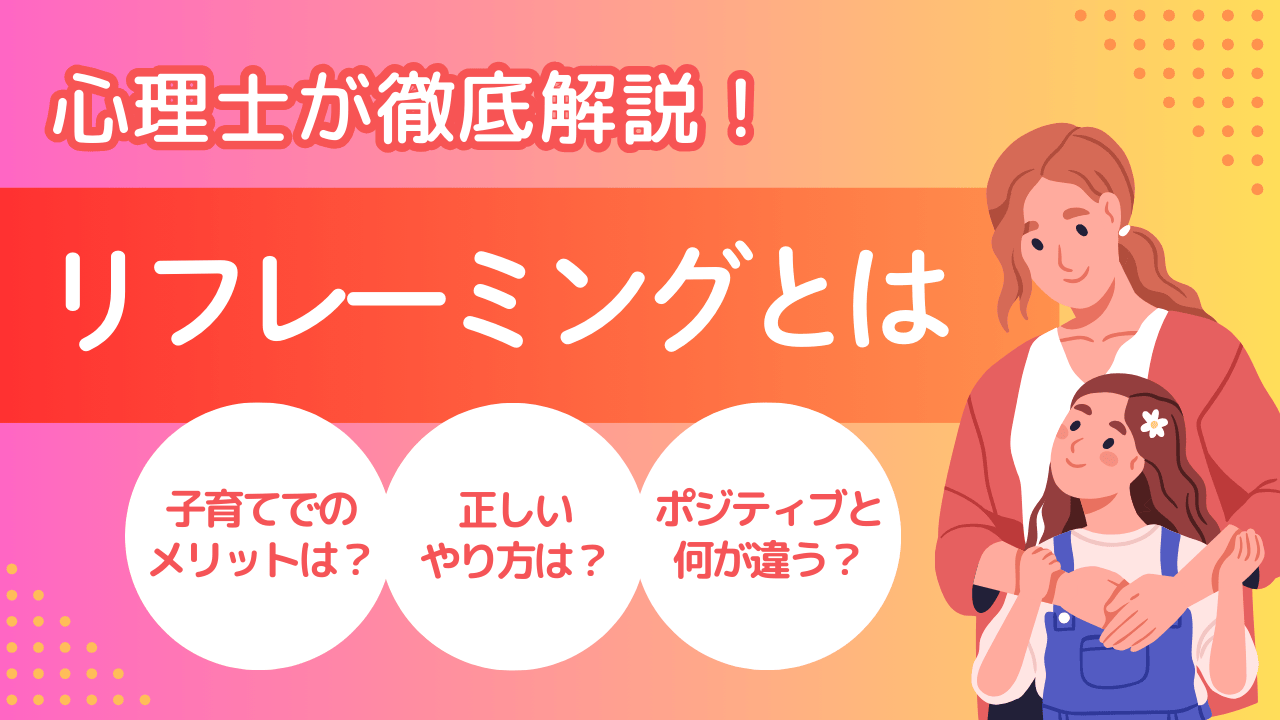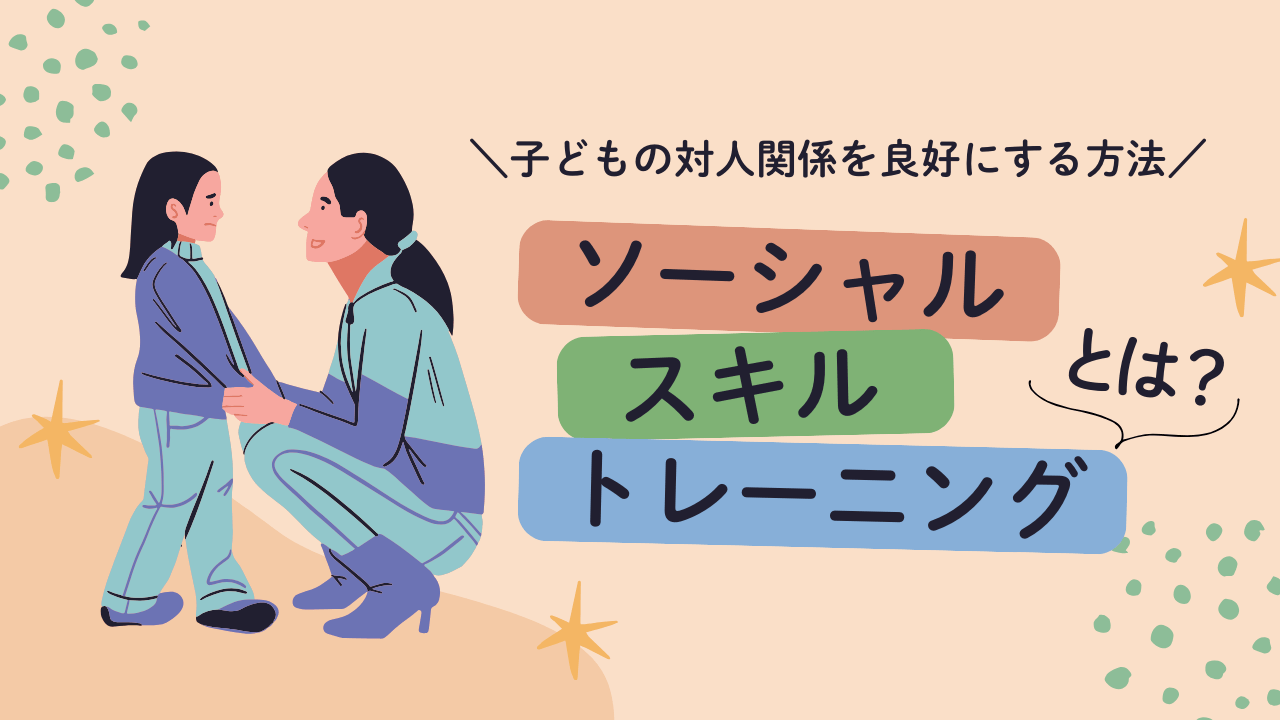「私って”モンスターペアレント”なの?」
「”モンスターペアレント”と思われたら嫌だ」
「モンスターペアレント」という言葉が広がる中で、「自分もモンスターペアレントかもしれない」と不安に思われ、園や学校と話をすることに躊躇する保護者の方が増えています。
モンスターペアレントとはどのような存在なのか、モンスターペアレントと呼ばれないために配慮するべきこと等についてご紹介していきます。

執筆:杉野 亮介
公認心理師・臨床心理士
教育支援センター、スクールカウンセラーとして不登校支援などに携わり、児童福祉施設で心理士として20年間以上従事。発達障害児の心理的支援などを行う。
モンスターペアレントとは
この記事でいう「モンスターペアレント」とは、「学校等に対して、理不尽な要求や苦情を、繰り返し行う保護者」のことです。
「モンスターペアレント」という言葉が広がる中で、インターネット等で検索しても、学校などの現場がいかに対応に苦慮しているのかという情報はたくさん出てきますし、実際に、園や学校の先生から特定の保護者の対応に苦慮しているという話もお聞きします。
保護者の方は、「私って、モンスターペアレント?」「園や学校にお願いしたいことがあるけれど、モンペと思われたらどうしよう」という悩みや不安もあると思います。
合理的配慮という言葉があるように、子どもの特性に合った配慮を求めることで、子ども本人も周囲も、より快適に生活を送ることができるようにしていくことは大切なことです。
そのため、保護者の方が園や学校に質問したり、時にはお願いをすることは悪いことではありません。
特定の言葉が広がる中で、その言葉の中身をしっかり周知されないと不安が高まることは仕方のないことなのかもしれません。
以下では、モンスターペアレントに関する具体的なお悩みに答えていきたいと思います。
あなたはモンスターペアレント?基準とは
モンスターペアレントの基準1:「自分本位」
ー子どものためと思って意見をしているのに、学校が言うことを聞いてくれません。親が子どものためを思って行動することのどこが悪いのでしょうか?
モンスターペアレントの特質の中で、最も分かりやすいのが、子ども本位ではなく、保護者本位であるということです。
「子どものことなんて、どうでもいい。私が腹が立つから言ってるだけ」とストレートにおっしゃる方は、ほとんどいません。どの方も「子どものため」ということはおっしゃいます。
しかし、中には「子どものため」なのか「自分のため」なのかが分からなくなってくる場合もあり、自分では「子どものため」と思っているけれど、実は保護者自身の不安や不満を解消するために学校や園に意見を言っている場合もあります。
その場合に「モンスターペアレント」となっていると言えるでしょう。
園や学校に対しての不満や要望を熱心に話される方に対して、「それはお子さんの意向ですか?お子さんは、どうしたいと言っておられますか?」ということを必ず質問します。
こう問われれ「でも、私は子どものためを思って」という場合も多いのですが、園や学校の現状、先生の対応等に対して、不安や不満を思っているのは、子ども自身なのか、親なのか、というところを明確にすることが大切です。
親子同席で話をしていて、子どもが何かを話そうとしても「あなたは黙ってて」「私はあなたのためを思って言ってるのに」と親が言い、子どもが気まずそうにしていることもあります。
子どもに聞くと「私はそんなに嫌じゃないんだけど」とか「本当はもう問題は解決してるけど、親が許してくれなくて困っている」ということもあります。
親が子どものことを心配するのはとても良いことですが、親子の間できちんと話し合うことがとても大切です。
現状に対して、親としてはこう思っている、子どもとしてはこう思っているというところから、この現状をどうしていきたいのかということを親子で話し合った上で、園や学校と協議していくことが望ましいでしょう。
あくまでも、子ども本位であるべきということを忘れていけません。
モンスターペアレントの基準2:「他者を巻き込む」
ーある先生の指導が度を越しているから、一緒に学校に話をしに行こうと言われています。一緒に行ってあげて良いですか?
自分だけ、あるいは、自分の子どもだけが目立ってしまうことを避けたいので、他者を巻き込むというのは、「モンスターペアレント」と呼ばれる方の特徴の一つです。
基本的には、園や学校と保護者とがお話をする際には、本来であれば各家庭ごとに分かれて行う方が良いです。
なぜなら、各家庭ごとに問題意識や求めるものというものに多少の差がありますし、初めは一致団結して学校と協議していたが、いつの間にか保護者同士の関係性の方が難しくなってしまったということも起こりえるからです。
他者を巻き込もうとする方は、内輪で話し合う際には感情的で攻撃的なのに、いざ学校と話し合う場面になると、他の人の後ろに隠れて何も言わなかったり、”他の人がこう言っていた”と責任転嫁する場合もあります。
こういう方に周囲が振り回されてしまって、協議が進まずに他の保護者が疲弊してしまいがちです。
子どもが同じ状況に置かれても、その受け取り方や希望する改善策はそれぞれです。他の保護者の方と一緒に学校と協議するのは避ける方が望ましいでしょう。
モンスターペアレントの基準3:「要求が理不尽」
ー当たり前の要求をしているだけなのに、学校側が全く要望を聞いてくれない
学校等に対して適切な要求をすることは、保護者として当然の行為と言えます。
ただ、ここで難しいのが、何をもって「理不尽」とするかですよね。
恐らく多くの方が学校や園に何かしらの対応を求める際には、それを”理不尽な要求”とは思っていないと思います。
「自分としてはこう感じている」ということを相手に伝えるときに大切なのは、相手からの話も聞き、相手の立場を理解しようとする態度があるかないかです。
自分の要求を伝えるだけではなく、学校側の意見も受け入れることがあれば、それは正当な(理不尽ではない)協議です。
「学校なんだから、保護者の要求を聞いて当然」という考えは、いつまで経っても話し合いは終わらず、相手からすれば「理不尽な」要求を「繰り返し、長期間」行ってくる典型的な「モンスターペアレント」と認識されてしまう可能性が高いです。
もちろん、保護者としては正当な要求をしているのに、学校側が適切な対応をしないこともあるでしょう。
この状況ではいつまでも問題は解決されず、結局は子どもが一番の被害者となってしまいます。
そうなってしまった場合には、教育委員会等の他機関や時には弁護士など、第三者に入ってもらうことが必要です。
モンスターペアレントにならないために「子どもの気持ちを大切にする」
ー当たり前の要求をしているだけなのに、学校側が全く要望を聞いてくれない
実際に、子どもの訴えだけでは何が事実か分からない、どうやって事実を明らかにしたら良いのか、盗聴器でも持たせるしかないのだろうか、というような相談を受けることもあります。
園や学校で起こっていることについて、何が客観的な事実なのかを明確にするということは非常に難しいです。
大切なことは、子どもが「こう思っている」「こう感じている」ということも一つの事実であるというところです。
今回の相談であれば、子どもの側から、親から学校に言って欲しいというぐらいですから、かなり辛い思いをしていることが予想されます。
客観的な事実に関しては分かりませんが、子どもがこう感じていると言っている、それを聞いて保護者としてはこう感じる、ということを学校側と共有しましょう。
子どもは苦しい思いをしているということは事実であるということを軽視しないことが大切です。
なお、先ほどご紹介したように、この場合も保護者本位とならないよう、学校にはどういう形で相談していくのか、保護者と子どもとで十分に話し合った上で行動を起こしていくことが必要です。
まとめ
「私って、モンスターペアレントなの?」という不安を抱いたことがある保護者の方は、かなりの割合でいらっしゃいます。
園や学校に言いたいことがあるけれど、言って良いのかどうか分からず、結局は自分一人でイライラしてしまったり、子どもに当たってしまうということもありますよね。
子どもが安全安心な生活を送るために、保護者として園や学校に相談するのは当然のことですし、必要なことです。
もしも、「私って、モンスターペアレントなの?」という不安が浮かんできた時には、上記の内容を読んでいただき、不安を軽減していただければと思います。
参考
佐藤晴雄(2011)学校における保護者対応について.文科省平成22年度学校マネジメント支援推進協議会講演.文部科学省
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/02/21/1301966_01.pdf (参照2025-03-25)