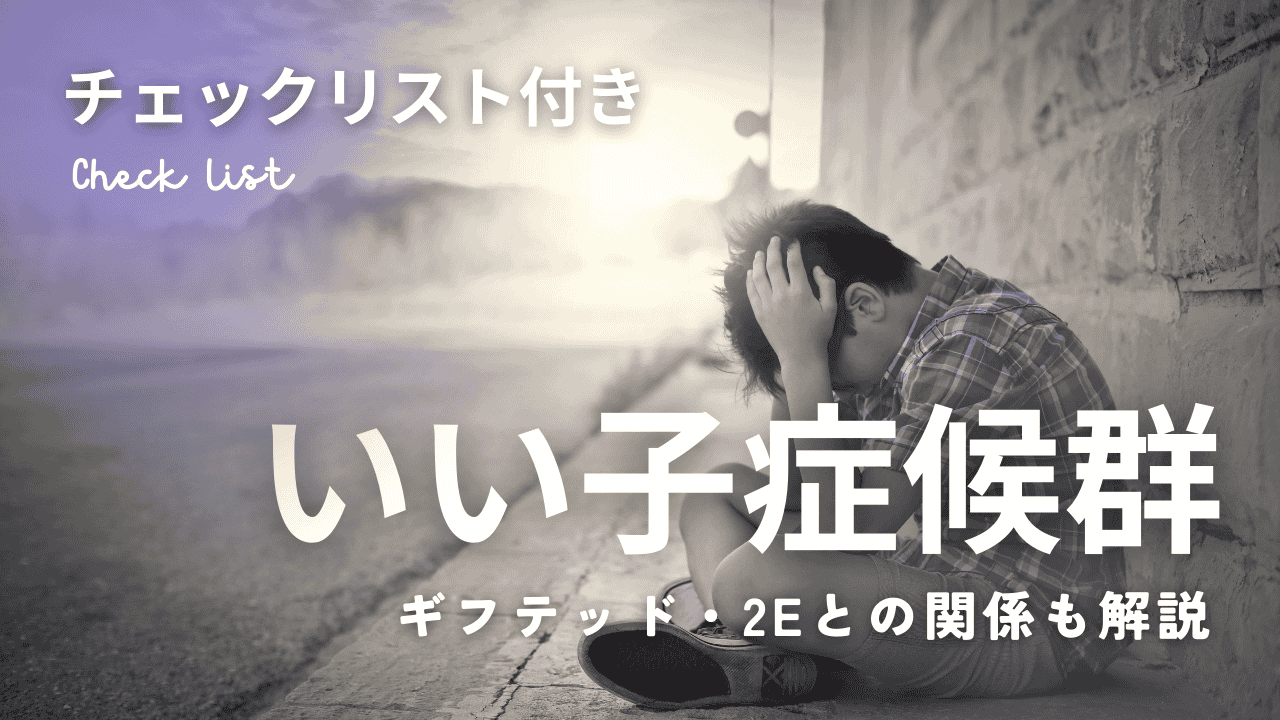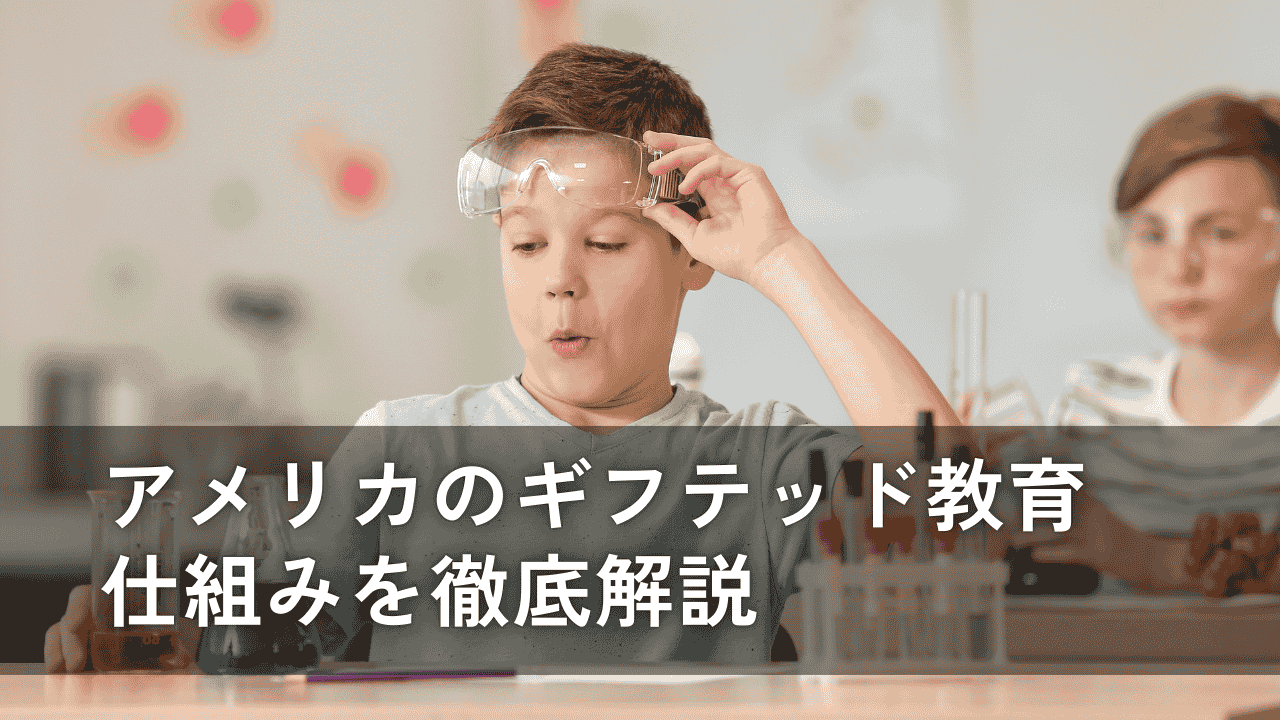いま、教育の世界で注目を集めている「非認知能力」。
それは、点数や偏差値には現れない、協調性・思いやり・主体性・レジリエンスといった、これからの社会を生き抜くための大切な力です。
でも、こうした力はどこで、どうやって育つのでしょうか?
今回お話を伺ったのは、アメリカとドイツで10年以上にわたって子育てをしてきた、駐在ママのKさん。
異なる文化や教育制度の中で、2人の息子さんが育まれてきた「選ぶ力」「伝える力」「挑戦する力」。それは、すべて“非認知能力”のかたまりでした。
「うちの子に、そんな環境はない」と思うかもしれません。
けれど、Kさんの体験には、日本で子育てをしている私たちにもヒントになることが、たくさん詰まっています。
親が、答えを用意しすぎないこと。子ども自身が「やってみたい」と感じた瞬間を、そっと信じて見守ること。
海外で育てるという選択の中で、Kさんが見つけた“育つ環境”の本質とは?
この記事では、非認知能力の育て方を、Kさんへのインタビューを通して探っていきたいと思います。
海外で育てるという選択—言葉ではなく”感覚”が子どもを動かす
Kさんの長男が高校2年の時、家族はシカゴからドイツに移住することになります。
一緒にドイツに来るか、日本に戻るか、それともシカゴに残るか。
最終的に長男は『英語で授業が受けられるならドイツに行く』と自分で決めました。
日本の大学進学を最終的に選んだ長男ですが、当初はアメリカの大学への進学も視野に入れてようです。
しかし、本人の中で「どこで何を学ぶか」の具体像が描けなかった。そのため、いずれ家族も戻る日本での進学を選択しました。
一方、次男は英語が第一言語になっており、「日本語では学べない」と自覚しながらも「日本に住んでみたい」という想いから日本の大学を目指しました。

Kさん
「協調性」とは何か—日本と海外の教育観の違い
Kさんが感じた、最も大きな教育文化の違いは「協調性の育て方」でした。
ドイツやアメリカでは、子どもが小さいうちから自分の意見を人前で話す機会が多く与えられます。
たとえば、アメリカの幼稚園では自分のお気に入りのおもちゃを持ってきて、クラスで紹介する“Show and Tell”が日常的に行われています。
うちの子も、おもちゃを手に自信満々に話していたのが印象的でした。
英語もつたなかったのに、楽しそうでしたね。

Kさん
一方、日本の学校では「きちんと座って、手を挙げて、一人ずつ発表」という形式が多く、そこに一定の緊張感がある。
発言の自由さはあっても、“場の空気”を読みながらでないと意見を述べにくい風潮もあります。
意見を言うこと=協調性がない、という捉え方があるのは、ちょっと違和感でした。

Kさん
協調性とは、決して“目立たないこと”ではなく、“違う意見を持つ人とどう関わるか”。
それを育てるには、早い時期から意見を出すことに慣れておく必要があります。
主体性と非認知能力—学力に表れない力を育てる
近年、教育の世界で注目されている「非認知能力」。
これはテストの点数などで直接測れない力、すなわち粘り強さ、共感性、自制心などを指します。
非認知能力の中でも、「主体性」は、海外の教育環境で特に重視されている要素のひとつです。
Kさんの息子さんたちも、幼少期から主体的に自分で選び、自分で決めることを多く経験してきました。
アフタースクールのプログラム選択、グループ活動での役割分担、学校行事でのテーマ決めなど、さまざまな場面で子どもが意思決定を求められるのです。
レゴクラブにしても、スポーツクラブにしても、誰かに言われてやるのではなく、自分が『やってみたい』と感じて動き出す。
そこで壁にぶつかっても、途中でやめても、やりきっても、それがすべて“経験”として蓄積されていくと思います。

Kさん
非認知能力は、数値で測ることができないぶん、学校だけで育つものではありません。
家庭での声かけや、子どもを信じて任せる姿勢こそが、それを伸ばす土台になるのです。
日本人学校での体験。イーブンな対応と序列の文化
ドイツ滞在当初、次男は2年間だけフランクフルトの日本人学校に通いました。
そこでは、日本語と英語の弁論大会がありましたが、それぞれの運営姿勢には差が見られたといいます。
- 日本語の弁論大会:先生は全員に“平等”に接し、完成度の差にかかわらず、一定の形で発表の機会が与えられる
- 英語の弁論大会:レベル別・成績別に発表が振り分けられ、上位3名が表彰されるシステム
次男が日本語で話すと笑いが起きたりして、本人には少し気の毒でした。
でも、できる子にもできない子にも平等な機会をもらえているということが好印象でした。

Kさん
グループワークと選択式学習の価値
アメリカの学校では、グループプロジェクトが盛んです。一人が手を抜くとグループ全体の評価が下がるため、協力と責任感が自然と育まれます。
日常的に、3〜5人のグループでパネル制作やプレゼンをしていました。
学年が上がるごとに役割分担も細かくなって、リーダーシップやサポートのスキルも自然と身につきます。

Kさん
さらに、アフタースクール活動の柔軟さも海外教育の魅力です。
アメリカでは2〜3か月単位で自由に選べるクラブが豊富にあり、スポーツ、チェス、プログラミング、折り紙など多様な選択肢が用意されています。
うちの長男はレゴにモーターをつけるクラブで、プログラミングの面白さに目覚めました。
今はAI分野を目指して工学系の道へ進んでいます。

Kさん
ドイツの進路選別制度とインターナショナルスクール
ドイツの公立教育では、小学4年生の段階で成績によって進学先が分かれる仕組み※があり、進学ルートの種類は以下です。
※ 複線型(分岐型)と呼ばれ、初等教育後に子どもたちが異なる種類の中等学校へと分かれて進学するのが特徴です。
- ギムナジウム(大学進学を目指す生徒)
- レアルシューレ(実務的知識と基礎的アカデミック教育の両立を目指す生徒)
- ハウプトシューレ(より実務・職業訓練志向の生徒)
Kさんはこの早期選別に違和感を覚え、インターナショナルスクールを選択しました。
10歳で将来を方向付けるのは早すぎると感じたんです。
英語で学びたいという希望もあり、うちは最初からインター一択でした。
ただし、ドイツのインターナショナルスクールの中にも、ブリティッシュスタイル(成績評価が厳しく、60点以下は再試)など厳格な校風がありました。
ドイツ語が話せないという壁があると、家庭での選択肢は限られました。

Kさん
「自分の居場所を選ぶ力」を育てる
Kさんの息子たちは現在、日本で大学生活を送りつつ、就職や将来の進路に悩みながらも、自分で進むべき道を模索しています。
帰国子女って、日本でも海外でも“中途半端”に見られることがあります。
でも、いろんな文化を知っているからこそ、相手と距離を取ったり、合わせたりする力があると思うんです。

Kさん
どの国の教育が良い悪いというより、「子どもに合った環境かどうか」が重要だとKさんは繰り返します。
子どもが自ら「これは好き」と言える環境。失敗しても試してみる自由。その積み重ねが、自信と方向性につながっていくのです。
教育に「選択肢」と「自由」を—保護者にできること
最後に、Kさんはこう語ります。
親にできるのは“その子に合った選択肢”を少しでも多く見せてあげること。
その中で、どれを選ぶかは本人次第です。その気持ちを尊重したいですね。

Kさん
子どもたちは自分で進路を決める力を少しずつ育てています。
たとえ選んだ道が変わっても、それはその時の最善の選択だったはず。柔軟に、しなやかに生きていく力。それがKさんが海外の教育で最も大切だと感じたことでした。
海外に行かなくても、日本の中で「自由に選ぶ」「自由に話す」環境をどう増やすか。その視点を持つことが、子どもの未来にきっとつながります。
編集部より
「非認知能力」は、親の働きかけ次第でどこにいても育てられる力です。
海外の教育現場には、その力を育むための“余白”や“自由”が確かに存在していました。
Kさんの体験を通して見えてきたのは、「子どもの声に耳を傾けること」そして「大人が答えを急がないこと」の大切さでした。
わたしたち大人がまず、“見えない力”の価値を信じること。そこから、子どもたちの未来はもっと自由に、豊かに広がっていくのかもしれません。