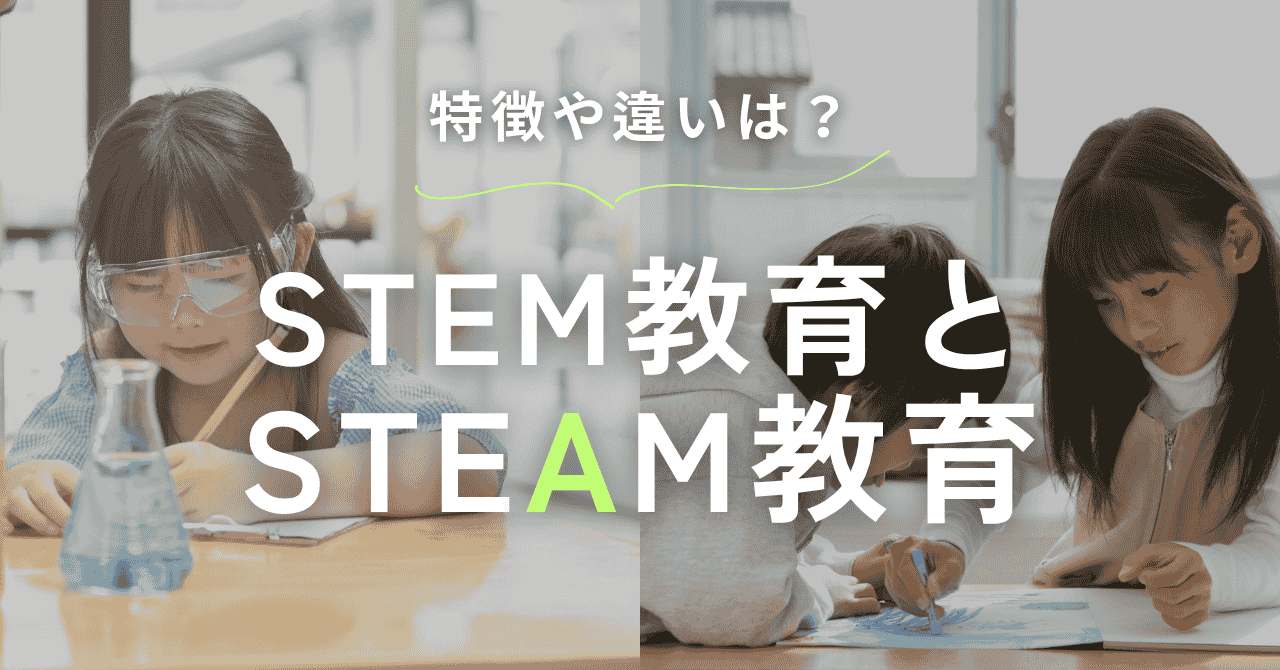「子どもの得意や個性をどう伸ばしてあげたらいいんだろう?」
そんな悩みを抱える保護者の方に向けて、今回はアメリカで子育てを経験されたOさんにお話を伺いました。
言語も文化も違う環境の中で、どのように子どもの力を伸ばしていったのか。
教育の選び方から進路決定のプロセス、そして一人の母親としての想いまで、子どもの「才能」や「個性」を大切にするヒントが詰まったインタビューです。
最初は「ESL」で無理なく現地に慣れる
ー アメリカならではだなと感じた教育方法はありましたか?
娘が小学校低学年の頃までは、「まずは飛び込ばせてみよう」という気持ちでしたが、高学年になると娘も繊細になり、丁寧なサポートが必要になります。
現地校のESL(英語学習支援クラス)に入ったことで、安心して環境に慣れて、徐々に自分を出せるようになりました。
娘自身が安心できる環境があることで、もともとの好奇心や表現力が自然に表に出てくると思います。
早い段階で「自分らしく過ごせる場」を用意することが、個性を伸ばす第一歩だと感じました。

Oさん
英語レベルの判断も“納得感”が大事
ー ESLに入るのと、現地の子たちの中に入るスタイル、どちらを選びましたか?
ESLを選びました。レベル分けテストがありましたが、「現地の専門家が見て判断してくれる」という安心感があり、無理なく学び始められたと思います。
無理に「みんなと同じ」にさせるのではなく、娘のペースを尊重することで、得意な分野への興味も伸びやすくなると感じました。
ESLについて、テストでは、話す、聞く、書く、読むの4つの能力のバランスが取れていないとパスできないようになっています。
「自分の子どもはある程度話せるし、先生の指示も理解している感じだから大丈夫」と決めつけずに、この4つのバランスが取れるまで、焦らず苦手な所を強化できるように、具体的なサポートが必要だと思います。子どもだからそのうち慣れるでしょう、というのは可哀想です。
英語自体の習得プラス、英語で様々な教科の内容を、勉強していかなければならないのですから…本当に、子ども達は大変な努力が必要ですね。

Oさん
高校生活は「勉強+課外活動」で充実!
ー アメリカの高校生は、学業の成績だけでは大学にいけないと聞きますが、具体的にどんなことが重視されていますか?
特に高校では、勉強だけでなく、ボランティアや文化活動などが重視されています。
娘は、「アイフェア」という文化紹介のイベントで日本文化を紹介するなど、自分らしさやアイデンティティを発揮する機会が盛りだくさんでした。
勉強が苦手でも、人に伝えたり、自分の文化を表現するといったことを活かせる場がたくさんあります。
学校の勉強だけでなくて、こういう体験があったからこそ、娘自身が「自分の得意」や「こういうことをやっていると心地良いんだな」ということに気づくきっかけになったと思います。
日本とアメリカの両方の文化を知っているからこそできる役割があって、周りの人からもそれが羨ましいと言われるので、娘自身も環境に感謝しているようです。
今では大学でも日本人会に所属し、文化交流を楽しんでいます。

Oさん
教育格差への対策は「住む場所選び」から
ー 日本でも昨今教育格差があると言われていますが、アメリカも教育格差はありますか?どんな環境を選びましたか?
アメリカも地域によって教育の質に差があるのは事実です。
学生の間に1年間休んで学費を稼ぐために時間を使い、翌年大学に戻る学生もいます。
だからこそ、娘にはできる範囲で“より良い環境”を選びました。治安が良く、教育に熱心な家庭が集まるエリアです。
アメリカの公立高校では高校受験がないため、より良い校区を選ぶために引越しをするご家庭がたくさんいます。
現地校を選ぶときには、日本語と英語のサポート体制が整っているかも重視しました。
その地域に住んでいる先輩ママたちからの評判をもとに情報を集めましたね。
周囲の環境や人間関係は、子どもが「どんな刺激を受けるか」に直結するので、安心できる環境で、子どもが自分の興味を広げたり、才能を見つけるきっかけになればいいなと思っていました。

Oさん
進路も大学選びも「柔軟さ」が魅力
ー アメリカの大学の進学事情を詳しく教えてもらえますか?
アメリカは、進路に迷っても大学在学中に、メジャー(専攻)を変えたり、ダブルメジャー(2つの専攻をとること)も可能でとても柔軟性があります。
娘は、ボランティアや課外活動を通して、学びたいことはいくつもあったので、進学しながら自分に合った選択を見つけていっています。
特に、大学選びでは、食生活や住環境も大切な要素だったので人種構成も意識し、アジア系が一定数いる環境を娘は希望しました。
自分に合った場所を探すプロセスも、アメリカならではだと思います。
娘の場合は、高校の時点で、すでにアメリカの大学進学を決意していました。
補習校(土曜日のみの日本人学校)をやめ、家族も帰国予定がない中で、自然とアメリカでの進路を模索するようになった感じです。
アメリカは、「決められた道を行く」のではなく、「自分に合う道を探す」ことが重視される環境です。
娘自身が、自分の興味や強みを見極めながら進めるので、自然と個性が活かされる進路選びになる気がします。

Oさん
専攻は「ビジネス」と「アーバンスタディ」へ。自分の関心で進路を決定
ー お子さまが今の学部を選んだ理由を教えてください。
日系スーパーでのアルバイトを通じてビジネスに興味を持ち、さらに都市のインフラや社会課題に関心を持ったことで「アーバンスタディ」にも進みました。
自分の中にある「違和感」や「気づき」が、進路を切り開く原動力になったみたいです。

Oさん
お金の教育は「実生活から」育つ意識
ー アメリカでのお金の教育について教えてください。
授業では特にお金をテーマにしたものはなかったと思いますが、生活の中で自然と経済観念が育ちます。
アメリカでは、職業や年収の情報がオープンになっていて、早くから自分の将来像を意識させられる環境があります。
娘も、自分のアルバイト代をどう使うか、車をどう買うかなど、現実的な判断力を身につけています。「儲ける」とかではなく、「どう有意義にお金を使うか」を考える意識があるなと思います。
親としても、そうした考え方を一緒に学んでいけるのは楽しいですし、心強いです。

Oさん
就職のカギは「インターン」。実力社会で力を発揮
ー アメリカでの就職事情を教えてください。
実力が重視ですし、大学のうちにインターンをするのが一般的です。
企業でのインターンは“修行”そのもので、学生は自分に合う分野を実践を通じて見つけていきます。
企業側も学生が大学で何を学んできたのか、この学生を雇う価値はあるのかをインターンを通して判断します。
インターンなしで面接に来ても、その学生の実力はわからないので、面接だけで入社はできません。
だからこそ、「今のうちに、小さな失敗をたくさん経験してほしい」と願う気持ちも強くなります。
日本のように新卒一斉採用という文化はありません。卒業時期もバラバラなので、100人単位の同期などもいませんし、数カ月に渡る新人研修のようなものもありません。
インターンで実際に体験することで、机上では見えなかった「向き不向き」が見えてきます。
子どもが自分の強みや個性を活かせる仕事を自ら発見していくプロセスが、社会に出るためにとても大切だと思います。

Oさん
「ありがとう」の言葉が、子育てのご褒美に
ー 子育てを振り返って思うことは?
娘から「バイリンガルに育ててくれてありがとう」と言われたとき、心から報われた気持ちになりました。子どもが成長する姿を見て、私自身もたくさん励まされました。
言葉や文化、経験すべてが“その子だけの資産”になります。
もちろん、一番頑張ったのは本人です。でも、その環境を用意することが親ができる最大のサポートだったのだと実感しています。
アメリカの教育や社会において、「自然にできていること」が強みになる。その“強み”は、社会に出たとき、確実に子どもを支えてくれると信じています。

Oさん
最後に:子育てに悩むすべての保護者へ
海外での子育ては、本当に毎日が手探りで、不安とチャレンジの連続でした。言葉も文化も違うし、学校のルールや教育のスタイルも日本とは全然違って、最初は戸惑うことばかりでした。
でも、「どんな環境を用意するか」、「どんな体験をさせるか」を少しずつ考えて工夫していくうちに、どこにいても子どもはちゃんと自分の力で道を切り拓いていけるんだって、心から思えるようになりました。
実際に、子どもが言葉や文化の壁を乗り越えて、悩みながらも少しずつ成長していく姿を見て、私自身が励まされたし、「親として、私もがんばらなきゃ」と何度も思わされました。
今、子育てで悩んでいる方や迷っている方がいたら、「子どもって、環境次第でどこまでも伸びるんだよ」「世界のどこにいても大丈夫!」っていうことを、少しでも感じてもらえたら嬉しいです。
編集部より
海外での子育てという、決して平坦ではない道のりの中で、お母さまが繰り返し大切にされていたのは、「子どもを信じる」ことでした。
無理をさせず、焦らせず、その子らしい歩みを大切にしていく。それは、どんな国にいても、どんな環境にあっても変わらない、親の願いではないでしょうか。
「才能は、環境と経験が引き出してくれる」
そんな温かなメッセージが、この記事を読んでくださったすべての保護者の方に届きますように。
子どもたちの未来が、ひとりひとりの「らしさ」で輝いていきますように。