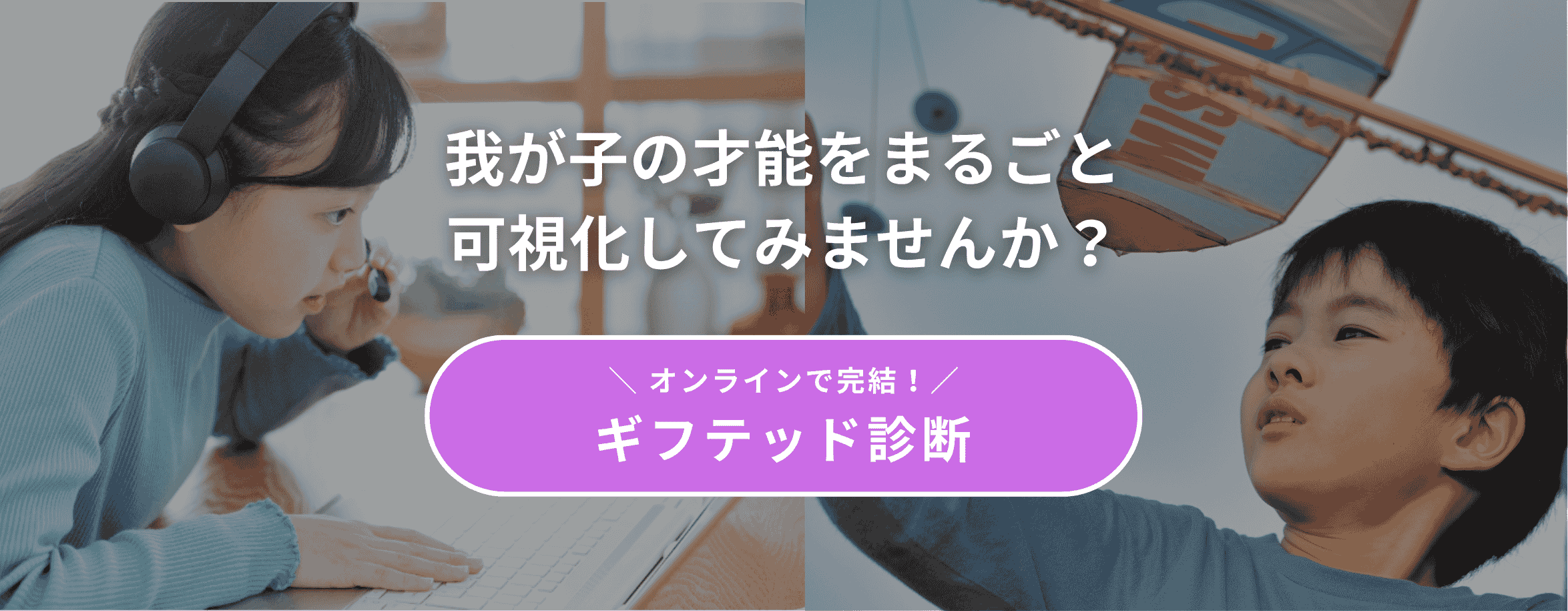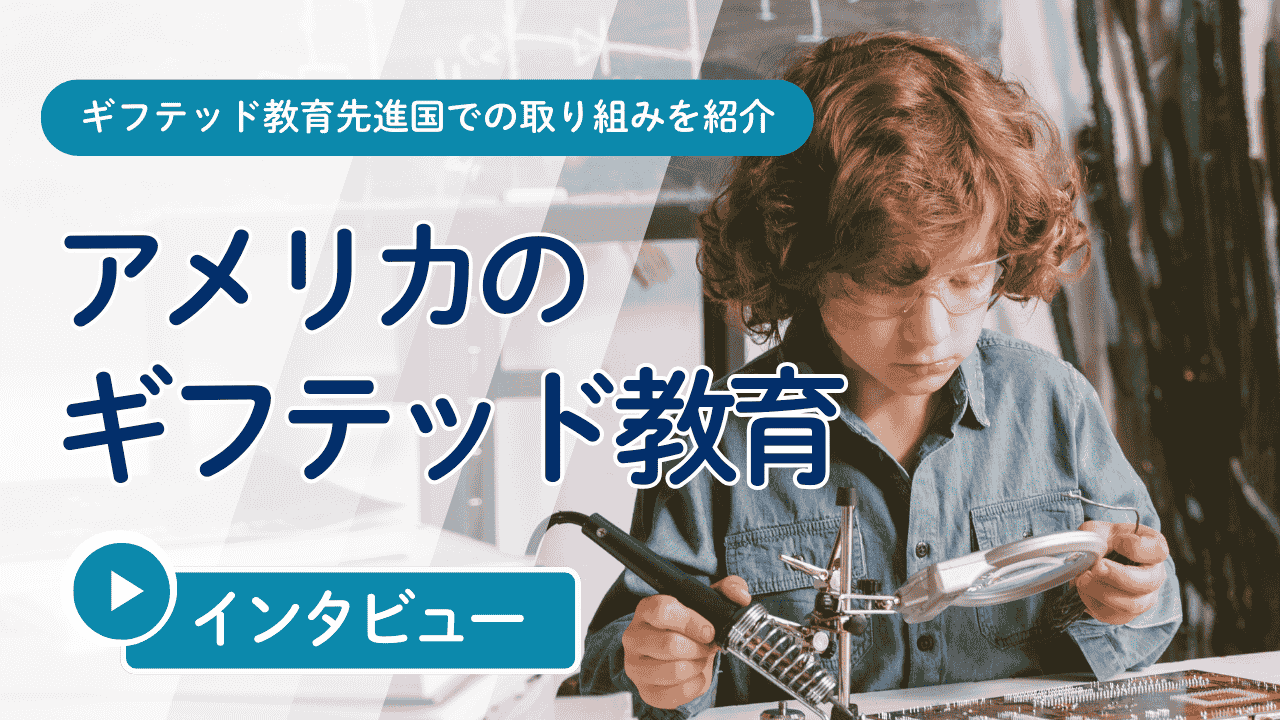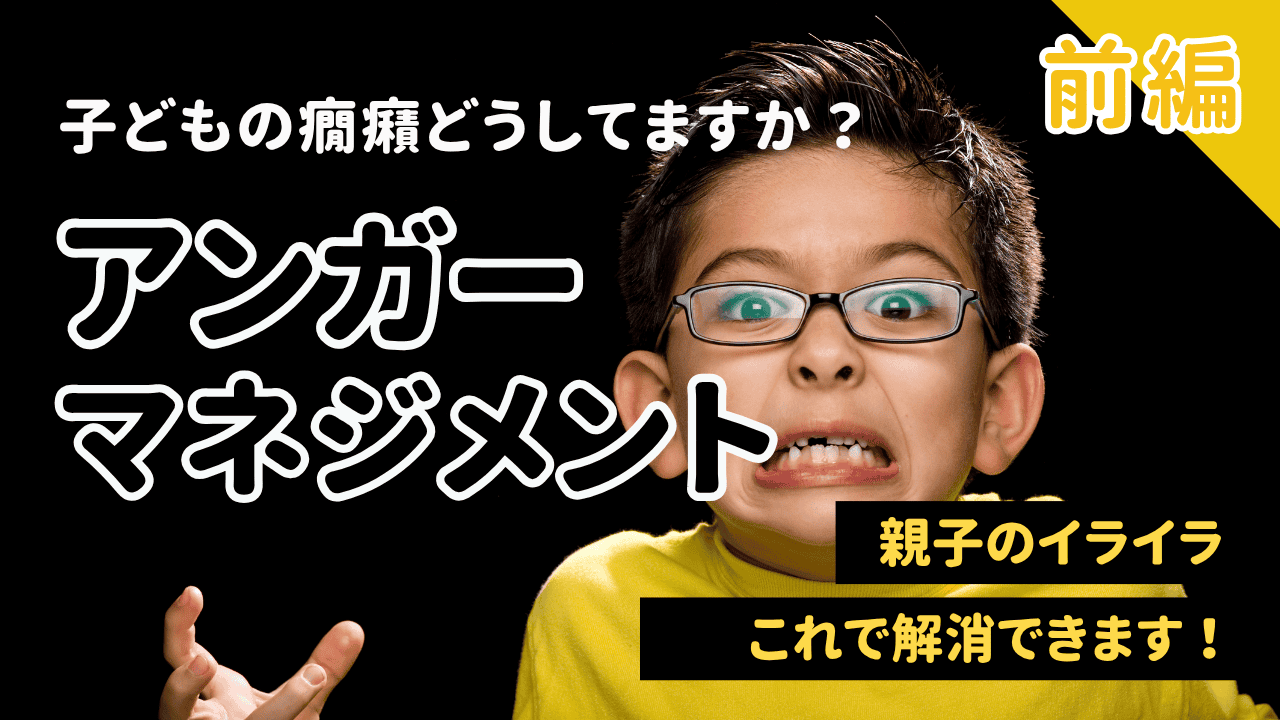子どもの知的関心や学習のスピードに、「この子には、もう少し高度な学びが必要なのではないか」と感じたことのある保護者の方もいらっしゃるでしょう。
近年注目されているのが、「ギフテッド教育」と呼ばれる、高い能力を持つ子どもたちに特化した教育アプローチです。
この記事では、小学4年生から高校卒業までアメリカ・イリノイ州で過ごした日本人女性の体験談をもとに、アメリカのギフテッド教育の特徴や意義、そして日本の教育における可能性についてご紹介します。
アメリカのギフテッド教育は「個」に寄り添うもの
シカゴというと都会で少し怖い場所もあるとイメージされる方も多いですが、私が育った場所はダウンタウンエリアから車で20分の所に位置する、緑豊かな場所でした。
取材に応じてくださった方は、小学4年時にシカゴ近郊に転居し、約9年間をアメリカの公立学校で過ごしました。
彼女が最も印象に残っているのは、「教育が個々の子どもに合わせて柔軟に構成されていたこと」だと言います。
同じ学年でも、学力や関心によって学ぶ内容が大きく異なりました。
学力の高い生徒には、より深く学べる環境が整えられており、その中でも特に優秀な生徒には“ギフテッドクラス”や“マグネットクラス”といった専門的な学びの機会が用意されていました。
こうした仕組みは、年齢に縛られず能力に応じて教育の内容やスピードが調整されるアメリカならではの制度設計です。
以下では、実際にギフテッドの子どもたちに対してどんなクラスが用意されていたのか、その選抜方法や授業の工夫についてご紹介します。
アメリカの「ギフテッドクラス」
才能を見極め、適切な環境で伸ばす
アメリカの公立学校では、一定の基準に基づき、知的能力の高い児童・生徒を「ギフテッド」として識別し、専用のプログラムを提供する仕組みがあります。
ギフテッドクラスへの参加には、学業成績や知能テストの結果、担任教師の推薦などが必要であり、単にテストの点数だけでなく、普段の学習態度や探究心の強さなども評価対象となります。
ギフテッド教育はどう選ばれる?:セレクションと推薦制度の実態
彼女が通っていた公立学校では、ギフテッドクラスへの参加はオープンな応募ではなく、教員による推薦と、教育委員会による正式な評価プロセスを経て行われていました。
選抜のステップと評価基準
ギフテッドクラスへの進学は、日々の授業態度や成績を踏まえて担任の教師の判断し、不定期で第三者期間がテストを実施してクラスの移動が判断されます。
「単なる学力の高さ」だけでなく、「日常の学習活動における思考の深さ・主体性・創造性」も重視されており、より多面的な視点で子どもを評価する仕組みであることが伺えます。
選抜後の進路:さらに上の「マグネットクラス」
また、ギフテッドクラスよりも高度な学習ニーズを持つ生徒に向けては、マグネットクラスと呼ばれる特別プログラムも設置され、医学や工学などの分野に関心を持つ生徒が参加していたそうです。
興味深いのは、この選抜にも定期的な試験はなく、担任との面談や本人の希望、能力に応じて流動的に参加が決まるという柔軟なシステムがあったという点です。
選抜のあり方自体が、「学びの継続的なプロセス」の一部として機能する仕組みです。
アメリカの教育の柔軟性と個別性
飛び級、科目選択、Study Hall
アメリカの公立学校では、学年や年齢にとらわれない学び方ができます。
実際、ギフテッド教育の一環として、飛び級(アカデミック・アクセラレーション)を実施する学校も多く見られます。
また、高校では科目選択の自由度が非常に高く、心理学や社会問題、LGBTQや薬物に関するリスク教育など、大学レベルの内容にも触れられるカリキュラムが提供されています。
一方、学習量が増える中高生には、Study Hall(≒自習時間)という仕組みが用意されており、授業の合間に課題をこなしたり、自主的な学びを進めたりできる時間がカリキュラムに組み込まれています。
こうした工夫が、生徒自身が学習を自己管理する習慣を自然と身につけていくことにつながるのです。
宿題を“量”で管理しない:自律と責任を育むアメリカ式の工夫
彼女が語るアメリカの教育における印象的な違いの一つが、宿題の量と取り扱い方です。
アメリカの小学校では、宿題の量は比較的少なく、年齢に応じた負担に調整されています。
たとえば、算数であれば教科書1ページ(6問程度)が日々の宿題として出される程度で、夏休みのような長期休暇中にも宿題は基本的に課されません。代わりに、読書リストの紹介など「学びの継続を促す形」で推奨が行われるのが一般的です。
しかし、宿題を忘れてしまった際には、単なる「注意」では終わりません。
彼女が通っていた学校では、「イエローペーパー(Yellow Paper)」というユニークかつ教育的なペナルティ制度がありました。
イエローペーパーとは?
- 宿題を提出できなかった生徒に対し、黄色い用紙に「なぜ提出できなかったか」「次回以降どう改善するか」を自分の言葉で記入させる
- 最後に保護者とこの内容について話し合い、保護者の署名をもらって翌日提出する
- 目的は「叱ること」ではなく、自分の行動に責任を持ち、原因と対策を自ら考えること
単なるペナルティではなく、子ども自身の自己管理能力と責任感を育てる点が重要です。
教員や保護者からの一方的な指導ではなく、子ども自身の言語化と振り返りを通じて、自律的な学びの習慣づけを重視しています。
アメリカのギフテッド教育 | 日本との違い
年齢に応じた「挑戦」の段階設計
また、中学・高校に進むにつれて宿題の量や内容は増えていきますが、それに合わせて生徒たちには学習習慣や自己調整力が備わっていきます。
たとえば、先述のStudy Hall(スタディホール)のような自習時間が時間割に組み込まれており、生徒たちはその時間に課題を進めたり、自分のペースで読書をしたり、試験対策を行うことが可能です。
このように、アメリカの教育現場では、「やみくもな量」ではなく、「意味のある課題と自己管理の育成」が意識されています。
ギフテッド教育を含め、アメリカの教育文化が子どもの成長段階と心理的発達を丁寧に考慮している好例だと言えるでしょう。
評価方法と学習姿勢:“対話型授業”が生徒の積極性を育てる
アメリカでは成績の評価基準として、「授業への参加度(Participation Point)」が重視されます。
教員との対話、発言、議論への貢献などが成績に反映されるため、生徒は積極的に授業に関わろうとする意識を高めていきます。
こうした学びのスタイルは、知識の定着だけでなく、思考力・表現力・自己主張のバランスが取れた人間形成にもつながっているようです。
保護者のマインドと学校文化:“才能を伸ばすこと”が自然に受け入れられる環境
アメリカの教育文化では、優れた子どもがより高度な教育機会を得ることは、社会全体の利益につながるという考え方が一般的です。
そのため、アメリカのギフテッド教育は“特別扱い”ではなく、当然の配慮と捉えられており、子どもや保護者同士の嫉妬や差別のような否定的感情が生まれにくいという印象をインタビューから受けました。
私の学校では、ギフテッドの子が特別視されたり、他の生徒から反感を買ったりすることはほとんどありませんでした。
むしろ、周囲がその能力を自然に認めていました。
一方で、日本人家庭の一部では、推薦の有無をめぐって戸惑いや不満が生まれることもあり、文化的な受け止め方の違いが教育選択に影響を与えることもあるようです。
教師の役割と日本への示唆:「教えるプロ」の専門性を高めるには
最後に、日本の教育制度に対する提案を聞いてみました。
日本の先生方は非常に多忙で、授業以外の業務に時間を取られてしまっています。
本来、教師の役割は“教えること”に集中するべきです。
そのためにも、部活動や事務作業などを外部に委ね、教員自身が常に学び続けられる環境を整えることが重要だと思います。
確かに、日本の学校はアメリカと比較すると教師の負担は大きいと言えます。
部活動の顧問、行事の準備、校務分掌、さらには保護者対応に至るまで、その業務範囲は多岐にわたるからです。
その結果、教科指導や子ども一人ひとりの学びに対して向き合う時間が削られ、本来の「教育のプロフェッショナル」としての役割が圧迫されているのが現実でしょう。
アメリカでは、教師の本務はあくまで「教えること」です。
もちろん雑務や管理業務が全くないわけではありませんが、学校カウンセラー、事務職員、コーチ、ボランティアスタッフなどが機能的に分業しており、教師は授業の設計・実施・評価という専門性を活かした仕事に集中できる環境が整えられています。
ギフテッド教育のような高度な教育支援を必要とする子どもたちに対応するには、教員自身が専門性を磨き、常に教育の質をアップデートしていく姿勢も重要になってきそうです。
おわりに:ギフテッド教育は“特別”ではなく“適切”な支援
アメリカの教育におけるギフテッドプログラムの根底にあるものは、「能力のある子どもたちに、適切なレベルの教育機会を提供する」という極めてシンプルな目的です。
日本でも、多様な子どもたちがそれぞれの才能を活かせるような教育環境を整えることが急務です。
そのためには、教師の研修体制の整備、評価基準の多様化、保護者の理解と協力が鍵となります。
一人ひとりの「違い」を認め合い、その個性や能力を活かす教育。それは決してギフテッドに限らず、すべての子どもに必要な視点ではないでしょうか。
我が子はギフテッド?と思ったら
わが子がギフテッド(Gifted)かもしれない、と思ったら、まずは「ギフテッド診断」テストを受けてみることもおすすめです。
「ギフテッド診断」テストでは、子どものIQ(知能指数)や行動特性、才能のバランスを多くの側面から確認することができます。
\申込みから結果までオンライン完結/
ギフテッド診断とは
子どもの才能は、多くの側面に光を当てながら総合的に判断することが重要です。
ギフテッド診断は、4領域・全27種類の項目を測定し、子どもの才能を多面的に把握します。
より多くの方にご利用いただける価格※と内容を実現しました。
※”4領域”のうちの一つ、例えばIQテストだけでも診断項目がきちんと揃ったものを受けるためには15,000円〜50,000円程度の費用がかかります。(弊社独自調査)



診断テストの結果が活用できるように、結果についてわからないことがあれば、LINEで質問※1することができます。
さらに、お子さまの状況と必要に応じて、子どもの発達と子どもの心の専門家である医師・心理士に相談※2することもできます。どんな些細な質問でも大丈夫です。
※1 月間の質問回数の条件があります。
※2 別途料金がかかります。
\申込みから結果までオンライン完結/