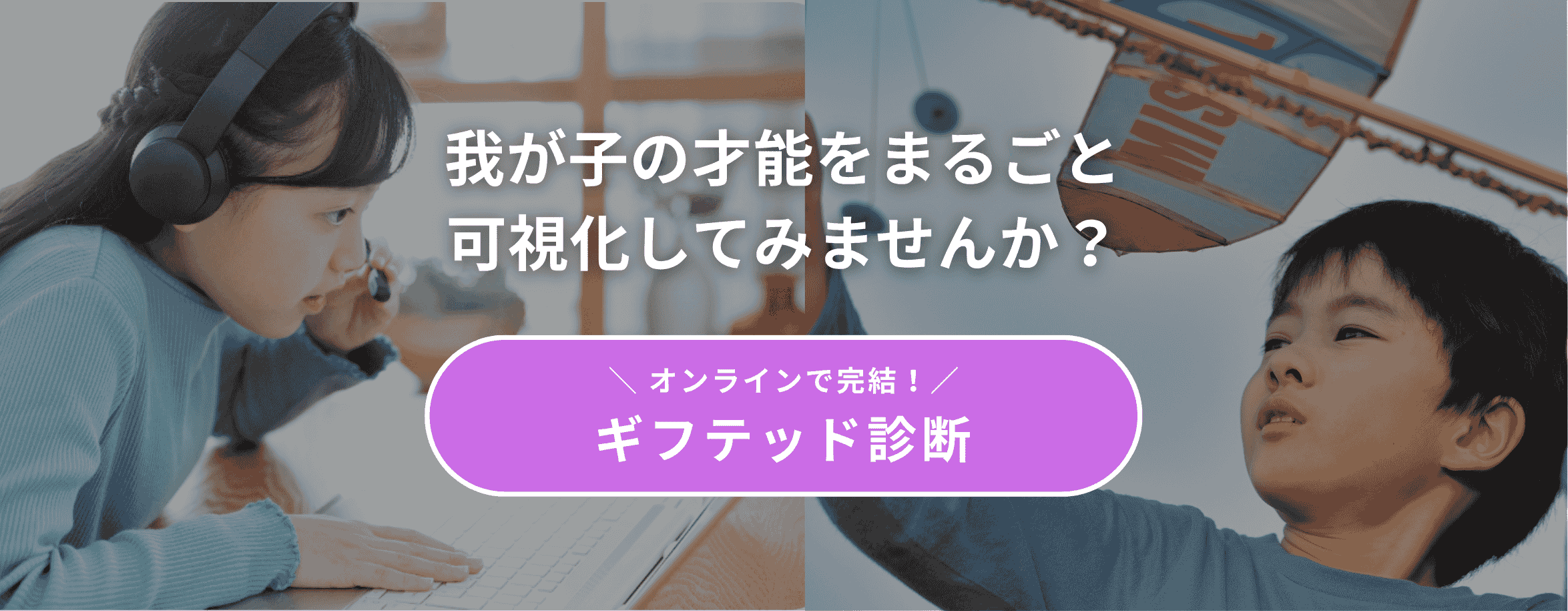「学校の勉強で退屈している」「授業のスピードが遅くて合わせるのがしんどい」
知的好奇心が高いギフテッドの子どもを持つ親御さんは、こんなお悩みを持っていることと思います。
ギフテッドの子どもたちは、一般的な教育の枠組みでは満足できず、学校生活でストレスを抱えていることケースがあります。
“ギフテッド”と聞けば、世間では「天才」や「高IQ」というイメージをもたれがちで、日本では長い間、個別に教育支援の対象とはなっていませんでした。
この記事では、ギフテッドの子どもたちの教育的ニーズを含め、日本での取り組みの紹介やギフテッド教育の必要性と具体的なプログラムをご紹介します。
ギフテッドの子どもが安心して力を発揮できるよう、ぜひ最後まで読んでみてください。
ギフテッド教育とは?その目的と重要性
ギフテッドとは?
ギフテッド(Gifted)とは、学年の枠を超えた高度な知的能力や特異な才能を持つ子どもを指します。(「ギフテッド・チルドレンについて」で詳しく解説しています。)
例えば以下の特徴を持っていることが多いです。
全ての子どもたちが、それぞれ、いろんな領域で素敵な才能を持っていますよね。
しかし同時に、同年代の子どもたちに比べて、特定の分野に極めて突出した能力を示す子どもは存在し、理解されない苦悩を抱えている子どもが多いのです。
高い能力を持つことは、決して“ラクなこと”ではなく、むしろ独自の困難や苦手を伴うこともあります。
「ギフテッド(gifted)」とは、「神から与えられた」「贈られた」などの意味を持ちますが、肝心なのは、ギフテッドの子どもたちの多くの側面を理解し、どのような教育的ニーズを求めているかを知ることです。
▶︎詳しくは「Gifted」(ギフテッド)ということばについて〜ギフテッドへの誤解を超えて〜も合わせてご覧ください。
ギフテッド教育の必要性と困りごと
では、彼らはどんな問題に直面していて、どんな支援が必要なのでしょうか?
ギフテッドの子どもたちは、自分の能力や感情をうまくコントロールできず悩んでいたり、潜在的な能力や特性を自覚できず周りに頑張って同調しているケースもあります。
小学校に入学してから困難が見つかって検査を受けたり、高校生まで本人と親が気づかないケースなど、ギフテッドと認識されるタイミングは様々なパターンがあります。
「頭がいいなら、困ることなんてないでしょう?」と思われがちですが、実はギフテッドの子どもほど、学校生活の多くの場面で苦労しているのです。
学習面での不適応「授業がつまらない」
ギフテッドの子どもたちは、先生が教えている間に答えがわかってしまうことが多く、それゆえ授業が退屈になり、つい気が散ってしまい勉強に集中できず、「落ち着きがない」と注意されることもあります。
否定や注意をされすぎることで、自尊心も下がってしまいますよね。
さらに、こうしたパターンによって、ギフテッドの子がADHDなどの発達障害の状態と誤解されることもあります。
学びたい意欲があるのに、授業が合わずに意欲を失ってしまう。
実際にこうした状況が不登校や行き渋りにもつながっていくのです。
社会的孤立「話が合わない」
ギフテッドの子どもは、周りの子どもたちと興味の対象が違うことが多く、友だちとのコミュニケーションの中で苦労する傾向もあります。
例えば、同年代の子がアニメやゲームの話で盛り上がっているときに、一人だけ量子力学や歴史の話をしてしまう。
そうすると、「変わってる」「話が難しすぎる」と思われ、周りから浮いてしまうことも。
その結果、「私は周りの人とは違う」と感じ、社会的な孤立感や疎外感を抱えてしまいます。
感受性の強さ「些細なことで傷つく」
ギフテッドの子どもは、知性だけでなく感受性が強いことも特徴です。
「過度激動(OE)性」とも呼ばれる特性を持つ子どもも多いとされています。
関連記事:ギフテッドの子どもに多い過度激動(OE)とは?ADHDやHSPとの違いも解説
例えば、先生に少し注意されただけでも、「自分はダメなんだ」と深く傷ついてしまったり、友だちが怒られていると自分が怒られている気持ちになってストレスを抱えたりします。
また、世の中の不公平や社会問題に対して、大人並みの視点で悩み、「どうして戦争がなくならないの?」などと本気で考え込んでしまう子もいます。
完璧主義「失敗が怖い」
ギフテッドの子どもは、自分への期待が高く、完璧主義になりやすい傾向があります。
「100点以外は失敗」「一度間違えたら終わり」と思い込み、小さなミスでも自己嫌悪に陥ることも。
これが強くなると、失敗を避けるためにチャレンジしなくなることがあったり、人にも同様に厳しくなりがちなので、友だちとのコミュニケーションに苦労するケースも多いです。
日本の教育現場の課題ー学校はギフテッドの子をどう支援できる?
ギフテッドの子どもたちが抱える困難に対して、学校は十分な環境なのでしょうか?
教育現場ではまだまだたくさんの課題があります。
教師の理解不足
ギフテッドという概念が日本ではあまり浸透しておらず、子どもが日常生活や人間関係で困っていても、「普通の子」として適切な支援が受けられません。
マスキング現象による、本人の困りごとが表出していない場合も多いです。
個別対応が難しい
日本の学校は、一斉授業が基本ですよね。
そのため、「この子には別の課題を与えよう」という柔軟な対応が難しく、ギフテッドの子が飽きてしまっても、個別のカリキュラムを提供できない場合がほとんどです。
また、「特別支援=勉強の遅れがある子ども向け」という固定観念が強いため、ギフテッドの子は支援対象になりにくいのです。
ギフテッドの子どもも、「通常の教育では適応しにくい子ども」であり、「この子はギフテッドだから、こういう関わりをしよう」という選択肢が学校には無いのです。
ギフテッド教育は「エリート教育」と間違えられがちですが、「必要な支援」です。子どもたちが本来の自分を活かせる場を求めることは当然のことですよね。
日本のギフテッド教育の現状と学びの場
上でもご紹介したように、日本でも近年になりようやく本格的な議論が進められています。
2021年に文部科学省が「特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導」を検討開始し、2023年には推進事業が試行的に始まり、保護者や教員への周知や研究結果の公表などの活動が行われました。
しかし、制度レベルでの具体的な支援策や教育プログラムの整備はまだ発展途上であり、今後の取り組みが期待されています。
参考リンク: 文部科学省のギフテッド支援事業
文部科学省は、「ギフテッド」という言葉を(ラベリングや偏見を避けるため)使用していませんが、「特異な才能のある児童生徒」と同義とご理解いただいていいかと思います。
「特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進事業」では、「特定分野に特異な才能のある」子どもたちへの支援方策を検討してきました。
今回、その推進事業の一環として具体的な取り組みとして研修パッケージが教員向けにリリースされました。
こちらがパッケージの内容です。全部で4つのパートから編成されています。
それぞれ20分程度の動画で、具体的な状況を踏まえた考え方も紹介していて非常にわかりやすいのでご視聴してみてください。
①特異な才能のある児童⽣徒の特性の理解について『あなたの学校に「特異な才能のある児童⽣徒」が⼊学することになったら?』
②特異な才能のある児童⽣徒の特性を踏まえた授業作りについて『あなたのクラスに「特異な才能のある児童⽣徒」がいたら?』
③2E の児童⽣徒(特異な才能と学習困難を併せ有する児童⽣徒)への対応について『才能のある児童⽣徒は完璧ではない、その凸凹』
④⾼等学校における⽀援の在り⽅について『「特異な才能のある児童⽣徒」の多様で⾼い知的関⼼にどう応えるか?〜⾼校編〜』
ギフテッド教育の種類
なお、ギフテッド教育の方式には大きく2つの方法があります。
エンリッチメント方式(Enrichment)とアクセラレーション方式(Acceleration)です。
エンリッチメント方式
エンリッチメント方式は、現在の学年の学習範囲を拡張・深化する方法です。
特徴
この方式のメリットは、子どもが現在の学年の枠内でより深い学びを得られることです。
授業のペースを変えずに知的刺激を増やすことで、興味関心を引き出し意欲を高めることができます。
アクセラレーション方式
アクセラレーション方式は、学習内容を早めに進めることで、子どもがより高度なレベルの教育を受けることができます。
特徴
「もっと深く学びたい」「創造的な学びが好き」という場合は エンリッチメント方式が向いていて、「今の勉強内容が退屈すぎる」「スピードを速めたい」という場合はアクセラレーション方式が向いていると言えますが、両者を組み合わせながら活用することもできます。
日本でギフテッド教育を受けられる主な機関・プログラム
日本では、ギフテッドの子どもに対しての認知や理解が十分に進んでおらず、教育機関や団体が少ないのが現状です。
文部科学省の取り組みや、東京都渋谷区の先進的なプログラムなどが注目を集めているものの、まだまだ発展途上です。
民間でのギフテッド教育を提供している機会をご紹介します。
関連記事:ギフテッド傾向の子どもが活用できる学びの場・学び方8選
翔和学園
翔和学園では、「人間の生きていく気力を育てる」を理念に、発達特性などがあるなど何らかの事情で学校に通えない子どもたちの学びと成長を支援するフリースクールを運営しています。東京都中野区にあります。
ギフテッドの学びの場を探していると翔和学園を見つけられる方も多いと思いますが、現在はギフテッド専門のプログラムはありません。
過去には、高いIQと発達障害を併せ持ち、二重に例外的であるという意味の「2E(twice-exceptional)」の子どもに向けた専用のプログラムがありました。
現在はこのクラス自体は解体され、高IQの部分に注目することではなく本人がやりたいことに着目し、機会を提供することに重点を置く方針となっているようです。
Lagoon
ギフテッド特性のある子どもに特化したフリースクール・個別指導塾。運営側にもMENSA会員が多く、Lagoonに入るためには知能検査など一定条件があります。
ギフトスクール
3-15歳の子どもが通う、定員30名のマイクロスクールです。
ギフテッドの子どもを対象にしているというよりかは、不登校の児童などの学習支援を行うフリースクールという印象です。
東京コミュニティスクール
東京都中野区にある小学生と幼児(3歳から12歳)を対象とする全日制のマイクロスクールです。
家族的な雰囲気の中で子供たちが安心して学べる環境や、人と人とのつながりを重視したコミュニティスタイルの学校です。
アメリカのギフテッド教育は?
アメリカでは、ギフテッド教育が州ごとに制度化されており、多くの公立・私立学校でプログラムが用意されています。
- 公立学校内の特別クラス(Gifted and Talented Education: GATE)
- 飛び級制度(Acceleration)
- マグネットスクール(特定分野に特化した公立校)
- ボーディングスクール(全寮制の私立校)
GATEプログラムの詳細やマグネットスクールとボーディングスクールの違いなどは次回以降の記事で解説したいと思います。
ギフテッドの子どもに合った機会を見つけよう
子どもたちが本来持っている能力や得意なことを活かすため、そして「学校に行っても意味が無い」「居場所がない」という状況を防ぐためにもギフテッド教育は必要なのです。
学ぶ意欲が減らないよう、そして大学進学など将来の選択肢のために
そしてまた、ギフテッドの子どもが仲間と出会える場を作ることは、非常に大切です。
「自分と同じように、宇宙やプログラミングに興味を持つ友達がいる」と感じられれば、孤独感を感じることも減ります。
似たような特性を持つ友だちが身近にいることは、発達段階の子どもたちとって心の支えにもなるのです。
お子さんの才能を最大限に伸ばせる学びの場を見つけ、その違いを理解し、適切な関わり方を見つけるヒントになれば嬉しいです。
我が子はギフテッド?と思ったら
わが子がギフテッド(Gifted)かもしれない、と思ったら、まずは「ギフテッド診断」テストを受けてみることもおすすめです。
「ギフテッド診断」テストでは、子どものIQ(知能指数)や行動特性、才能のバランスを多くの側面から確認することができます。
\申込みから結果までオンライン完結/
ギフテッド診断とは
子どもの才能は、多くの側面に光を当てながら総合的に判断することが重要です。
ギフテッド診断は、4領域・全27種類の項目を測定し、子どもの才能を多面的に把握します。
より多くの方にご利用いただける価格※と内容を実現しました。
※”4領域”のうちの一つ、例えばIQテストだけでも診断項目がきちんと揃ったものを受けるためには15,000円〜50,000円程度の費用がかかります。(弊社独自調査)



診断テストの結果が活用できるように、結果についてわからないことがあれば、LINEで質問※1することができます。
さらに、お子さまの状況と必要に応じて、子どもの発達と子どもの心の専門家である医師・心理士に相談※2することもできます。どんな些細な質問でも大丈夫です。
※1 月間の質問回数の条件があります。
※2 別途料金がかかります。
\申込みから結果までオンライン完結/