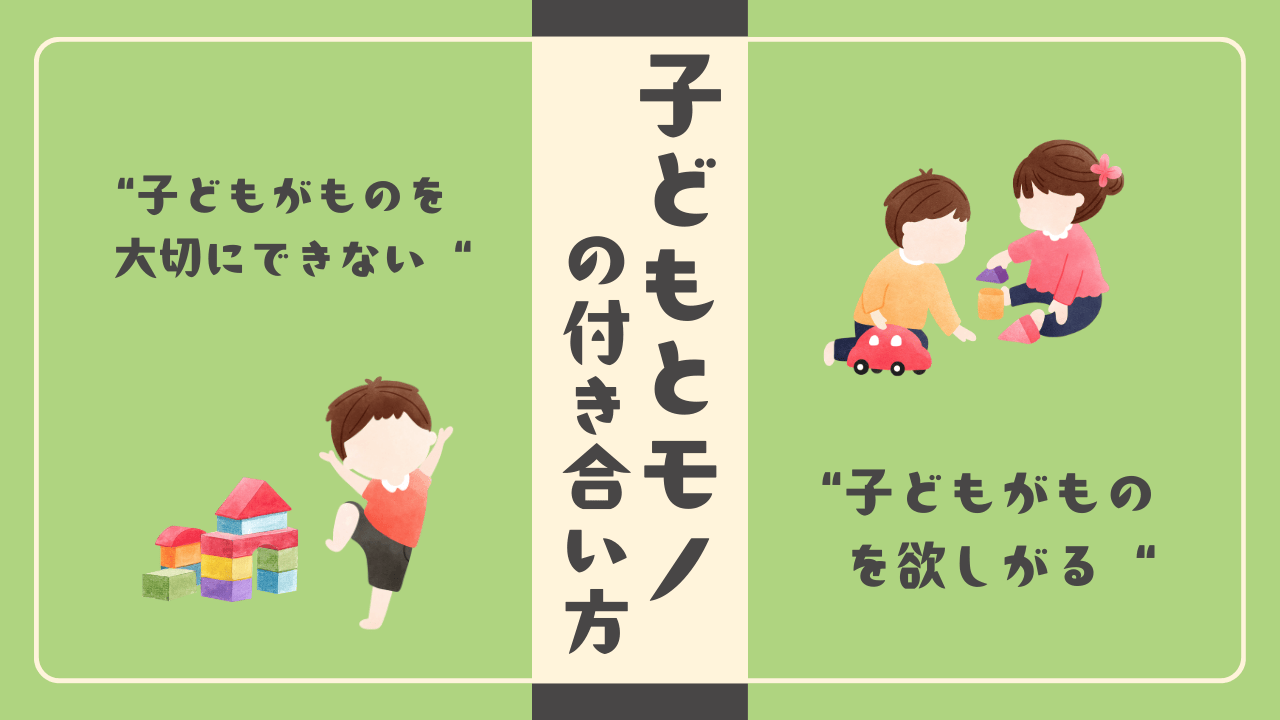「うちの子、発達障害かも…」「これって個性?」と悩む親御さんは少なくありません。
発達障害は、0歳から兆候が現れることもあれば、小学校以降で気づくケースもあります。
この記事では、発達障害がいつわかるのか、年齢別の特徴や診断の基準、早期発見のポイント、そして支援の方法についてわかりやすく解説します。
また、発達障害の診断がつくタイミングや発達の遅れが見られたときに相談すべき機関もご紹介しているのでご参考にしてみてください。

監修:いけや さき
公認心理師・臨床心理士
精神科病院、療育施設、心療内科・児童精神科クリニックなど主に医療と福祉領域にて心理士として従事。発達障害の子どもたちや保護者、女性のメンタルヘルス等のサポートを行う。
はじめに
発達障害は、0歳から兆候が現れるケースもあれば、幼稚園・保育園、小学校以降で気づかれることもあります。
また、知的障害、学習障害(LD)、注意欠如・多動症(ADHD)、やASD(自閉スペクトラム症)などは、相談機関に相談しても、年齢が低いと「もう少し様子を見ましょう」と言われることも多いと思います。
診断がつくまで不安を抱えたり、逆に「診断がついたとして、どうしよう?」という気持ちにもなると思います。
一方で、発達障害の早期発見・早期支援が、お子さんの困りごとや親御さんの不安を解消する一歩にもなります。
発達障害がいつわかるのかを知り、お子さんの特性を理解することで、適切な関わり方を検討しましょう。
発達障害とは?主な種類とその原因や症状別の特徴
発達障害とその原因
発達障害(Neurodevelopmental Disorders)とは、生まれつき脳の発達に偏りがあることにより、認知・行動・社会性・学習能力などに特定の困難を抱える状態を指します。
発達障害の特性は、乳幼児期から現れることもあれば年齢が上がるにつれて顕著になる場合もあります。
発達障害は、遺伝的要因と環境要因の相互作用によって発生すると考えられています。
日常生活での困難がある場合は、早期の発見と適切な療育・教育が非常に重要です。
近年、特に発達障害に関する情報が多く発信されていますよね。
それぞれの子どもの状態はもちろん異なりますし、日常生活での環境も異なるため、正しい支援のために我が子に合った情報を利用していくことが重要です。
発達障害の主な種類
近年では、発達障害を「障害」としてではなく「脳の多様性」として捉える場面も多くなってきました。
関連記事:新たな時代を作る!「ニューロダイバーシティ」(脳の多様性)
発達障害は、子どもの年齢や発達段階によって症状の現れ方が異なりますし、症状にも個人差(グラデーション)があります。
そのため、はっきりと診断がつく場合もあれば、「グレーゾーン」とされるケースもあり、判断が難しいこともあります。
関連記事:発達障害?知的障害?「グレーゾーン」よく聞くけど、どういう状態?~グレーゾーンを意味する2パターン〜
発達障害は大きく以下の4つに分類されます。主な特徴もご紹介しています。
自閉スペクトラム症(ASD)
コミュニケーションや対人関係に困難を伴い、特定の興味や反復行動などの特性の行動パターンが特徴的です。
自閉スペクトラム症(ASD)の「スペクトラム」とは、”仲間とみなせる範囲”を意味しています。
ASDには、「自閉症」「高機能自閉症」「アスペルガー症候群」の3種類があり、言葉の遅れやコミュニケーションの困難などに違いがあります。
たとえば、自閉症の子のなかには知的な遅れを伴う子もいますが、高機能やアスペルガー症候群の子どもは知的な遅れを伴いません。
以下は、ASDの主な特徴です。
- コミュニケーションや対人関係の困難
- 特定の興味や行動パターンへのこだわり
- 感覚過敏(音や光に敏感など)
診断がつくタイミング:1歳半〜3歳頃に最初の兆候が見られることが多いです。
関連記事:ASD(自閉スペクトラム症)とは?特徴、診断の受け方やサポート方法について詳しく解説【小中学生編】
注意欠如・多動症(ADHD)
不注意、多動性、衝動性が主な特徴で、集中力の持続や落ち着きのなさが見られます。
- 不注意(忘れ物が多い、集中力が続かない)
- 多動(じっとしていられない)
- 衝動性(順番を待てない、思ったことをすぐに口に出す)
診断がつくタイミング:幼児期~小学校低学年が多いです。
ただ、それが単なる子どもらしさなのか、パーソナリティの特性なのか、発達障害なのか、またOE(過度激動性)によるものかのの判断が難しい時期ではあります。
関連記事:小学生の子どものADHD(注意欠如多動症)とは?特徴や原因、対処法・治療法も解説
学習障害(LD)
読む、書く、計算するといった特定の学習分野において困難を抱える状態です。
- 読む・書く・計算するといった特定の学習分野の困難
- ディスレクシア(読字障害):文字を読むのが苦手
- ディスグラフィア(書字障害):文字を書くことが苦手
- ディスカリキュリア(算数障害):数の概念を理解しにくい、計算が苦手など
診断がつくタイミング:小学校入学後に学習の遅れが目立つことで判明します。
関連記事:文章の読み間違いは学習障害(LD)?ほかの可能性も解説〜チェックリスト付き〜
関連記事:漢字の壁を乗り越える!漢字が苦手な子どもへの理解と学び方の工夫
知的障害
IQ(知能指数)が概ね70以下とされ、年齢に応じた日常生活スキル(コミュニケーション、自立スキルなど)が遅れているといった適応行動の制限がある状態です。
- 知能指数(IQ)が概ね70以下
- 年齢に応じた日常生活スキル(自立、コミュニケーションなど)の遅れ
診断がつくタイミング:0歳〜3歳頃の発達の遅れで気づかれることが多いです。
発達障害はいつわかる?年齢ごとの特徴と診断のタイミング
発達障害は、子どもの年齢や発達段階によって症状の現れ方が異なり、診断のタイミングも様々です。
以下の表では、発達障害がわかる年齢の目安と特徴を整理しました。
| 年齢 | 主な発達障害の種類 | 特徴的な行動 | 診断・相談の目安 |
| 0〜1歳 | ASD 知的障害 | 視線が合わない 名前を呼んでも反応しない 言葉の遅れ 感覚過敏(音や光に敏感) 人見知りがない | 1歳半健診・2歳児健診で確認 ※1 小児神経科や小児科、児童精神科で相談できる場合もある |
| 2〜3歳 | ADHD 知的障害 | 落ち着きがない(常に動き回る) 指示が伝わらない 言葉の発達の遅れ 友達とトラブルが多い | 3歳児健診で専門機関へ相談可能 児童発達支援センターの活用が有効 |
| 4〜6歳 | 学習障害(LD) ADHD 知的障害 | 文字の読み間違い、計算の苦手さ 忘れ物が多い 時間管理ができない 集団行動が苦手 | 小学校入学前の行動などで傾向を観察 教育機関との連携が重要 |
| 小学生 | ADHD 学習障害(LD) 知的障害 | 学習や行動面の困難 時間管理が苦手 友達とのトラブル | 知能検査(WISC-Vなど)での診断 小学校の先生やスクールカウンセラー、心理士、医師などの専門家と相談しながら支援を検討 関連記事:何をどこに相談すればいい?小中学生の子育てのお悩み相談をテーマ別にご紹介 |
※1 わかりやすい症状がある場合は2歳程度で診断できることもありますが、症状が軽いと園での集団行動や学校生活が始まって診断がつくこともあります。
発達障害の子どもとの関わり方
発達障害は「いつわかるか」よりも、子ども一人ひとりに合った支援が大切
ご紹介したように、発達障害は、もちろん症状や状態にもよりますが、7歳ごろまでに困り事が顕著にあらわれて7歳までに診断を受けるケースが多いです。
一方で、子どもの成長スピードには個人差があります。特定の行動特性が見られたとしても、それが必ずしも発達障害であるとは限りません。
また、小学校高学年や中学生になってから初めて診断されることもありますし、社会に出てからわかる場合もあります。
子どもの困り事を減らすために「どんな行動ができるか」という観点で発達障害の診断や、医師などの意見を参考に活用できると良いでしょう。
関連記事:知能検査を受けさせて【発達障害】とわかったら?中学受験と進路を心理士が解説
関連記事:発達障害でないと安心?「障害かどうか」と「親として心配な子どもの状態」の関係
「いつわかるか」よりも、「どう対応するか」
上でご紹介した通り、発達障害の特性は乳児期から見られることもあれば、小学校以降に明確になることもあります。
そのため、「いつわかるのか」ということに焦点を当てるよりも、子どもの行動や発達の特性を丁寧に観察し、分かった時にどんな支援ができるかを考えることが大切です。
「診断」はゴールではなく、子どもを理解するための手段
発達障害の診断を受けたとしても、その診断は、子どもが持っている強みと困難さを明確にし、適切な支援を受けるための一つの手段であり、ゴールではありませんよね。
日本では、まだ発達障害に対する理解が十分とは言えず、「普通」との違いを気にしてしまう風潮があるかもしれません。
しかし、大切なのは子どもの「個性」として受け止め、その子に合った方法で成長を支えていくことです。
子どもの発達は一人ひとり違います。
「みんなと同じように育ってほしい」という願いは親として自然なものですが、発達障害の子どもにとっては、「普通」に合わせることが大きなストレスとなることもあります。
発達障害のある子どもたちは、一般的な学習や集団生活で困難を抱えることもありますが、独自の発想力や視点など、子どもたちそれぞれの才能があります。
以下のようなことを意識しながら関われると良いでしょう。
✔ 気になる症状があれば、早めに専門機関へ相談し、必要な診断や療育を受ける
✔ 無理に「普通」に合わせたり「できないこと」に注目するのではなく、できることを増やす工夫をする
✔ 保護者や教師、周りのお友だちも発達障害について理解し、適切な関わり方や支援の方法を実践する
✔ 子どもが興味を持つことを見つけて伸ばす、得意なことを活かせる学習方法を模索する
まとめ:「発達障害=不安」ではなく「個性」として受け止めよう
「発達障害がわかったらどうしよう…」「うちの子は将来大丈夫?」と不安を感じる親御さんも多いかもしれません。
大切なのは「障害」という言葉にとらわれすぎず、その子が持つ「特性」を理解し、適切な環境を提供し支援の仕方を工夫することです。
日本でも、少しずつ発達障害に対する理解が進み、多様な教育の選択肢が増えてきています。
発達障害があってもなくても、「その子らしく成長できる環境」を整えていくことを大切にしたいですね。
Gifted Gazeでは、経験豊富な臨床心理士や公認心理師が子育てオンライン相談を行っています。悩みは抱えずに吐き出しましょう!