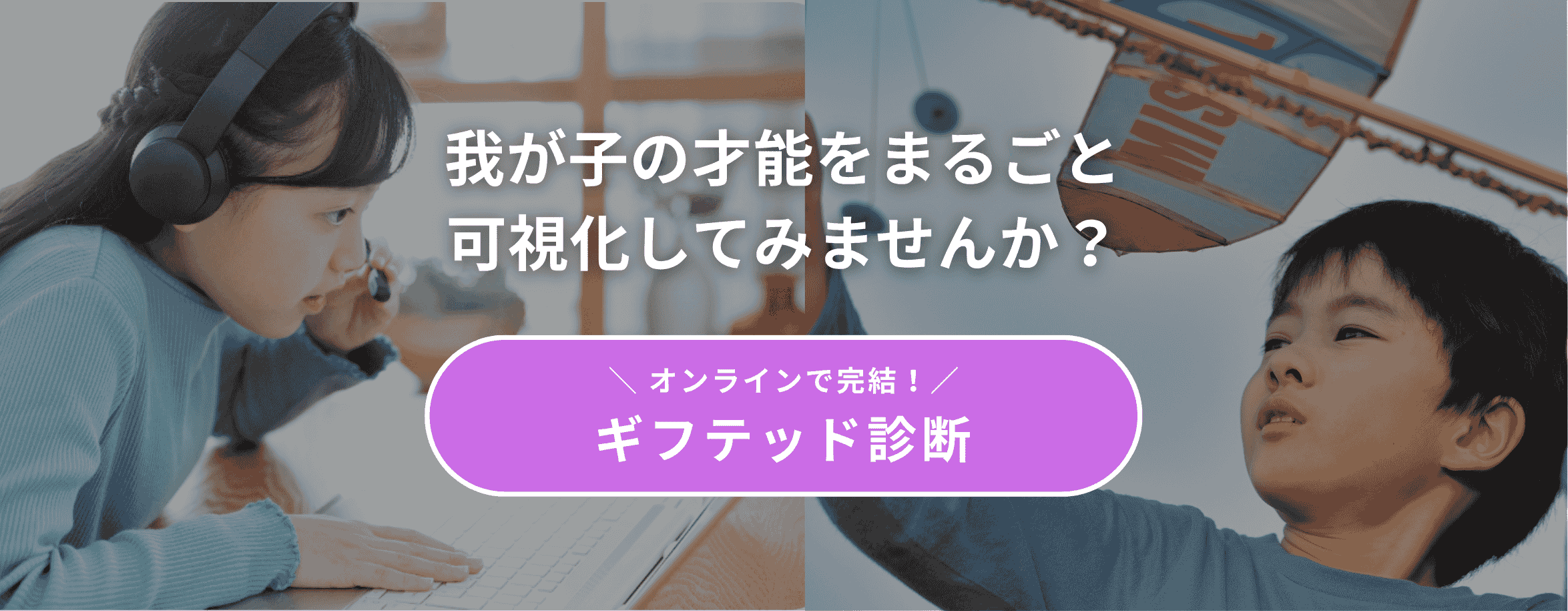「虫ばっかり追いかけていて勉強しない」「石や草ばっかり集めて…将来が不安」
そんなふうに感じたことはありませんか?でも実は、その“好き”こそが、子どもの才能の芽かもしれません。
虫や自然に強い興味を持つ子どもたちは、観察力・探究心・集中力など、STEM教育につながる力を自然と育んでいます。
この記事では、子どもの「虫好き」をどう理解し、将来の学びにつなげていけるのかをご紹介します。
この記事を書いた専門家

いけや さき
公認心理師・臨床心理士
精神科病院、療育施設、心療内科・児童精神科クリニックなど主に医療と福祉領域にて心理士として従事。発達障害の子どもたちや保護者、女性のメンタルヘルス等のサポートを行う。
虫好きな男の子が理系に向いてる理由とは
虫好きが「理系の入り口」といわれる理由は、小さな生き物への興味が科学的思考の基礎となる探究心や集中力、論理的思考を自然に育てているからです。
「この虫はなんでこんな色なの?」と興味を持つことは、仮説を立てて検証するプロセスそのもの。
「でもうちの子は算数が苦手で…」と思う親御さんも多いかもしれません。
しかし、学校の勉強が苦手でも虫への興味という学びの種を見つけることで、新しい視点が開けることがあります。
大切なのは、子どもの「好き」を見過ごさずに可能性を発見することです。
また、女の子の虫好きも珍しくありませんが、社会的期待や周囲の反応から、否定されたり見過ごされたりしやすい傾向もあります。
性別に関係なく、子どもの興味を大切にして理系脳を育てていきませんか?
「理系の才能」と言われる虫好きな子の特徴
虫好きな子どもたちを観察していると、彼らには共通する特徴があることに気づきます。
これらの特徴は、将来の理系分野での成功につながる重要な要素でもあります。
では、具体的にどのような特徴があるのでしょうか。
以下の5つのポイントを通じて、お子さんの隠れた才能を発見してみましょう。
得意や好きに極端なこだわりがある
観察や試行錯誤を好む
体験で理解するのが得意である
論理的に考える力がある
創造する力を持っている
それぞれ詳しくご紹介します。
得意や好きに極端なこだわりがある
虫好きな子どもたちの最も顕著な特徴の1つが、極端なこだわりです。
1つの虫を何時間も集中して観察したり、同じ昆虫図鑑を何度も繰り返し読んだりする姿を見たことはありませんか?
興味の強さが、学びを深めることの大きなきっかけになります。
ただ知識を身につけるだけではなく、特定の分野について徹底的に理解しようとする姿勢。
将来、その姿勢が専門的なキャリアにつながるかもしれません。
観察や試行錯誤を好む
「なんで?」「どうなってるの?」と繰り返し質問する子どもは、典型的な研究者タイプ。
虫の行動を観察し、行動の理由を考え、実際に試してみることで理解を深めていきます。
このように、トライアンドエラーする(試して失敗して学ぶ)というプロセスは、STEM分野に必要な科学的思考にとても重要です。 ※「STEM」は後段で解説しています。
観察力の高い子どもたちは、大人が見過ごしてしまうような細かな変化にも気づき、将来の研究活動において役立つからです。
体験で理解するのが得意である
教科書の文字で生物を読むより、実際に虫を触って観察して理解を深める子どもがいます。
このような体感覚優位な子どもたちにとって、「感覚知」は重要な学習手段です。
手で触れ、目で見て、時には匂いを嗅いで理解する学び方は、STEM分野では特に有効でしょう。
実験や観察を通して得られる体験的な学びは、自分の知識として定着させるだけでなく、得た知識をどう活用していけばいいか、応用力も育むからです。
論理的に考える力がある
大人以上に詳しすぎる説明をする子どももいます。
例えば、「カブトムシは夜行性だから、昼間は木の陰にいる」といった説明が自然にできるのは、論理思考の芽が育っている証拠です。
物事を筋道立てて考え、根拠を示しながら説明する能力は、STEM分野では不可欠。
幼少期からこのような思考パターンが身についている子どもは、複雑な問題解決にも前向きに取り組めるでしょう。
創造する力を持っている
自由研究で独自の観察方法を考案したり、工作で虫の模型を作ったりする。
既存の知識を組み合わせて新しいアイデアを生み出すプロセスは、新しい価値を生み出す創造力の源です。
好奇心から始まった興味を使って、試行錯誤しながら自分のアイデアを試すことで、STEM分野で求められる「新しいものを生み出す力」につながります。
なぜ「虫好き」が非認知能力を育てるのか?
虫好きな子どもたちの行動を注意深く観察していると、子どもたちが単に知識を蓄えているだけでなく、将来の成功に欠かせない非認知能力も同時に育てていることがわかります。
「非認知能力」とは、学業やテストでは測れない「人間力」「生きる力」とも呼ばれる能力で、近年その重要性が再認識されています。
以下では、虫への興味がなぜ非認知能力の育成につながるのかを解説します。
「好き」が集中力や粘り強さを育てる
虫探しに夢中になる時間は、集中力や粘り強さを育む最高の時間です。
目当ての虫がなかなか見つからなくても、諦めずに探し続ける。
どんな違いがあるのか興味深く観察を続ける。
こうした集中力や忍耐力が、将来の学習や仕事においても役立つでしょう。
虫が思うように捕まえられない時、別の方法を考えたり、場所を変えたりすることで柔軟性も身につきます。
探究心が思考力と感情コントロールを鍛える
「なぜ?」を追いかける虫好きな子は、思考力と同時に感情を整える力も身につけていきます。
興味のあることを深く調べるプロセスでは、予想と違う結果が出ることもありますが、その時に新しい視点で物事を考える力が育つのです。
虫の行動が予測と異なった時、最初は困惑するかもしれませんが、状況を受け入れて新しい発見につなげる力は、将来の研究活動や問題解決において重要な資質となるでしょう。
没頭体験が自己効力感を高める
好きなことに没頭できる子は、「自分はこれができる」という感覚(自己効力感)を持ちやすくなります。
虫のことを詳しく調べたり、観察記録をつけたりすることで、「自分は虫をよく知っている」という自信も得られるでしょう。
1つの分野で成功体験を積むことは、他の分野でも「やればできる」という気持ちを持つことにつながります。
探究心や集中力、粘り強さという非認知能力は、「好きなことに没頭できる」という才能の土台となるのです。
STEM教育の視点で見た将来につながる虫好き
近年、教育界で注目されているSTEM教育という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。
これは単なる流行ではなく、変化の激しい現代社会で活躍するために必要な能力を育てる教育アプローチです。
虫好きな子どもたちの興味や行動を STEM教育の視点から見ると、将来への可能性がより明確に見えてきます。
STEM教育ってどんなもの?
STEM教育とは、科学(Science)・技術(Technology)・工学(Engineering)・数学(Mathematics)を横断的に学ぶ教育のことです。
身近な自然体験や「なぜ?」を深める学びが、STEMの入り口になります。
虫の観察から始まり、その生態を調べ、環境との関係を考え、データを記録し分析するという一連の活動は、STEM教育の実践そのもの。
特別な教材がなくても、子どもの興味を出発点にすれば、家庭でもSTEM的な学びは十分可能です。
関連記事:STEM教育とSTEAM教育。違いや日本の事例をご紹介
虫好きから広がる未来の進路
虫への興味は、将来の様々な専門分野への扉を開く可能性があります。
昆虫学者や生物学者以外にも、環境科学や生態学、農学、医学など、多岐にわたる分野で虫の知識を活かせるのです。
例えば、虫の生態を理解するためには植物や気候についても学ぶ必要があり、やがて環境問題に関心を持つようになるかもしれません。
また、虫の体の仕組みを調べることで、生物学や医学に興味を持つ子どももいます。
幼少期の体験が専門分野の原点になることは珍しくありません。
多くの研究者が、子どもの頃の自然体験や好奇心が現在の研究テーマにつながっていると語っています。
まとめ
虫や自然に夢中になる子どもたちは、好奇心を原動力にあらゆるスキルを育てていきます。
STEM教育の土台となるだけでなく、非認知能力という生きる力を育てているのです。
「好きなこと」に寄り添い、「そのままでいい」と伝えること。
そこから始まる子育てが、子どもの才能を引き出し、自信につながります。
夏という季節、虫好きの子どもが輝くチャンスを、ぜひ家庭でも応援してあげてください。
Gifted Gazeでは、STEM教育と関連性が深いとされるギフテッドの可能性がわかる「ギフテッド診断」をご用意しています。
虫好きは才能のヒント。我が子に隠されたいろんな才能を探してみませんか?
我が子はギフテッド?と思ったら
わが子がギフテッド(Gifted)かもしれない、と思ったら、まずは「ギフテッド診断」テストを受けてみることもおすすめです。
「ギフテッド診断」テストでは、子どものIQ(知能指数)や行動特性、才能のバランスを多くの側面から確認することができます。
\申込みから結果までオンライン完結/
ギフテッド診断とは
子どもの才能は、多くの側面に光を当てながら総合的に判断することが重要です。
ギフテッド診断は、4領域・全27種類の項目を測定し、子どもの才能を多面的に把握します。
より多くの方にご利用いただける価格※と内容を実現しました。
※”4領域”のうちの一つ、例えばIQテストだけでも診断項目がきちんと揃ったものを受けるためには15,000円〜50,000円程度の費用がかかります。(弊社独自調査)



診断テストの結果が活用できるように、結果についてわからないことがあれば、LINEで質問※1することができます。
さらに、お子さまの状況と必要に応じて、子どもの発達と子どもの心の専門家である医師・心理士に相談※2することもできます。どんな些細な質問でも大丈夫です。
※1 月間の質問回数の条件があります。
※2 別途料金がかかります。
\申込みから結果までオンライン完結/