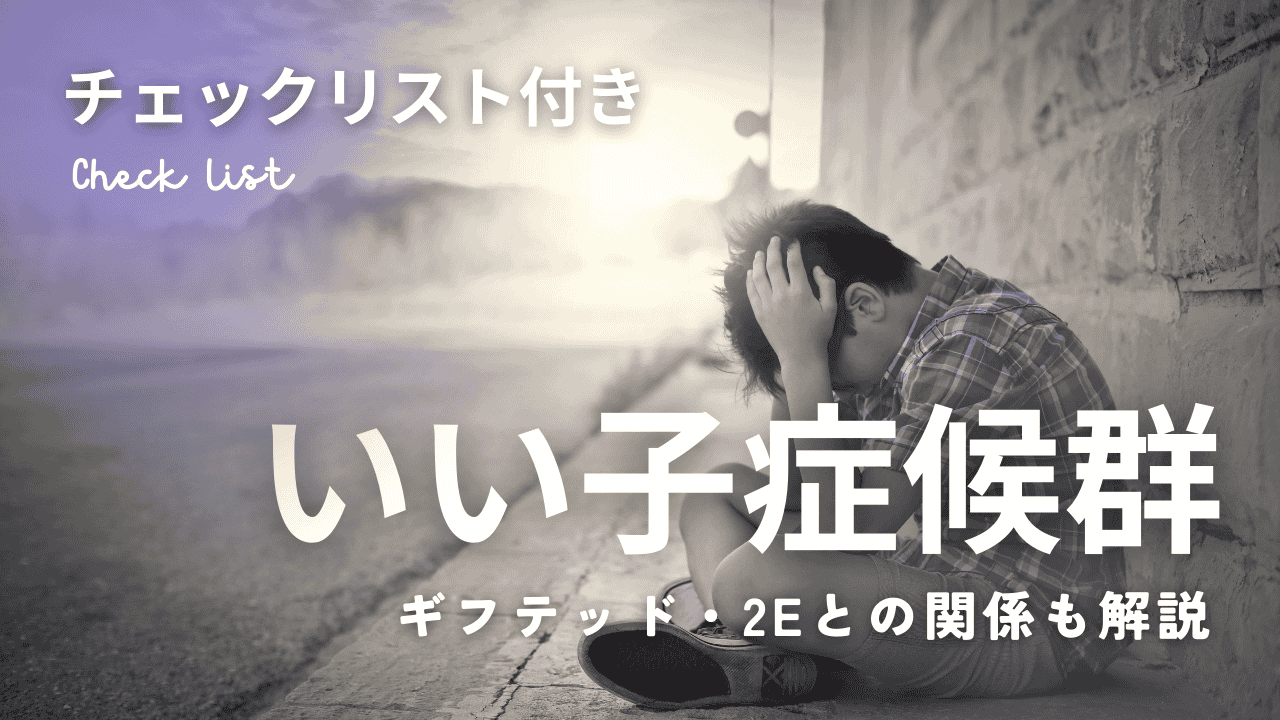「友達やきょうだいとのトラブルが多い」「学校や社会でうまくやっていけるだろうか」など、子どもの協調性について心配になったことがある方も多いかもしれません。
また、子どもの特性を理解しているからこそ、協調性と聞くだけで苦手意識を感じられる方もいらっしゃるかもしれませんね。
今回の記事では、協調性とは何なのか、また、子どもが協調性がないように見える振る舞いをした時どう理解しておくと良いのか、日常生活の中での対応の仕方についてご紹介します。

執筆:山崎 日菜乃
公認心理師・臨床心理士
心理士としてメールカウンセリングに3年半従事し、家族関係の悩み、心身の不調、仕事の悩みなど、様々な困り事へのサポートを行う。アメリカ合衆国在住。
協調性とは
協調性とは、利害や性格や意見などが異なる人とうまくやっていくことができる性質のことです。
人と意見がぶつかった時、相手に合わせたり、お互いにとってより良い解決策を話し合ったり、協力して動いたりと、うまくやっていく方法は色々とありますよね。
協調性とは、そのように受け身的なスタイルから能動的なスタイルまで、色々な態度を含む包括的な概念です。
子どもの協調性がない?「協調性」に関する3つの誤解
以下では、よくある協調性に対する誤解を通して、その本質や多様な形を整理してみます。
誤解1. 周りと違う意見を飲み込めない子は協調性が低い!
日本では、文化的な背景により、人との対立を避けたり、自分の気持ちや考えを抑えて人に合わせようとするスタイルの協調性が発達しやすいと言われています。
確かに、人と合わせるのは協調性の一つのあり方ですが、人に合わせないからといって協調性が低いというわけではありません。
また、長期的によりよい人間関係や集団を築いていくには、誰かが譲るばかりでなく、様々な意見を出し合って話し合うことも必要となってくるでしょう。
人やルールに合わせる、譲るスタイルばかりでなく、建設的にお互いの意見を出し合えたり、話し合ってこそたどり着けるよりよい解決策を探っていくようなスタイルも大切な協調性のあり方の一つです。
誤解2. 指示に従ったり、みんなと同じように動けない子どもは協調性が低い!
協調性をはじめとしてその子が持っている力を十分に発揮するには、安心できる環境や信頼できる人間関係が必要です。
相手を信頼できなかったり、安心できない集団においては、協調性が高い子でも、その力を発揮できないこともあるでしょう。
大人でも、居心地がいい相手や集団と、そうではない相手や集団がありますものね。
また、その集団に貢献したいというモチベーションが持てなかったり、指示やルールに従うことの大切さがよく分かってないという可能性も考えられます。
このように、指示に従わない、人と違うことをすることの背景には協調性だけでは片付かない、その子の考えや気持ちがある可能性も大いにあるでしょう。
誤解3. 協調性は高ければ高いほどいい!
必要以上に人に協調してしまうと、過剰適応という状態になってしまう恐れがあります。
過剰適応とは、自分の気持ちを押し殺してまで相手や集団の期待に応えようと頑張りすぎてしまい、心や体に悪影響が出てしまう状態です。
例えば、嫌な要求を断れない、いつも本音を隠して相手に同意する、常に周りの顔色を伺いながら行動するなどです。
人と上手くやっていくことばかりに意識を向けるのではなく、自分の心や体を大事にすることとのバランスをとることがとても大切です。
子どもの協調性が気になるきっかけと、その対応アイデア
この記事にたどり着いて下さったのは、子どもの協調性について気になっておられるからかもしれませんね。
そう感じられたきっかけはどのようなことだったでしょうか?
日常生活や遊び、習い事、学校の教室の中でのコミュニケーションの様子を見て「協調性が育てられていないかも」というご相談は多いです。
学校の先生や他の大人から指摘された
学校のように、規律やまとまりが重視されている集団では、みんなと同じように行動する、指示をよく聞いてそれに従う、衝突しそうな時に相手に譲るといったことができているかという基準で協調性が判断されることがあります。
そのため、子どもがそうした行動に当てはまらないと、協調性がない、反抗的などと誤解されてしまうこともあるかもしれません。
特定の集団、特定の大人に対する言動だけで子どもの協調性について判断してしまうと誤解に繋がる恐れがあります。
異なる場面や異なる集団で楽しく集団行動ができる時があったり、違う人の指示なら聞けるといったことはないでしょうか?
また、協調性がないと言われた場面で、子どもがどうしてそういう行動をするのか、じっくり話を聞くことも大切です。
子どもは大人が想像する以上に色々と考えを巡らせて行動していることも多く、大人が先に決めつけてしまうと信頼関係を損なってしまうことにも繋がりかねません。
良し悪しで評価してしまう前に、まずは子どもの考えや気持ちを理解できるといいですね。
友達やきょうだいとのトラブルが多い
大人と同様に子供も、人との相性がありますから、うまくいかない相手がいるのは自然なこととも言えるでしょう。
また、人間関係のトラブルは、自分、相手、環境といった様々な要素が複雑に絡み合っていますから、原因を子どもの協調性のせいだけに決めつけてしまわないよう注意が必要です。
トラブルになった時の状況やその時の気持ちなど、まずは子どもの話をしっかり聞きましょう。
人に意見や感情を伝えられることは強みでもありますが、色々な相手との間にトラブルが続く場合は、意見や感情の伝え方聞き方、それらのバランスの取り方に練習が必要かもしれません。
家庭で子どもの発言について「○○って言われてうれしかったな(悲しかったな)」などとポジティブな気持ちもネガティブな気持ちも伝えてあげると、子どもが相手の気持ちに意識を向けるきっかけになるかもしれません。
そこから、「△△っていう言い方にしてみたらどうかな?」「言いすぎたと思ったら”さっきは言いすぎてごめんね”って言えばいいよ」などと代替案やリカバリー方法を練習してみるのもいいと思います。
また、攻撃的やいじわるに見える態度を繰り返す場合、意見や気持ちを言葉にすることが難しいために乱暴な言動が出てしまっている可能性も考えられます。
そういう場合は、気持ちに名前をつける練習をしたり、子どもの気持ちや考えを言葉にして伝え返してあげることなどもよいサポートになるでしょう。
自分の意見やこだわりがあったり、それを表現できるのは素敵なことですから、それを大切にしつつ、より気持ちのよい表現の仕方を身に付けられるといいですね。
一人でいることが多い
一人でいることは、特に子供時代ではネガティブな意味合いでとらえられることが多かったり、見ていて心配になってしまうこともありますよね。
その一方で、自分で自分の過ごし方を選び、一人でいられるというのはその子の力であり、主体性や自立性の表れとも言えるでしょう。
また、一人でいることが多いからといって人間関係を経験していないとは限らず、常に一緒にいなくても大丈夫な健康的な友人関係を築けている可能性もあるでしょう。
また、人と関わることでたまった疲れを、一人の時間に回復している可能性も考えられます。
人と関わることと一人で過ごすことの適度なバランスや好き度合いは人によって様々ですから、子どもの感覚やペースを尊重してあげられるといいですね。
協調性の問題だと結論付けてしまう前に、まずは子どもが一人でいる時の気持ちや、人間関係で困っていることがあるかなどをよく聞いてみることが大切です。
もし人との関わり方に悩んだり自信がないようであれば、悩みに寄り添い、自信がないポイントについてご家庭で練習してみるのもいいですね。
また、学校やクラスという限られた場だけでなく色々なところで人と出会うことができるんだよという選択肢を伝えたり、子どもが乗り気であれば興味のあるコミュニティに参加してみるのもいいかもしれません。
発達障害の診断やその傾向がある
発達障害のある子どもの場合も、協調性がないように見える振る舞いが他の理由からきていたり、協調性はあるけれど発揮できていないことも少なくありません。
例えば、環境が騒がしすぎたり刺激が多すぎて必要な情報を拾えていなかったり、相手の発言や表情の意味を読み取るのが難しかったり、協力したいけれどどう振る舞えばいいのか分からないといったこともあり得るでしょう。
子どもの特性に合わせて環境を居心地よく調整したり、コミュニケーションの取り方を工夫する(明確な表現を使う、否定形でなく肯定の文章で伝える、イラストや表を使うなど)、ソーシャルスキルトレーニングで練習するといったことで子どもが協調性を発揮しやすくなる場合もあると思います。
また、子どもが幸せに生きていくための力は協調性だけではありません。
協調性に着目することで子どもの自己肯定感が下がってしまっては本末転倒でもありますし、子どもの興味や得意なことが思わぬ形でコミュニケーションや人間関係を助けてくれることもあるはずです。
とはいえ、子どものことを大事に思っているからこそ苦手な部分が心配になってしまうのはとても自然なことです。
悩んだ時には第三者に相談したり(第三者だからこそ見えている子どもの意外な一面もあるかもしれません)、時には、子どもがどんな時に楽しそうであったり生き生きしているか、すでにどのような力や素敵なところを持っているかにも意識を向けられるといいですね。
おわりに:協調性がないことは気にしなくていい!
子どもが協調性がないと言われたりそう見える振る舞いには様々な背景があります。
また、それは子どもが周りに流されず自立しているということや、遠慮や我慢をしすぎず自分らしく振る舞えているという強みとも言えるでしょう。
子どもの言動の背景にはどのような気持ちや考えがあるのかをよく聞きながら、子どもが困っているポイントに合わせて、サポートや練習ができるといいですね。
ご家庭での対応が難しかったり不安な時には、専門家に相談することも検討していただけたらと思います。
参考文献
登張 真稲首藤 敏元大山 智子名尾 典子(2019)3因子で捉える多面的協調性尺度の作成. 心理学研究90(2), 167-177