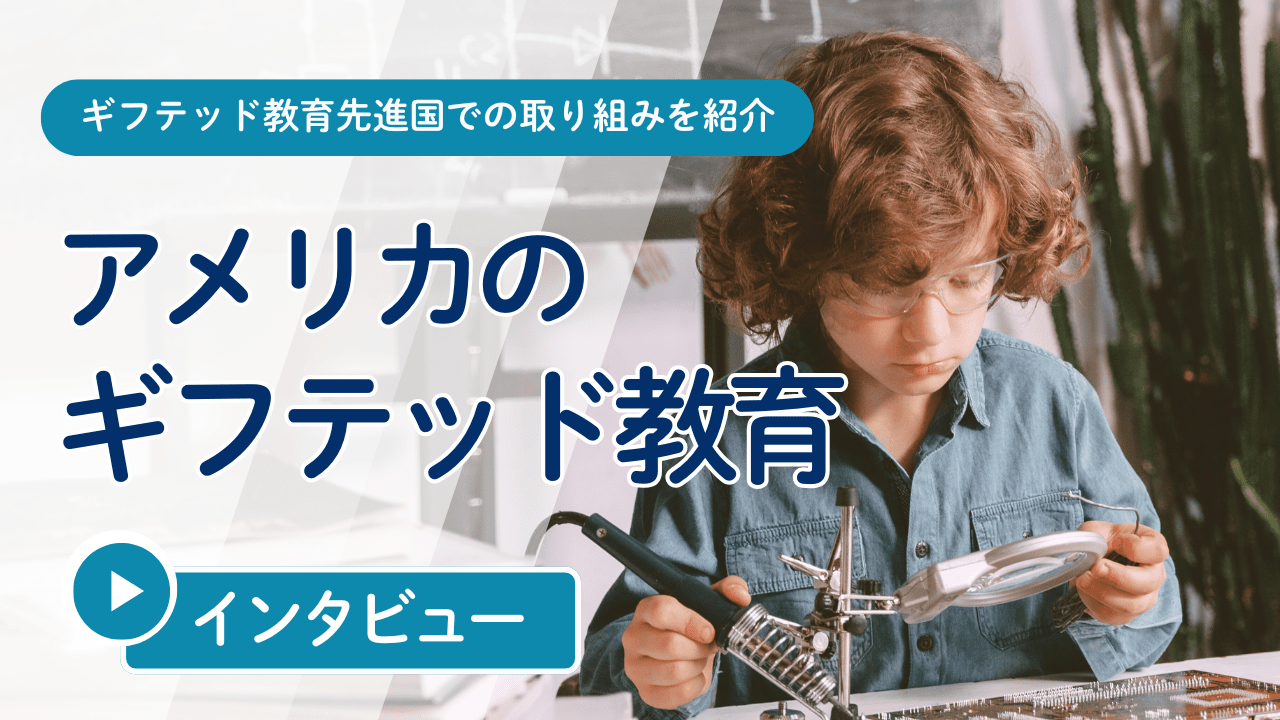子育ての中で、避けがたいのが「比較」の問題です。
きょうだい同士の違い、学校での順位、SNS上での他者との比較
—これらはすべて、子どもの自己肯定感に影響を与える要素です。
しかし、「比較=悪いこと」ではありません。
正しく向き合い、伝え方や関わり方を工夫することで、比較はむしろ子どもを成長させ、自己肯定感の土台を育むこともできるのです。
この記事では、比較がテーマの3つの場面について、保護者の立場からできることを考えていきます。
子どもの心にそっと寄り添うための、ちょっとした工夫をご紹介しているのでぜひ最後まで読んでみてください。
自己肯定感に影響のある”比較”とは?
子どもを育てる中で、どうしても避けられないのが「比較」です。
きょうだいの違いや学校での順位、SNSでの他者との違い……。こうした比較が、子どもの自己肯定感に影響を与えるのは確かです。
しかし、比較=悪いこととは限りません。
本来、比較は子どもの特性や個性を理解するための一つの手がかり。
それを「どう伝えるか」「どう関わるか」次第で、比較は子どもを傷つけるものではなく、自己肯定感の土台を育む関わりへと変わっていきます。
子どもが「比べないで!」と感じるとき親の向き合い方
以下では、具体的な日常の”比較”のシーンを踏まえて、子どもの自己肯定感への影響を考えてみましょう。
きょうだい間の“評価付きの比較”に要注意
「弟の方が優れている気がする」「なんで私だけ怒られるの?」
きょうだいの中でも、特に上の子が敏感に反応するのが、“親からの比較”です。
実は、きょうだいの違いに気づき、それぞれに合った接し方をすること自体は悪いことではありません。
「この子にはこういう言い方が伝わりやすい」「あの子にはこんな環境が合う」
先ほどお伝えしたように、こうした個性への理解をもとにした比較は、むしろポジティブな関わりと言えるでしょう。
問題となるのは、「評価をともなう比較」です。
「弟はあんなに頑張ってるのに」「お姉ちゃんはもっとちゃんとしてたよ」といった言葉は、子どもの心に劣等感や反発心、不信感を生んでしまいます。
子どもが「比べないで」と訴えてきたときは、自分の言動に“評価の軸”が入っていなかったか、ぜひ振り返ってみてください。
そして、「あなたはあなたのままで大切だよ」というメッセージを、繰り返し伝えることが何よりの対処法です。
子どもが頑張りすぎていたら
子どもが一生懸命頑張りすぎて、心身ともに疲れているように見える時、「頑張らなくてもいいんだよ」と声をかけたくなることはありますよね。
このような言葉が子どもの自己肯定感を下げるかどうかというと、一概にそうではありません。
むしろ、「あなたの努力をちゃんと見ているよ」「これ以上無理しなくていいよ」というメッセージとして伝われば、子どもは安心し、自己肯定感は守られます。
ただし、「もう頑張らなくていいから、やめなさい」といった形で、子どもの挑戦したい気持ちを否定するような伝え方になってしまうと、かえって「自分は認めてもらえていない」「頑張っても意味がない」と感じてしまうこともあります。
表現を変えて、「あなたが今まで頑張ってきたことは、ちゃんと伝わっているよ」「もう十分やってるの、知ってるよ」といった言葉にしてみると良いでしょう。
大切なのは、“頑張りを評価する”のではなく、“頑張っているその姿を受け止める”ことです。
順位付けは本当に悪い?
競争と自己肯定感の「健全な関係」を育むコツ
学校では運動会、テスト、スピーチ大会など、様々な場面で順位がつきます。
「負けて傷つかないか」「自己肯定感が下がるのでは?」と心配する声もありますが、実は競争そのものが悪影響を与えるわけではありません。
大切なのは、結果だけでなく“過程”に価値を見出す考え方を育てることです。
たとえば、「負けちゃったけど、すごく練習頑張ったよね」「チャレンジして成長したことが何よりの宝物だね」など、努力を認める言葉がけが重要です。
結果で落ち込む子どもに対して、親が「絶対的な味方」として見守ってくれていることが伝われば、子どもは安心して何度でも挑戦できるようになります。
さらに、多くの子どもは競争が好きです。勝てば嬉しいし、負ければ悔しい—その感情の動きそのものが、心の成長の一部なのです。
競争を避けるのではなく、その経験をどう受け止めるかを親子で共有することが、自己肯定感の健やかな育ちにつながります。
SNSでの「他人との比較」が子どもに与える影響
SNSが身近になる中で、子どもが「他の子と比べて自分は劣っている」と感じていないか、心配に思う保護者の方も多いのではないでしょうか。
SNSと自己肯定感の関係について、重要なポイントは2つあります。
① SNSを使う前に、自己肯定感の“コア”を育てる
とくに小学生期は、リアルな人間関係の中で「ありのままの自分が受け入れられる」経験をたくさん積むことが必要です。
この時期に「無条件に大切にされた」体験を重ねておくことで、中学生以降、SNSで比較されても揺らぎにくい心の基盤がつくられます。
② SNSの「仕組み」と「偏り」を理解する
SNSは、自分が興味をもっている内容ばかりが流れてくる仕組みになっています。
すると、ある種の「世界の一面しか見えない状態」に陥りやすくなり、自己評価をゆがめる原因になります。
親子でSNSのリスクや仕組みについて会話をしておくことで、「あの人は本当に幸せなのかな?」「これって一部の情報かも」といった冷静な視点=リテラシーを育てることができます。
制限するだけでなく、対話を通じて信頼関係を築いておくことが、SNS時代の自己肯定感を守るうえで何よりも大切なのです。
おわりに:比較は“使い方”しだいで、成長の味方になる
比較、競争、SNS—すべては子どもが社会と向き合っていく上で避けて通れないものですよね。
だからこそ、親がどう受け止め、どう伝えるかが、子どもの自己肯定感にとって決定的な意味を持ちます。
比較は時に子どもを傷つけることもありますが、正しく使えば、違いを認め合い、自分を大切にする力を育てるきっかけにもなります。
「あなたはあなたのままで大切」
その一言が、子どもの中に揺るがない自己肯定感を育てていくはずです。
こちらの動画で専門家が詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。