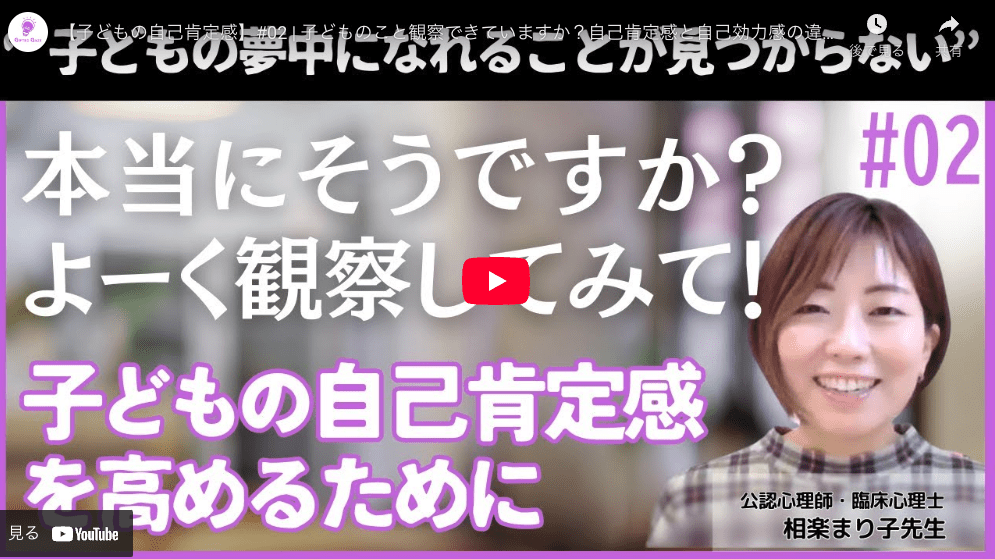「自己肯定感」「やる気」「褒め方」。
子育てのキーワードとして耳にするけれど、実際どうすればいいの?と悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、子どもの発達や心理学の視点から、子ども自己肯定感や自己効力感を育てるために『夢中になれること』の効果を、すぐに使える実践的な声かけのコツと合わせてご紹介します。
自己肯定感とは何か?
自己肯定感(Self-Esteem)とは、「自分自身の価値を無条件に受け入れられる感覚」のことです。
自己肯定感とは、「どんな自分でも、存在するだけで価値がある」と思える気持ち。
うまくいっても、失敗しても、できてもできなくても、「自分は大事な存在だ」と思える力です。
たとえば、
このような気持ちが、自己肯定感です。自分を“丸ごと”認める感覚ですね。
合わせて読みたい;子どもの自己肯定感#01 |「自分を信じる力」はなぜ大切なの?専門家が詳しく解説
自己効力感とは
自己肯定感と自己効力感の違い
「自己肯定感」のよく似た言葉に「自己効力感」があります。
自己肯定感は、先ほど説明した通り「自分は大事な存在だ」と思える力のことです。
対して、自己効力感は「自分ならできる!」と感じる自信や、チャレンジする勇気というイメージです。
こうした「行動への自信」や「やってみようとする気持ち」が自己効力感です。
自己肯定感と自己効力感の関係
この2つの力は、密接に関係しています。
簡単に言うと、自己肯定感が「土台」で、自己効力感がその上にのっている「柱」みたいなものと考えるのがわかりやすいかもしれません。
自己肯定感があるからこそ、「できなくても自分は価値ある存在」と思えるし、自己効力感があると、「やってみたい!やれそう!」と前向きに行動できるからです。
この両方があると、
そんな、しなやかで強い心が子どもたちの中に育っていきます。
自己肯定感を育むために:子どもが夢中になれることのチカラ
小さな“好き”が大きな自信に
子どもが自己肯定感を育むために、とても大事なのが「夢中になる体験」です。
でも、そもそも「夢中になる」って、どんな状態でしょう?
それは、
こんなふうに、頭も心も全力で取り組んでいる状態です。
夢中になれるものには、子どもにとって「ちょうどいいチャレンジ」の要素があります。
簡単すぎるとすぐ飽きてしまうし、難しすぎるとあきらめたくなる。
でも、「あと少しでできそう!」というレベルだと、どんどんやりたくなりますよね。
そして、夢中でやっている中には、
こういう“トライ&エラー(やって→失敗して→またやる)”がいっぱい詰まっています。
この繰り返しが、自分で考えて動く力を育て、結果的に「自分ってけっこうやれる!」という自信=「自己肯定感」へとつながっていきます。
子どもの夢中になれることの見つけ方
そして、よくあるのが「うちの子、何にも興味がないんです…」というお悩み。
でも、本当に「興味がない」のでしょうか?
実は、子どもの“好き”は、大人の期待と違う方向にあることがよくあります。
たとえば、
「これが夢中の始まりかも?」という視点で見てみると、子どもの“好き”って、実はすぐそばにあります。
大人が「これをやらせたい」と思って与えるよりも、子どもが自然にハマっていることに目を向けるのが、夢中のタネを見つけるコツです。
自己肯定感を高めるための”褒め方”のポイント
では、子どもが夢中になれるものが見つかったあとはどうすればいいのでしょうか?
おさえておきたいポイントは、子どもは大人の“本音”をちゃんと見ているという点です。
「もっとやらせたい」気持ちは子どもに伝わっている
子どもを褒めるって、すごく大切なことですよね。
でも、「褒めすぎるとよくない」って聞いたこと、ありませんか?
これは実は、「褒める=操作しようとすること」になっている時の話なんです。
子どもは親の“裏の気持ち”に敏感
「これを褒めれば、またやってくれるはず」
「こうすればいい子になるかな」
そういう“ねらい”があると、子どもは「褒められた」というより「コントロールされた」と感じます。
すると、
こんな反応になってしまうこともあります。
本心からの言葉が一番うれしい
逆に、心から「いいな」と思ったことをそのまま伝えると、子どもの心にまっすぐ届きます。
たとえば、
そんな言葉が、子どもにとっては「ちゃんと見てもらえている」という安心感につながります。
まとめると、この2つです。
子どもの心を育てるのは、「すごいね!」という言葉よりも、「ちゃんと見てるよ」の気持ちかもしれませんね。
【番外編】我が子がテストで悪い点をとってきたら?
たとえば、テストの点が悪かったとき、親はどうするのがベストだと思いますか?
これ、どの保護者の方も一度は感じたことがあるのではないでしょうか。
本来の「テスト」の意味に立ち戻ってみる
子どものためを思っているからこそ、子どものテストの点や成績に対して親として感情的になってしまうこともありますよね。
でも、少しだけ視点を変えてみましょう。
テストって、そもそも誰のためのものでしょうか?テストは、「子ども自身のためのもの」です。
自分の苦手なところを知るため、自分の実力を確かめるため、そして、今後どう勉強すればいいかを考えるためのものですよね。
つまり、「点数=評価」ではなく、「点数=学びのチャンス」なんです。
親が感情的にならないために
点数が悪かったとき、親が「なんでこんな点数なの?!」と怒ったり、ガッカリしたりすると、子どもはこう感じます。
こうなると、テストの意味が「成長のチャンス」から、「親の評価を避けるためのもの」に変わってしまいます。
ベストな対応は「リアクションを控えること」
本当に理想を言えば、「何も言わない」のが一番いいのかもしれません。
ただ、それって難しいですよね。受験もあるし、将来も気になる。
だからこそ、「今はこの点数が返ってきたんだな。これが子どもの“今の地点”なんだな」と受け止めてあげましょう。
テストの点を責めるのではなく、
という言葉がけで、子どもと一緒に“次”を見つめる姿勢が、何よりの応援になります。
おわりに
自己肯定感や自己効力感は、目に見えないけれど、子どもにとってとても大切な「心の土台」です。
大人ができることは、子どもの夢中を見つけ、そっと応援し、本心で関わること。
テストの点などよりも、「どんな気持ちで向き合っていたか」に目を向けて、毎日をともに歩んでいけたら素敵ですね。
こちらの動画で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。