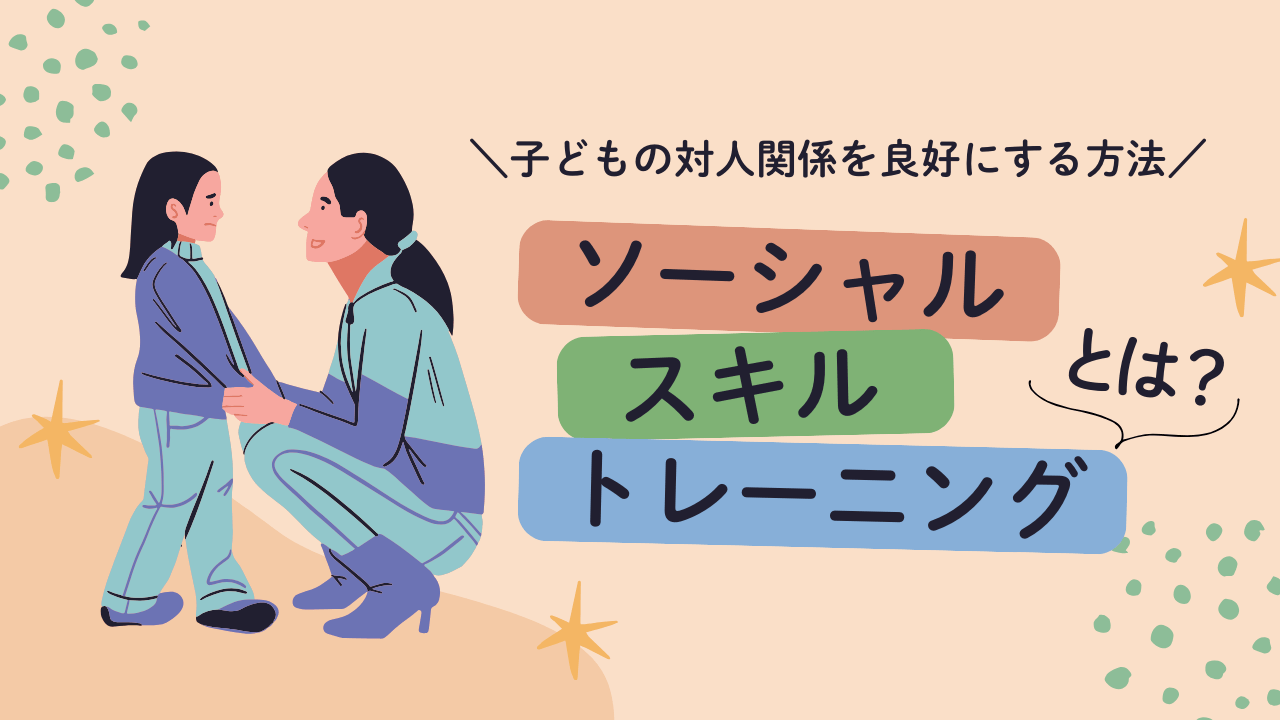「友だちとうまく話せない」「トラブルになりやすい」
子どもの対人関係について悩む保護者様は多いでしょう。
しかし、学校にいる間の様子はわかりにくく、どう対応したらいいかわからないですよね。
子どもの対人関係で悩みが多くなる背景の1つには、社会性や対人関係スキルの未習得があるといわれています。
そこで注目されているのが、ソーシャルスキルトレーニング(SST)です。
今回は、精神科病院で成人向けのSSTを実施し、その後に療育施設で子どもの個人SSTを経験した臨床心理士が、SSTについて解説します。

執筆:いけや さき
公認心理師・臨床心理士
精神科病院、療育施設、心療内科・児童精神科クリニックなど主に医療と福祉領域にて心理士として従事。発達障害の子どもたちや保護者、女性のメンタルヘルス等のサポートを行う。
ソーシャルスキルトレーニング(SST)とは
ソーシャルスキルトレーニング(以下、SST)とは、社会生活のなかで人と関わるために必要なスキル=「ソーシャルスキル」を身につけるためのトレーニングです。
子ども向けに実施するときは、遊びやロールプレイなどを通して実践的に学べるのが特徴。
ここでは、学べる具体的なスキルや方法を紹介します。
SSTで身につける具体的なスキル例
SSTでは次のようなスキルを身につけられます。
対人関係に限らず、生きていくために必要なセルフケアの方法なども含め、ソーシャルスキルといいます。
学校生活や家庭の中で、困りやすいもしくはトラブルになりやすい場面を解決していくための方法です。
医療機関だけでなく、学校や児童発達支援事業所、放課後等デイサービスなどで取り入れられています。
SSTでソーシャルスキルを身につける方法
SSTの基本的な流れは次の通りです。ただし、対象となる子どもの年齢や学ぶスキルによって「遊び」「ゲーム」のような感じで進めることもあります。
なぜ子どもの対人関係にSSTが必要なのか?
ソーシャルスキルトレーニングが「なんとなく必要そう」であることは想像つくかもしれません。
では、具体的にどうしてSSTが必要なのかを子どもに聞かれたら、みなさんはどう答えますか?答えられるように、SSTの必要性を学びましょう。
対人関係に正解はないけど土台は必要である
人との関わり方には、教科書のような「これが正解!」というたった1つの答えがあるわけではありません。
場面や相手によって、適切な対応は変わります。SSTでは具体的な場面を想定して、何度も練習を重ねます。
対人スキルは一度学んだだけでは身につきにくく、繰り返し経験しながら、日常生活に生かしていくことが重要だからです。
普段の生活でも学べることはたくさんありますが、SSTという枠組みがある方が理解しやすい子どももいます。
実践しないとわかりにくいものもある
あいさつのタイミングや、相手の表情から気持ちを読み取るスキルなどは、言葉の説明だけでは理解しづらいものですよね。
SSTではロールプレイやグループワークを通して、実際の場面を模擬体験し、「こうすればいいんだ!」「伝わった!」という気づきが得られます。
SSTはゲームや視覚的な教材で楽しく学べる
特に子ども向けSSTでは、イラストカードや絵本、簡単なゲームを使って楽しく学ぶ工夫がされています。
「勉強」や「訓練」などの堅苦しい雰囲気ではなく、遊びの延長のような形で行われるため、子どもたちも抵抗なく参加しやすいのが特徴です。
楽しい体験を通して、自然に「人と上手に関わる力」が育っていきます。
成功体験が自己肯定感や安心につながる
「うまくできた!」「伝えられた!」という体験は、子どもにとって大きな自信になります。
SSTでは、一人ひとりのペースに合わせてステップを細かく分けて(スモールステップ)進めるため、無理なく達成感を得られるのです。
積み重ねた小さな成功体験は、自己肯定感や対人不安の軽減にもつながるでしょう。
SSTと発達障害の関係性
SSTはどんな人にもおすすめですが、特に発達障害を持つ子どもに効果が高いとされています。
発達障害のある子は、自身の症状や状況を感じ取りにくい傾向があり、対人関係で嫌な思いをしやすい子も多いからです。
たとえば自閉スペクトラム症(ASD)の子は、相手の気持ちをくみ取ることが難しいのが特徴の1つ。
注意欠如・多動症(ADHD)の子どもは衝動的に行動したり、順番を守るのが苦手な傾向があります。
SSTでは、発達障害の子どもたちが楽しいと感じられる環境で、対人スキルを段階的かつ具体的に学べます。
成功体験を積みながら、自分らしく人と関われる力を育てられるのがソーシャルスキルトレーニング法です。
SSTの実践的なトレーニング例
SSTで身につける具体的なスキル例
子ども向けのSSTは、楽しみながら学べるようにゲームやロールプレイをたくさん取り入れています。
低学年向けのSST例
低学年の場合、「ルールを守る」「基本的なコミュニケーションスキル」を学ぶことが重視されて行うことが多いです。
たとえば、以下のようなゲームが行われます。
学校生活は先生の指示を聞いたり、友達と協力したり、順番を守ったりすることが大切です。
低学年の子どもには遊びやゲーム、絵カードを用いて「楽しみながらできる」という点を重視することが、SSTで重要となります。
高学年以降向けのSST例
教材を用いることもあれば、低学年向けの方法を発展させたものを行うことも多いです。
たとえば「並び替えゲーム」などでルールを守ったり、友達に質問したりする練習を行います。
「お店屋さんごっこ」も発展し、店員さんとお客さん役に分かれて「お願いします」「ありがとうございます」と実践することもあります。
数人で行うことで、ほかの子のやり方を見て学んだり、お互いのいいところを取り入れる機会にもなるでしょう。
また、絵カード以外にプリントなどを用いて視覚的に学ぶことも。
「こういうときどうしますか?」「どっちの方がいい行動だと思いますか?」とイラストで見せて、答えてもらったり選択してもらったりします。
SSTが受けられる場所
SSTは以下のような場所で受けられます。
興味のある人は、ぜひ問い合わせや見学をしてみてくださいね。
SSTは専門家ではなくても実施できます。
しかし、より効果的に学ぶなら専門家によるSSTがおすすめです。
たとえば、臨床心理士や公認心理師、言語聴覚士、作業療法士などの専門職が支援に関わることもあります。
学校なら発達障害について学んだ教員が行うこともあるでしょう。
また、市販の教材もあるので保護者の方が家庭で実施することも可能です。
専門家によるSSTを受けたい場合は、お住まいの自治体の福祉課などに相談すると情報が得られやすいでしょう。
子どもの対人関係の相談先
今回は子どもの対人関係の悩みに効果的なSSTの紹介をしました。
子どもに実施するSSTは、遊びやゲームなどを通して、楽しく学習することを大切にしています。
また、年齢があがるにつれて楽しさ以外にも「ワークへ取り組む姿勢」「友達と協力する意識」なども大事にしています。
ただし、SSTはどこでも受けられるわけではありません。
Gifted Gazeでは、小学生の子育て相談のプロである医師や心理士がオンラインで相談を承っています。
子どもの対人関係にお悩みの保護者様は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。
参考文献
NPOフトゥーロ LD発達相談センターかながわ 2010 あたまと心で考えようSST(ソーシャルスキルトレーニング)ワークシート―自己認知・コミュニケーションスキル編 かもがわ出版