「放課後等デイサービス」は、厚生労働省によれば、2021年時点で全国15,000カ所以上あるとされ、年々増加傾向にあります。
アクセスのいい場所だけで考えると、いくつもの候補がある場合もあり、どのように選べばいいか分からないですよね。
そこで今回は、元放課後等デイサービス職員である臨床心理士・公認心理師の筆者が、放放課後等デイサービスの選び方をご紹介します。

執筆:いけや さき
公認心理師・臨床心理士
精神科病院、療育施設、心療内科・児童精神科クリニックなど主に医療と福祉領域にて心理士として従事。
放課後等デイサービス(「放デイ」)とは
発達障害など、発達に偏りのある小学生〜高校生(18歳)までの子どもに対し、日常生活の支援や学習指導、交流の場などを提供する施設です。
「放課後」と名称の通り、基本的には学校帰りに行く場ですが、休日や祝日に開室しているところや日中に開放している施設・事業所もあります。
放課後等デイサービスの役割・内容
放課後等デイサービスは、事業所・施設によってプログラムが異なることをご存知でしょうか。
また、運営(社会福祉法人・NPO・株式会社など)によって雰囲気が違います。
まずは基本的な放課後等デイサービスの役割と詳しい支援内容を紹介します。
施設の役割
厚生労働省の「放課後等デイサービスガイドライン」によると、放課後等デイサービスの役割は以下の3つです。
1.子どもの最善の利益の保障
2.共生社会の実現に向けた後方支援
3.保護者支援
放課後等デイサービスは、子どもたちの生活能力向上のために必要な訓練や交流の場を提供する場所。
学校や家庭と異なる場所での体験を通し、子ども一人ひとりに応じた発達支援を行います。
また、専門的な知識や経験に基づいて学童や児童館などをバックアップしていく「後方支援」も放課後等デイサービスの役割の1つ。
そして、保護者に対する子育ての悩み相談やペアレントトレーニングなどを活用した支援なども放課後等デイサービスの役割として期待されています。
対象者
放課後等デイサービスは、小学生から高校生の子どもが対象ですが、誰でも利用できるわけではありません。
発達障害などの診断書の有無、療育手帳などの取得が必要になることも多く、その基準は自治体によって少々異なります。
厚生労働省の基準は「就学」が条件。
つまり、どの自治体でも中卒で高校に進学していない子は、診断書があっても放課後等デイサービスは利用できないということです。
なお、在籍しているけど不登校状態という子どもは、他の基準を満たしていれば放課後等デイサービスの利用が可能となります。
支援内容
放課後等デイサービスの役割を踏まえ、以下のような支援が行われています。
・自立した日常生活のための訓練:学習支援や宿題のサポート、金銭管理やコミュニケーションスキルの訓練など
・創作活動や余暇活動:アートなどの創作や工作、ゲーム、運動など
・地域交流やイベント:外出(施設見学など)やバザー・お祭りの開催、地域行事に参加など
主に長期休暇や土日に実施されます。
ただし、放課後等デイサービスごとに細かな内容は異なります。
放課後等デイサービスの種類
放課後等デイサービスは、全ての施設が同じ形式ではありません。
ここでは、運営の違いとタイプの違いに分けて紹介します。
運営の違い
主な運営先は「社会福祉法人」「株式会社」「NPO法人」の3つです。
規模的には株式会社と社会福祉法人が比較的大きいところが多いと考えられますが、選ぶ際は子どものためになる支援内容かどうかを見てあげてください。
プログラムのタイプの違い
次に、プログラム・支援内容のタイプの違いです。
これまでは主に「療育」「学童」「特化型」という分類がされていました。
しかし、2024年度の法改正により「総合支援型」と「特定プログラム特化型」の2種類に変わるなど、今まで放課後等デイサービスだった事業所がそうではなくなっていく可能性も指摘されています。
今回は、2024年6月現在にある3つのタイプを紹介します。
療育タイプ
一人ひとりの発達段階・特性に合わせた支援を提供するタイプ。
“個別療育”がメインの施設が多いです。
もちろん集団療育も必要ですが、一人ひとりの特性が未就学児の頃以上に出始める時期。
療育タイプには主に機能訓練担当職員と呼ばれる職員が配置されています。
学童タイプ
居場所提供を主とし、自由時間が多いタイプ。
療育プログラムを入れている施設もありますが、「発達障害・知的障害の子のための学童」という感じの雰囲気である事業所が多いようです。
特化・習い事タイプ
運動や音楽、絵画などに特化したプログラムがあるタイプ。
ただし、このタイプが法改正後の「特定プログラム特化型」に当てはまるわけではありません。
2024年6月現在は、運動メインの“運動療育”と呼ばれる事業所が多い印象を受けます。
放課後等デイサービスの選び方:7つのポイント
最後に、放課後等デイサービスの選び方を紹介します。
筆者が勤めていた放課後等デイサービスは、「特性に合わせた完全個別療育」「学習支援メインの小集団療育」「学童タイプ」の3施設でした。
放課後等デイサービスは年々増加傾向にあるため、選ぶ際には、以下で紹介するポイントを必ずチェックするようにしましょう。
空き状況の確認も重要ですが、ポイント1、2をある程度明確にしてから探すことをおすすめします。
ポイント1:通う目的を明確にする
まずは利用目的を明確にします。
何のために子どもを放課後等デイサービスに通わせるのか、子どもはどんな支援や居場所を必要としているのか整理していきましょう。
望ましい選び方の例
C美ちゃん(小学校高学年)
・お絵描きや工作が好き、勉強は好きだしそこまで困っていない
・同世代や大人と話すのが得意ではなく、緊張しやすい
・発達の凸凹が見られる
選んだ施設:心理士または言語聴覚士(機能訓練指導員※)がいて、余暇活動なども充実している施設
※機能訓練担当職員とは、理学療法士や言語聴覚士、作業療法士、臨床心理士・公認心理師などの資格保有者を指します。
ポイント2:アクセスや送迎の有無
次にアクセスや送迎の有無をチェックしておきましょう。
筆者が働いていた施設は以下のような感じでした。
・特性に合わせた完全個別療育:送迎なし。親など療育者が行うor子ども本人が自力で通う
・学習支援メインの小集団療育/学童タイプ:送迎あり。送迎範囲外の人は到着時間などの連絡を入れて自分で通う
放課後等デイサービスの場合は、送迎車を使う子もいれば年齢が上がるにつれて自力で来る子もいるので、アクセスのチェックも合わせて行うことをおすすめします。
ポイント3:支援内容
タイプやプログラム内容から、お子さんと一緒に考えましょう。
保護者のみの希望で決めてしまうと、障がいのある子どもにとって負担となる場合が考えられるからです。
実際に見学して支援内容を見たり、体験したりすると、子どももイメージがしやすいでしょう。
ポイント4:スタッフ(先生)の専門性
お子さんの支援にとって、必要な職員がいるかも選び方のポイントです。
放課後等デイサービスの人員(スタッフ)配置基準は以下となっています。
一般的な放課後等デイサービス(重心型※は除く)
・管理者:1名以上必須(兼任可)
・児童発達支援管理責任者:1名以上必須(常勤)
・児童指導員or保育士:利用人数10名で2名以上
※重心型:重症心身障害児特化型
必要に応じて配置される専門職員
・機能訓練担当職員:機能訓練を行う場合
・看護職員や嘱託医:重心型のみ必須
ポイント5:施設の規模や雰囲気
子どもに合う雰囲気か、スタッフの対応や施設の清潔感、施設の大きさなども重要。
開室している時間に見学できそうであれば、通っている子どもの様子も見ておきましょう。
ポイント6:地域や学校との連携
外出やイベント参加希望や学校との連携を望む場合は、どのくらいの頻度で行われているか確認しましょう。
また、学校と連携はお手紙なのか、会議などで会って話してくれるのかなども確認ポイント。
なぜ連携してほしいのか理由も整理しておくと、連携をお願いしやすいです。
ポイント7:週どのくらい通えるか
事業所・施設によって定員オーバーな曜日があるなど、限られた人数しか受け入れていないことも。
また、事業所によっては通う日数があらかじめ決まっている場合もあるので、子どもに負担のない範囲で通う日数を考えてから確認しましょう。
ほかにも長期休暇中に朝から開室している事業所もあれば、いつも通り放課後からスタートする事業所もあります。
長期休暇中の開室時間も確認しておくといいでしょう。
放課後等デイサービスは“子どもの視点”も大切に選びましょう
子どもにとって、家でも学校でもない新しい居場所となる放課後等デイサービス。
居場所でもありますが、子どもの心と体と社会性などの成長にも大きく関わります。
一方で、保護者支援の手が足りていない事業所が多いのも現状です。
Gifted Gazeの専門家相談では、放課後等デイサービスという選択肢も含め、お子さんの状況に合わせてどのような環境を用意すべきか、プロの心理士が相談に乗っております。ぜひご活用ください。

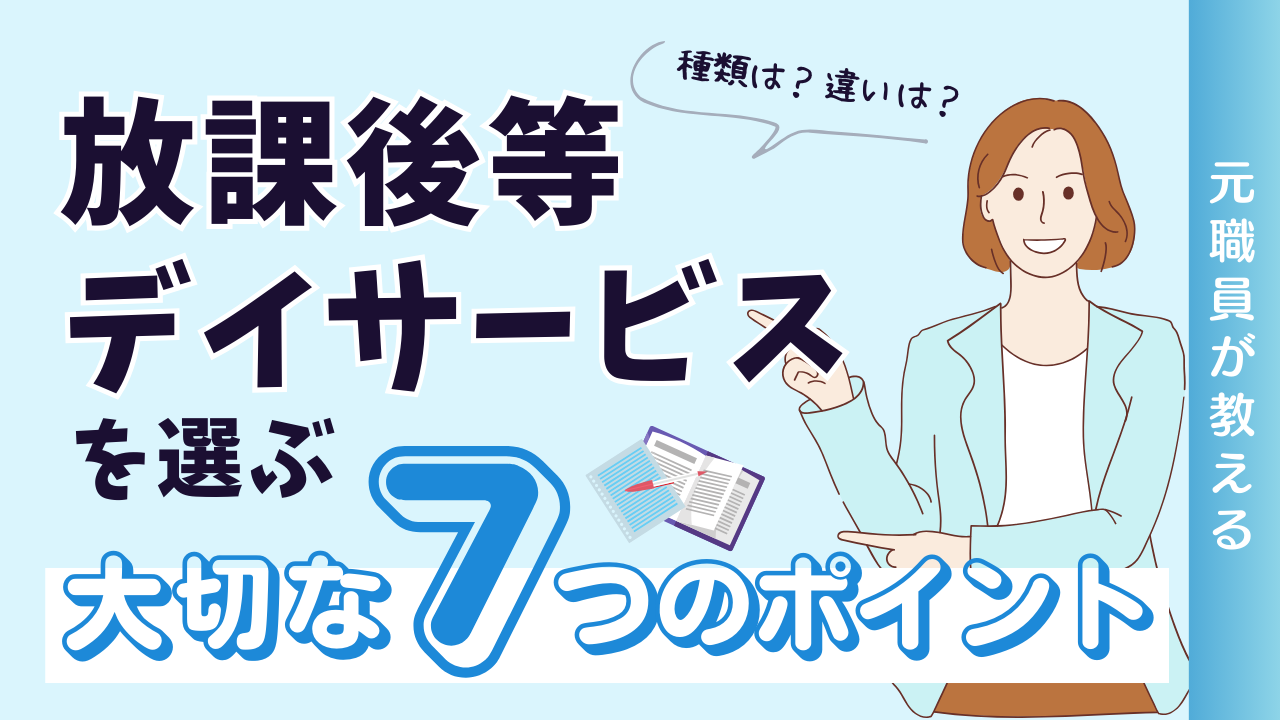



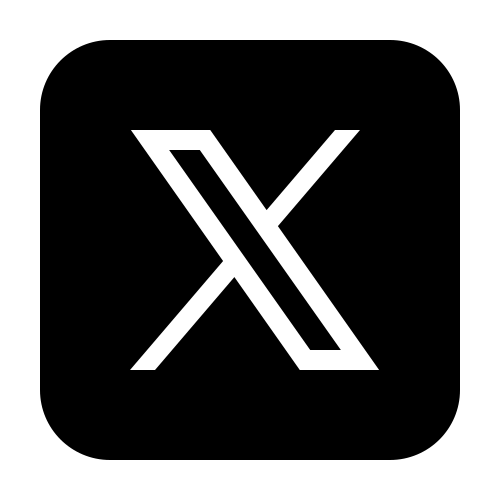

を調べる方法-知能テストで測定できることやギフテッドと成績の関係も解説-2-1024x536.png)


