子どもたちの才能を観察し、引き出すために有用とされているのが「STEM教育」と「STEAM教育」です。
近年になってこの言葉を聞くことが増えた人も多いと思います。
STEM教育とSTEAM教育は、各領域を統合的に学ぶことで、子どもたちの才能を引き出し、好奇心や問題解決能力を促進するアプローチです。
伝統的な日本の知識偏重の教育方法とは異なり、STEM教育やSTEAM分野を用いた分野横断的な学びが、現実社会の問題に対応するための、貴重な生きた学びの機会となるのです。
特に現状は、AIなどのテクノロジーの台頭もあり、一層ICT教育が注目され、STEM教育やSTEAM分野を学ぶ重要性も増しています。
この記事では、STEM教育とSTEAM教育の違いと重要性、具体的なSTEM教育やSTEAM分野の機会についても解説します。
STEM教育とSTEAM教育とは
「STEAM」(スティーム)とは、それぞれの分野の頭文字で、科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術(Arts)、数学(Mathematics)の5分野です。
これまでのSTEM(ステム)教育に加え、感性や創造性に関わる芸術(Art)分野を取り入れることで、より多様な視点や柔軟な思考を育てることを目的としています。
この教育アプローチは、暗記型・一方向の知識伝達ではなく、探究する力、自分で考える力、表現する力を重視し、現代社会に求められる”21世紀型スキル”の育成にもつながります。
以下では、STEAMを構成する各領域の役割や目的について解説します。
S:科学(Science)
自然現象や因果関係への気づき、観察・仮説・検証の体験など科学的リテラシーを高め、探究的な学び(inquiry-based learning)を促すことを目的とします。
自然現象や身近な「不思議」に目を向け、「なぜ?どうして?」を問い、観察や実験を通して答えを探す経験が中心です。
因果関係を考える力や、事象の背後にある原理を理解する態度を育みます。
T:技術(Technology)
プログラミングなどICTや道具を目的に応じて使いこなすスキルの育成を目的とします。
ICT(タブレット・PC等)や、デジタル機器を使って「調べる」「つくる」「表す」など、目的に応じて道具として使いこなす力を身につけます。
デジタル・リテラシー、メディア・リテラシーの基礎を育て、現代社会に不可欠な情報活用能力や倫理観、セキュリティ意識の素地を養います。
E:工学・ものづくり(Engineering)
「どうやったら上手くいくかな?」と考え、試行錯誤しながら構造や仕組みを工夫して何かを組み立てたり改良したりする力を養います。
ものづくりや構造・仕組みへの理解、試行錯誤力の育成を目的とします。
エンジニアリングは、デザイン思考やシステム思考を取り入れ、構造化された課題解決のプロセスを学びます。
論理的で創造的な問題解決につながるなど、アイデアを現実にすることができる重要なポイントです。
A:芸術(Art)
STEM教育から発展して追加された分野です。
自由な発想や表現、感性を大切にしながら、創造力や発想力を広げるといった目的の分野です。
音楽や美術だけでなく、演劇、身体表現、デザインなども含まれます。
創造的思考や感性に関連します。論理や数理に偏りがちな思考に、感性や表現の視点を統合する役割を担い、STEAM全体のつながりを生み出すとされています。
M:数学(Mathematics)
数や形、パターンなどを通して、「比べる」「順序を考える」「ルールを見つける」といった思考の土台をつくる分野です。
論理的思考や数量的推論力を育成し、他分野(特に科学・工学)と接続する土台になります。
数理モデルの理解や構造的思考を通じて、抽象的な課題に対する認識力を高めることになります。
STEAMの各分野はそれぞれ独立しているように見えて、実は互いに深くつながっています。
だからこそ、一つの教科だけでなく、複数の視点を重ねながら学ぶことが大切です。
STEM教育とSTEAM教育の違い
日本では、従来の学習指導要領に基づく教育から、より創造性を重視する教育へのシフトが少しずつですが進んでいます。
2020年度の新学習指導要領の全面実施により、プログラミング教育の必修化など、STEM教育の要素が強化されました。
近年では、「STEM教育」をこれを発展させ「STEAM教育」というものが学びにおいて重要な役割を担っているとされています。
「STEAM教育」とは、STEM教育にアート(Arts)の要素を加えたもので、科学、技術、工学、芸術、数学の分野を統合的に学ぶアプローチです。
STEM教育も、先に説明した通り創造性を育むことができるのですが、STEM教育が科学技術の知識と技能に重点を置いているのに対し、STEAM教育はそれに加えて創造性やイノベーション、デザイン思考をさらに重視します。
芸術を通じて、科学や数学をより深く理解し、創造性やイノベーション能力をさらに高めることを目指しているのです。
アートを組み込むことで、広い視野を持ち、科学技術に対する新たな視点を獲得し、多角的な思考が促されるという考え方が強調されています。
例えば、分かりやすい例だと、工学と美術を組み合わせたプロジェクトで、技術的なスキルを活用しつつ、美的感覚を養い、独自の製品やアートワークを創り出すプロセスを通じて、両分野の統合的な理解を深めることができます。
このように、デザイン思考や創造的問題解決能力を育てます。
文部科学省は、「STEAM教育」の推進を図り、学校でのアート教育と科学技術教育の融合に向けた取り組みも進めています。
創造力や問題解決能力を養うためのプログラムの導入や地域社会と連携したプロジェクトや産業界との協力による教育プログラムも増えていきているように感じます。
科学技術の知識の習得だけでなく、実社会や他の分野にも広げられる創造性や表現力を養う機会を得ることを重視した動きと言えます。
STEM教育とSTEAM教育の効果
まず、STEM教育やSTEAM教育を行うことで具体的にどのような学びの効果があるのでしょうか。
具体的なプロジェクトでいうと、例えば、水質汚染など環境問題を解決するためにはどのような方法があるのか、調べるような活動です。
まず住んでいる近所の水路の水がどれほど汚染されているか把握するという科学的な調査を共同または分担して行い、測定した数値やデータを比較し、議論し、デジタルツールなどの技術を使用してみんなで解決策を設計するという活動などです。
このような活動によって期待できる効果は、以下のようなものが挙げられます。
STEM教育やSTEAM教育の特徴とその効果がわかると思います。
- グループワークや体験学習が多いため、他者と協同し異なる意見や見方に触れ合い多様性が育まれる
- 決まったやり方や結論にこだわらず新しいものを探求するため創造力が育まれる
- 自分たちがもともと得意とすることや夢中になれることを取り入れるため、知的好奇心がさらに刺激され学びが広がっていく(科学的探究や数学的思考の能力が深まる)
- 他者のアイデアや考え方も尊重しながら、協力やコミュニケーションのスキルを育む効果もある
このような活動の中で、子どもたちは、大人が想像する以上の成果を見せてくれることさえあります。
STEM教育やSTEAM教育は、ギフテッドと呼ばれるような特異な分野に突出した才能がある子どもにとっても有用です。
ギフテッド・チルドレンは、科学や数学に対して、非常に強い興味や高度な理解を示すことが多いためです。
特に、科学の分野で優れた才能があるギフテッド・チルドレンは、以下の特性があると言われています。
1. 科学的好奇心が高い
2. 明確な想像力を持っている
3. アイデアを表現する際に数字や図を使用する
4. 関連する質問をすることで好奇心を示す
5. 既存の答えに依存しない
6. リーダーシップがある
例えば、高度な数学的問題を解決したり、科学実験を通じて新しい理論を検証する活動は、ギフテッド・チルドレンが自分の才能に挑戦し、それをさらに発展させる絶好の機会なのです。
STEM教育やSTEAM教育を活用して、ギフテッド・チルドレンの高い知的好奇心と創造性を刺激することが重要です。
ギフテッドについては、こちらのページでいろんな視点から詳しく紹介しています。
STEM教育とSTEAM教育の重要性
STEM教育やSTEAM教育は世界で急速に成長しています。将来、多くの職業がこのSTEM分野での知識が必要とされているためです。
また、STEM教育やSTEAM教育は、実践を重視するため、実世界の問題を解決するためのアプローチを学ぶための有用な機会です。
子どもたちは自分の周りの世界をより深く理解し、将来、どのような分野に進んでも成功するための基礎を築くこともできます。
小さな子どもがキッチンで親と一緒に簡単な科学実験をしているシーンを想像してみてください。
たとえば、重曹と酢を使った火山の噴火実験。子どもに科学の基本的な原理を教えるだけでなく、なぜそのような反応が起きるのかを考えさせ、観察力と好奇心を刺激します。
学校や家庭でのプログラミングの授業があります。子どもたちは、コンピューターゲームやアプリを作る基本的なコードを学びます。プログラミングは、単にコードを書くだけでなく、問題を細分化し、段階的に解決する論理的な思考プロセスも必要とします。
子どもたちがクラスで橋やビルのモデルを作る工学プロジェクトに取り組むシーンを想像してください。物理学の原理を理解するだけでなく、どのようにして強くて安定した構造を作り出せるかを考えます。その中でチームワークを学び、互いのアイデアを共有して最適な解決策を見つけ出します。
買い物をする際の割引計算や、料理のレシピの分量を調整することなど、数学は私たちの日常生活に密接に関連しています。子どもたちに数学の問題を実生活の状況に適用させることで、数学が抽象的な概念だけでなく、実用的なツールであることを理解させることができます。
このように、STEM教育やSTEAM教育のプロジェクトを通じて、新しいアイデアを生み出し、それが現実の世界とどう繋がるか、どのように活用できるかなどを考えることができます。
こうして創造性を刺激し、イノベーションの精神を育むわけです。
なお、「リベラルアーツ」(Liberal Arts:教養教育)ということばがありますが、STEAM教育とリベラルアーツには深いつながりがあります。
答えが一つでない課題に取り組む中で、考える力・判断力・対話力など、知の応用力を育てるような「人間としての総合的な力」の育成という点でとてもよく似ていると言えるでしょう。
補足:リベラルアーツ(教養教育)とは
もともと「自由人にふさわしい学問」という意味をもち、古代ギリシャ・ローマ時代にさかのぼる概念です。
当時の「自由人」とは、社会に参加し、責任をもって行動することが期待された市民のこと。
その市民が持つべき知性・思考力・倫理観を養うための、幅広く基礎的な学問がリベラルアーツでした。
現代では、「専門に偏らず、幅広い視点から物事を考える力を養う教育」として、多くの大学や教育機関で「教養教育」として位置づけられています。
STEM教育・STEAM分野の具体的な機会
家庭でできるSTEM教育とSTEAM教育
家庭でも、日常の中の「なぜ?」「やってみたい!」に寄り添いながら、小さなSTEAM体験を重ねることで、学びの芽を大きく育てていくことができます。
| S:科学 | 好奇心を大切にして一緒に「調べてみよう」 | コップに水を入れて数日間置き、水が減る様子を観察してみる。 →「水はどこにいったのかな?」と蒸発について考えるきっかけになる。 |
| T:技術 | 道具を「使うだけ」ではなく「しくみ」にも注目 | ソフトウェアツールやアプリケーションで簡単プログラミングにチャレンジしてみる。 →キャラクターを動かすブロック型プログラミングで論理的思考を育成。 |
| E:工学 | 作って→試して→直す、を一緒に楽しむ | 紙やストローで「荷物を支えられる橋」を設計してみる。 →構造の強さや耐久性を体験的に学べる。 |
| A:芸術 | 自由な発想や表現を「正解のない学び」として受け入れる | 落ち葉や小枝を使ってコラージュ作品を制作。自分の気持ちを表現してみる。 →観察力+創造力を融合させ、感情理解を深める。 |
| M:数学 | 暮らしの中で「数や形」に注目して遊びに取り入れる | いろんな種類のボールを転がして距離をはかり、平均距離を出す。(「平均ってなんだろう?」実験) →データの扱いと統計的な考え方を楽しく学べる。 |
STEM教育とSTEAM教育は「高品質の機会」が大切
自分自身の強みのある領域に挑戦的な課題を組み込むことは、自尊心と自己達成感を高めることができますが、さらに興味を高め好奇心をより促進するためには、さまざまなツールを提供することも重要です。
愛媛大学教育学部の隅田学教授は、学ぶ機会の提供に加え、さらなる探求への機会についての重要性も語っています。
単にすべての子供たちに「活動」へのアクセスを提供するだけでは十分ではありません。
むしろ、子供たち自身が収集した情報に基づく説明や、学んだことを関連する科学的な知識に適切につなげることによって、探求への橋を築く必要があります。
また、幼少期からすべての子供たちが科学に触れるための高品質な機会にアクセスできるようにする努力も必要です。
Kids Science Academy: Talent Development in STEM from the Early Childhood Years-Manabu Sumida
STEM分野で自分の強みを発見し、自尊心と自己達成感を高めるためには、実践的なプロジェクトや体験学習の機会が不可欠です。
愛媛大学のキッズアカデミアでは、子どもたちが自らの興味に基づき、独自の科学実験を計画し実施することで、科学的探究過程を深く理解し、同時に学びへの興味をさらに深めることができます。
活動について、以下10のガイドラインを掲げていますので参考にしてみてください。
- 子供の自発性と発見の感覚に焦点を当て、統合されたプロジェクトスタイルの活動を実施する。
- 子供の創造的な思考スキルを刺激する要素を含める。
- 馴染みやすく、手ごろな価格の素材を使用する。
- 科学用語を正確に使用する。
- 子供が簡単な測定機器やデバイスを使用する活動を含める。
- グループ活動と個々の活動の両方を含める。
- 他の分野や科目と統合しやすいように活動を設計する。
- 活動の知的側面だけでなく、子供の感情や感性にも焦点を当てる。
- 馴染みやすい、季節的、地元のテーマや素材を取り入れる。
- 家族やコミュニティとの連携を促進する。
Kids Science Academy: Talent Development in STEM from the Early Childhood Years-Manabu Sumida
プログラミングスクールやロボット教室、小中学生でも参加できる夏休みの研究室など民間企業が提供している機会も増えてきました。
STEM教育とSTEAM教育の今後
今の世の中は、単なる知識を身につけることだけでは、予測困難で不確実、複雑で曖昧な時代(「VUCAの時代」)を柔軟に生きていくことが難しいとされています。
この、変化のスピードが速い時代で、STEM教育やSTEAM教育は、子どもたちの将来の可能性を広げるためのより強力なツールとなっています。
子どもたちと一緒に、散歩中に植物や動物を観察し、なぜそのように生えているのか、どのように動いているのかを話したり、季節の変化や天気の変化について話し合い、それらが生物にどのように影響を与えるかを探ってみてください。
料理をするときに、温度変化や材料の混ぜ合わせによって食品がどのように変化するかを観察し、化学反応について話してみましょう。
YouTubeでは、科学実験や宇宙、動物についての興味深い動画がたくさんあります。
子どもたちが楽しむだけでなく、保護者の方もぜひ一緒に観てみてください。
子どもを特別なプロジェクトに参加させなくても、身の回りにもSTEM教育やSTEAM教育を実践できるツールがこんなにもあるのです。
子どもたちは、日常の中でも、大人が問いかけると驚くようなアイデアや見方を私たちに提示してくれるかもしれません。
参考文献
Kids Science Academy: Talent Development in STEM from the Early Childhood Years-Manabu Sumida

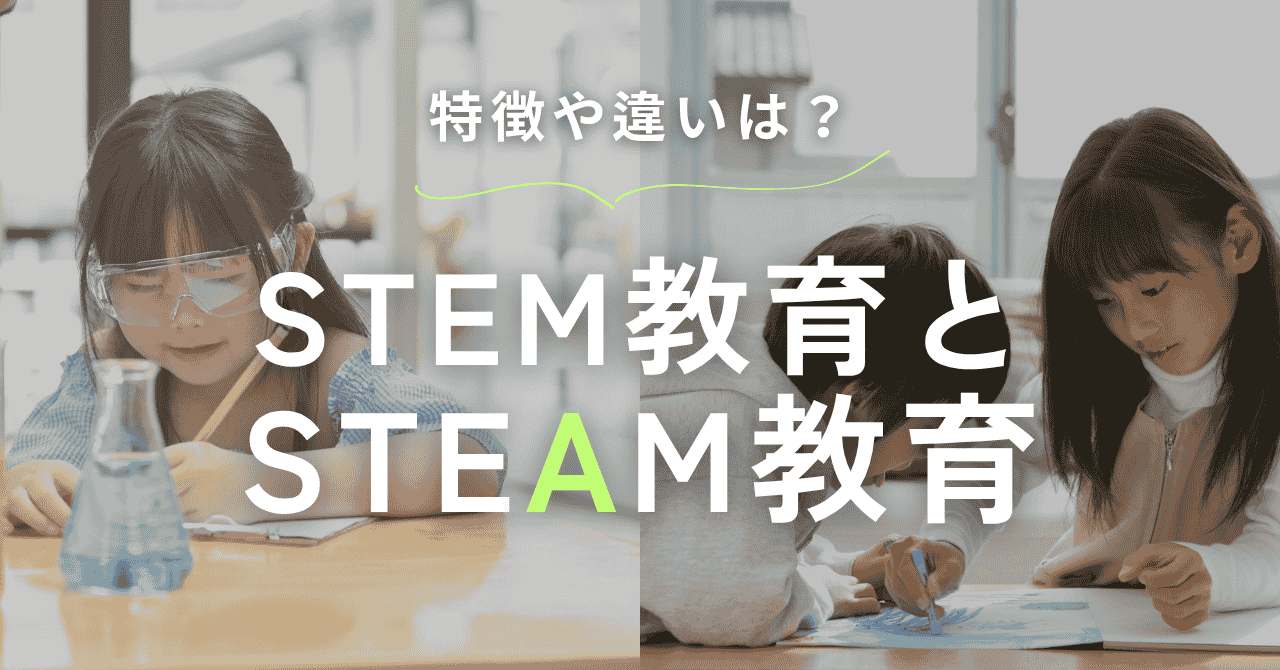



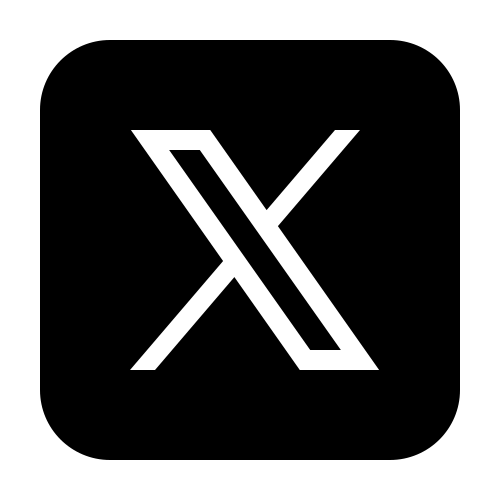

を調べる方法-知能テストで測定できることやギフテッドと成績の関係も解説-2-1024x536.png)


