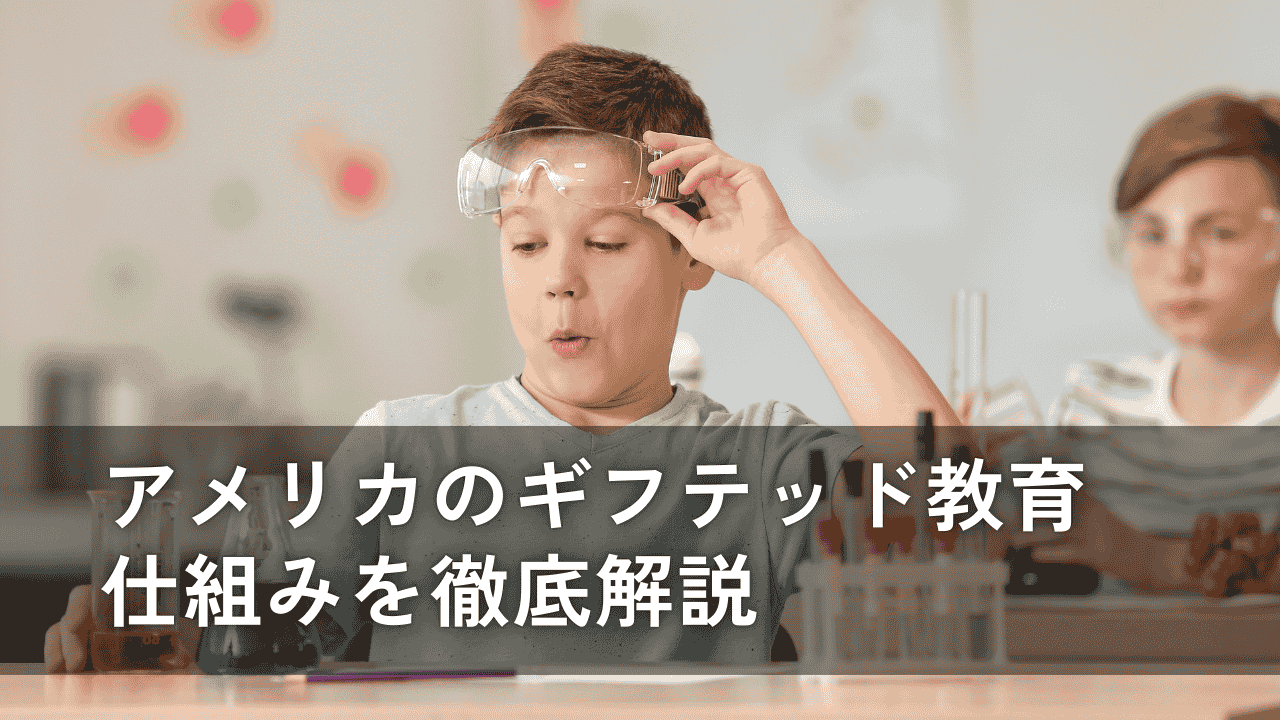現代の世界では技術革新がどんどん進み、それに伴って国同士の関係や地球環境を含めた世界のあり方は驚くほどのスピードで変化しています。
今の子どもたちが大人になる頃には、まだ見ぬ職業や新しい価値観が当たり前になっていたり、新たに生まれる社会課題に対処する必要も出てくることでしょう。
そのような未来を子どもたちがよりよく生きていくためにはどのような力を育てていけばいいのだろうか?という問いに世界の知恵を集めて取り組んでいるのが『Education2030』です。
今回はその概要と、時代背景やこれまでの教育プロジェクトとの関係について解説します。

執筆:山崎 日菜乃
公認心理師・臨床心理士
心理士としてメールカウンセリングに3年半従事し、家族関係の悩み、心身の不調、仕事の悩みなど、様々な困り事へのサポートを行う。アメリカ合衆国在住。
Future of Education and Skills 2030/2040とは
Future of Education and Skills 2030/2040(以下、Education2030)は、OECDが2015年に立ち上げた教育プロジェクトです。
近年、世界は目まぐるしく変化し、未来はますます不確実で予測困難なものとなっています。
当時の子どもたちが大人になる2030年に向けて、生徒たちが成長しよりよい未来を共有していくためにどのような力が必要か、また、その力を育成するためにはどうしたらよいかを検討し、各国で共通の理解を構築することを目的としてこのプロジェクトが始まりました。
現在、更なる未来を見据えて、Education2030は『Education2040』へと移行中です。
Education2030での問い
Education2030では、各国が以下の2つの問いに対する答えを見つけられるようサポートすることを目的としています。
そして、2019年と2025年にそれぞれ、生徒と教師が目指すべき方向性を示す枠組みが発表されました。
フェーズ1(2015~2018年)での問い
現代の生徒が成長して世界を切り拓いていくためには、どのような知識やスキル、態度及び価値観が必要か?
→生徒に必要な力や学習の指針をまとめた「ラーニングコンパス」が2019年に発表されました。
フェーズ2(2019年~)での問い
学校や授業の仕組みが、これらの知識やスキル、態度及び価値観を効果的に育成していくことができるようにするにはどうしたらよいか?
→教師に必要な力や教育のあり方をまとめた「ティーチングコンパス」が2025年に発表されました。
プロジェクトが生まれた背景
Education2030が生まれた背景として、世界の急激で本質的な変化があげられます。
現代はVUCA(不安定、不確実、複雑、曖昧)の時代とも言われるように、私たちは世界の様々な分野において前例のない変化に直面しています。
環境面
気候の変化や天然資源の枯渇が深刻な問題となっています。
また、パラダイムシフトにより人間を含めたより大きな生態系システムで環境が捉えられるようになり、人間が自然の一部として自然と共存していく必要性が重視されるようになりました。
さらに、自然は重要な資本の一つであると考えられるようになり、持続可能な開発や経済活動と環境保全を両立させる取り組み(Green Growth)に焦点があてられるようになってきています。
経済面
ソーシャルメディア、人工知能、ロボット工学など、技術革新が加速し、それに伴ってビジネスモデルも変化しています。
職場はよりフラットでオープンで柔軟になり、上下関係ではなくチームワークがより重視されるようになってきました。
また、ビジネスの目的として、利益の追求だけでなく、社会的価値の創造や社会問題の解決にも焦点があてられるようになりました。
その一方で、デジタル化やソーシャルメディアを利用したフェイクニュースなどの問題も出てきており、サイバーセキュリティや個人のプライバシーをいかに守るかが課題となっています。
社会面
21世紀を特徴付ける要素として、グローバルなコミュニケーションやソーシャルメディアによる国家間の相互依存や権力の分散化の加速、ナショナリズムの台頭、テロ事件の増加が挙げられています。
また、移民が増え、都市化が進み、社会的文化的多様化が国やコミュニティの在り方に影響を与えています。
さらに、世界の多くの地域では生活水準や機会の格差が拡がっており、政府に対する信頼が失われてきています。
新しい技術や変革は便利さや新たな機会を生むものであると同時に、活用の仕方によっては格差や社会的な不安定さ、資源の枯渇を加速させてしまう恐れもあるでしょう。
今ある、また、これから生まれる社会課題を解決できるのかどうかには教育の在り方が大きく関わっています。
このような社会を生き抜くため、また、よりよい未来を作っていくためには、変化する社会に対応する、という姿勢を育てる教育から、自ら変革を起こす、という姿勢を育てる教育への転換が必要とされています。
Education2030に影響を与えた2つのプロジェクト
DeSeCoプロジェクト(1997年~2003年)
Education2030の前身となるプロジェクトとして、OECDの「Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations」(以下、DeSeCoプロジェクト)がありました。
DeSeCoプロジェクトでは、すべての個人において、幅広い文脈で有益で重要な能力である「キーコンピテンシー」の選定が行われました。
コンピテンシーとは「単なる知識や技能ではなく、人が特定の状況の中で技能や態度を含む心理社会的な資源を引き出し、動員して、より複雑な需要に応じる能力」のことです。
キーコンピテンシーの中核には、思慮深さ(reflectiveness)が位置付けられ、深く考え、多面的な判断を行うこと、自分の行為に責任を持つことの重要性が強調されました。
キーコンピテンシーは以下の3つのカテゴリーに分類され、それぞれがバラバラに働くのではなく相互に影響を与え合い、文脈に依存しながら発揮されるものとされました。
相互作用的にツールを使う力(Using Tools Interactively)
言語や情報、知識といった社会文化的ツール、情報技術などの物理的ツールを使いこなせるようになること。
それらを単に使用できるというだけでなく、周囲との能動的な対話においてツールを活用できたり、目的に合わせて使えるくらい十分に理解すること。
異質な集団において交流する力(Interacting in Heterogeneous Groups)
多様化する社会において、様々な背景を持つ人たちと良好な関係を築けること。
具体的には、相手の立場に立って考えたり、自分や他者の感情を適切に解釈したり、グループで力を合わせたりできること。
また、衝突が生じた際に他者の利益とニーズを理解し、双方が利益を得られる解決策を考え解決できること。
自律的に行動する力(Acting Autonomously)
社会において自分が果たしている役割、果たしたい役割を認識し、社会的文脈に自分の生活を位置付けて自分の生活を管理する責任を負うこと。
自分の価値観や行動を振り返り、アイデンティティを育んで、人生に意味と目的を見つけること。
DeSeCoプロジェクトにより、教育課程において重視されるポイントが「何を学ぶか」から「何ができるようになるか」へと転換されました。
しかしながら、目標が抽象的、哲学的すぎて実行に移しにくかったこと、また、プロジェクトメンバーのほとんどがヨーロッパや英語圏中心で文化的なバランスが悪かったことなどの問題点もありました。
そうした問題点の解消、また、さらなる社会の変化に合わせてコンピテンシーを再定義する必要性もあり、Education2030プロジェクトが開始されました。
「OECD東北スクール」プロジェクト(2011年~2014年)
OECD東北スクールは、OECDや文部科学省の協力を得て、福島大学が主催した復興教育プロジェクトです。
このプロジェクトは、東日本大震災の被災地である福島、宮城、岩手から集められた中学生高校生約100人を対象とし、「国際的な視野を備えた、東日本大震災からの復興の担い手を育てる」ことを目的として行われました。
東北スクールでは、DeSeCoプロジェクトで選定されたキーコンピテンシーと創造的な復興に必要な力は重なっているということと、キーコンピテンシーを育むにはプロジェクト学習が適しているということから、エビデンスに基づいたプロジェクト学習が導入されました。
子どもたちに与えられたプロジェクトは、2年半の活動や学びを通して2014年にフランスパリで「東北日本の魅力を世界にアピールする国際イベントを企画実行する」というものでした。
プロジェクト学習の効果を検証するために、キーコンピテンシーをより具体的にし評価しやすくした独自の評価尺度に基づいて生徒の能力が評価されました。
その結果、好奇心、発想力、チームワーク力、マネジメント力、課題解決力、巻込み力、発信力、地域力、グローバル力という9つの全てのコンピテンシーにおいて向上が確認されました。
それだけでなく、プロジェクトへの参加を通して、自分の進路や将来の夢、ロールモデルを見つけたり、レジリエンスが高まるなど、コンピテンシーに留まらない、人格形成や人生への影響も見られました。
また、学習方法については「学年や学校の壁を越えて他地域、異世代、学校外と接触する」という学習方法が特に生徒のコンピテンシー向上に繋がったという知見も得られました。
東北スクールでのプロジェクト学習の実践によるこのような成果や知見はEducation 2030の議論にも活かされることとなりました。
おわりに
今回は、Education2030の概要と、プロジェクトが生まれた社会的教育的な背景についてご紹介しました。
このように、社会のあり方と教育のあり方とは密接に関わり合っており、これまでも時代に応じて生徒に求められる力や教育のあり方は様々に変化してきました。
次回からはEducation2030の具体的な内容に焦点を当て、プロジェクトの目指すところ、未来をよりよく生きていくためにどのような力が必要とされるのかなどについて解説していきます。
参考
松尾知明(2017)21世紀に求められるコンピテンシーと国内外の教育課程改革 国立教育政策研究所紀要146, 9-22.
OECD(2005)Definition and Selection of Key Competencies – Executive Summary
OECD(2018) The Future of Education and Skills Education 2030.
OECD(2019)OECD Future of Education and Skills 2030 project background
OECD東北スクール OECD Tohoku School
OECD東北スクールが残したもの 日本文教出版
白井俊諏訪哲郎森朋子(2021)OECDラーニングコンパス2030について―文部科学省 白井教育制度改革室長に聞く― 日本環境教育学会31(3), 3-9.