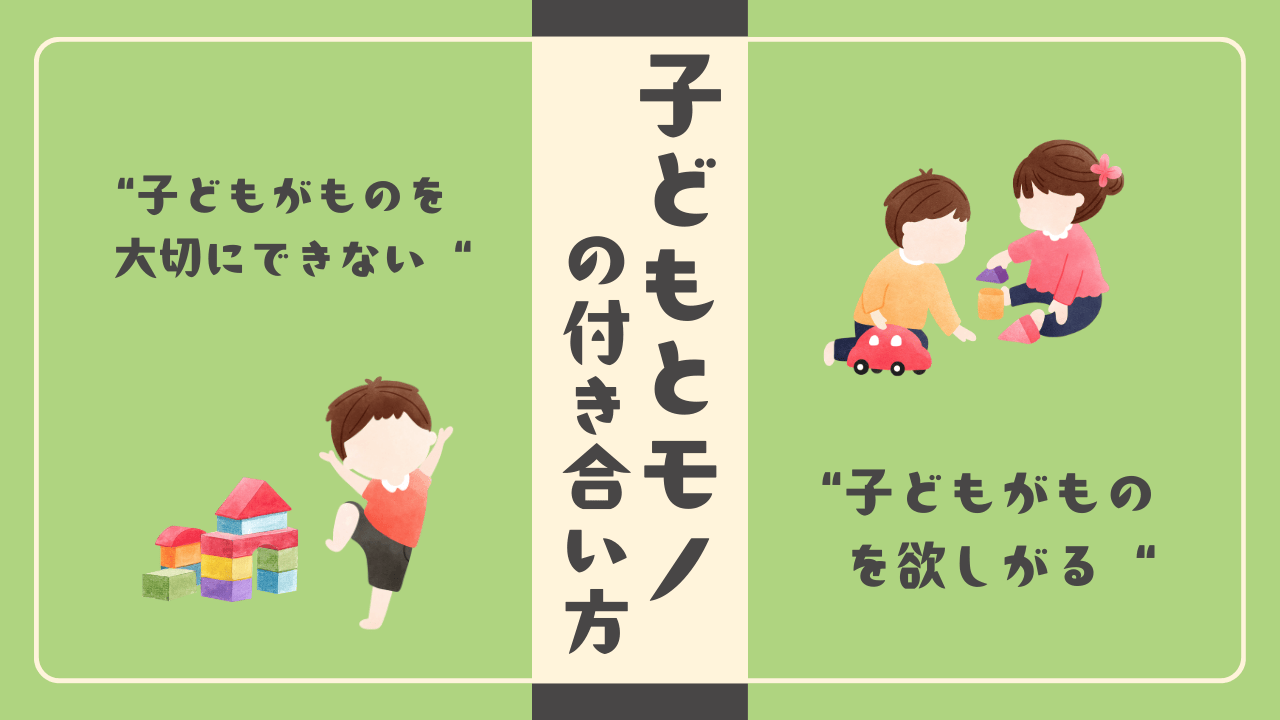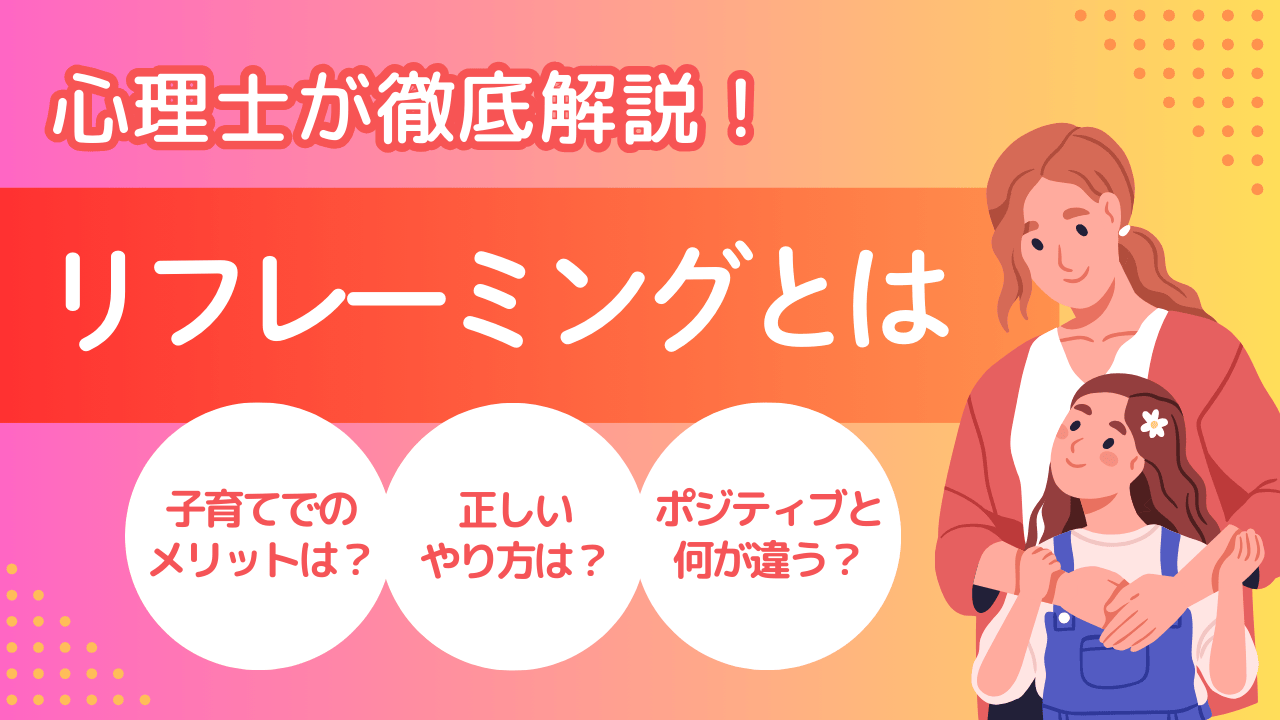子どもが物を「欲しがる」「大切にできない」「片づけができない」「独占してトラブルになる」など、子どもが物とどう付き合っていくのかは意外に多い悩みですよね。
子どもが物を大切にしないのには、年齢や発達段階、心のサインなど、さまざまな理由があります。
この記事では、「子どもと物との付き合い方」について心理士の視点からその背景をわかりやすく解説し、家庭でできる具体的な対処法をご紹介します。
今日からできる声かけや環境づくりのヒントが満載なのでぜひ最後まで読んでみてください。

執筆:杉野 亮介
公認心理師・臨床心理士
教育支援センター、スクールカウンセラーとして不登校支援などに携わり、児童福祉施設で心理士として20年間以上従事。発達障害児の心理的支援などを行う。
子どもと物との付き合い方についてのQ&A
※ この記事で紹介させていただく質問に関しては、どなたか特定の方からいただいたものではありません。
子どもの物欲が激しいです。どこまで我慢させるべき?
質問:子どもの物求が強くて困っています。子どもの要求にどこまで応えれば良いですか?
専門家の回答:
基本的には子どもが求めるものを可能な範囲(親がそれほど負担だと思わない範囲)で満たしていくことが良いです。
もちろん各家庭の経済状況にもよるのですが、子どもが我慢をできるようになるには、我慢を学ぶのではなく、まずは満たされる必要があります。
子どもがずっと我慢を強いられて育っていくと、物や人との関わりを求める欲求がとても強くなり、どれだけ与えられてもなかなか満たされず、「もっとちょうだい」「もっと関わって」と我慢することが難しくなります。
満たされないままで大人になってしまうと、自分で自分をコントロールすることができずに買い物依存症になってしまったり、異性に過度に依存的になってしまう場合もあります。
子ども達の欲求が小さいうちに(スーパーのお菓子売り場でお菓子が欲しいという、ガチャガチャをしたいという等)、できる限りで欲求にこたえてあげて、「満たされた」という体験を子どもの中に積み重ねていくことが大切です。
子どもがものを欲しがった時の具体的な対処法3選
1. きちんと言葉で何が欲しいのかを伝えてもらう
欲しそうにしているとか、ぐずっているけれど何が欲しいのかは分からない、という状態は良くありません。
きちんと言葉で言えば聞いてもらえる、あるいは、答えてもらえるという体験が必要です。
子どもが自分の欲求を言語化してくれば、今度は大人が思っていることを言語化して伝える必要があります。
「それなら、1つ買って良いよ」なのか、「それは高いから、今日は買えない。こっちのなら、1つ買って良いよ」なのか、あるいは「それは誕生日に買うことにしたら?」なのか、は状況によりますが、とにかく大人も素直に言葉にして伝えてあげることが必要です。
2. 見通しを持たせる
「買うわけないでしょ」とか「自分で考えたら分かるでしょ」など言われても子どもは分かりません。
今は買ってもらえないけれど、自分がどうすれば、いつ買ってもらえるのかという見通しを持つことで、我慢できる子もいます。
3. 子どもの選択を褒める
そして、子どもが「これ欲しい」とか「ガチャガチャ1回する」となったら、自分で選択できたことをしっかりと褒めてあげましょう。
そして、ここが大切なのですが「1つに決めて偉いね」と褒めることです。
2つも3つも欲しがるのではなく、1つ選んで、残りの物は我慢したというところに焦点を当てましょう。
こうすることで、この体験を、物を要求して満たしたという体験に加えて、他の物を我慢することができたという体験にすることができます。
こういう体験を繰り返すことで、子どもの中に、自分は我慢ができる子どもだというセルフイメージを作っていくことができます。
ただ、どれだけ要求に応えても、次々に物を欲しがったり飢餓感が強い子もいます。
何かは欲しいという思いが強く、あれこれ欲しがるけれど、本当はその物自体を欲しいわけではない場合も多いです。
そのため、提供された物には興味を示さないということもあります。
「こういう場合には、”~が欲しい”と言えば大人が反応してくれる」という体験を積み重ねてしまっていることが多いので、物を与えるということ以外で、その子との接点を持って行くことが重要です。
例えば、一緒に外に遊びに行く、一緒にお風呂に入る、一緒に布団に入る等、個別に関わる時間を持つことです。
子育て相談の場面では、「この子が欲しいというものは全て買い与えているのに、全く言うことを聞かない」というような相談を受けることも少なくありません。
ケースにもよりますが、子ども側から話を聞くと、何かが満たされない感じがずっとしていて、それを満たすためには刺激を求めてしまうということで、反社会的な行動に進んでしまう子どもが多いように思います。
もちろん、子どもは物を欲しいのですが、それだけではないようです。「あれが欲しい」「はい」と買って渡されてほったらかしとなってしまうと、子どもは満たされません。
「あれが欲しい」と言えば、「どうして欲しいの?」と聞いて欲しいし、「あれ、良いよね」と共感してほしい気持ちもあります。一緒に買いに行って、自分でレジに持って行く時の子どもはみんな嬉しそうな顔をしていますし、買ってもらった後に「買ってくれてありがとう」と言える子どもはそんなに心配は要らないでしょう。
買った後に「良いのが買えて良かったね」と言ってもらえたら子どもは嬉しいですし、家に帰ってからも「お菓子、おいしかった?」とか「使ってみてどうだった?」と聞いて欲しいと思います。
物を介して子どもと大人がつながることは悪いことではありませんが、物だけのやりとりをどれだけしても、子どもと大人の心はつながらないことを忘れてはいけません。
どうしたら子どもがものを大切にできるようになるの?
質問:うちの子はものを大切にできません。買ってあげたおもちゃもすぐ壊れます。本人はまた別の物を買えば良いと思っているみたいです。
専門家の回答:
まずは、「物を大切にする」ということは具体的にどういう意味なのか、ということを、大人が整理しておく必要があります。
大人が言っている「物を大切にする」と、子どもが思っている「物を大切にする」とでは、理解がずれている可能性があるからです。
そして、子どもとコミュニケーションをとる上では理解がずれてしまわないように抽象的な表現は避けましょう。
例えば、あなたが友人から「これ、大切にしてね」とペンをもらったとします。あなたにとって、このペンを「大切にする」というのは、具体的にどういう行動でしょうか?
大人が「使わずにとっておくことが、大切にするということだ」と思っていて、子どもは「毎日使うことが大切にすることだ」と理解している可能性もありますよね。
そうすると、子どもが毎日ペンを使っているのを見て、大人は「もっと大切にしなさい」と叱るかもしれません。
ここで大切なことは、”理解がずれることがある”ということを大人が自覚しておくことです。
まず初めに、大人が「物を大切にする」ということは、どういうことなのかを具体的に子どもに話してあげましょう。
出したものは片付ける、置くときは音が立たないように優しく置く、壊さないように気をつけるなど、大人が思っていることを具体的に伝えるのです。
「子どもはどうせすぐに壊すから、安い玩具しか与えていません」という親御さんもいますが、その「安い玩具」を子どもが本当に欲しいものであれば、それでもかまわないのです。
本当は別の物が欲しいのに、「安いから」「すぐに壊せるから」という理由で、別の物で我慢させるのは良くないです。
たいして欲しくない物を渡されて「大切にしなさい」と言われても、子どもとしては納得できないですし、大切にしたいという気持ちが湧いてきませんよね。
自分が欲しい物を手にした時に、子どもは「これを壊したくない」「なくしたくない」と思い、自然と物を大切にするということを学ぶことができます。
もちろん「安いから」ダメというわけではないのですが、壊れやすい玩具は安全面から考えても良くないのです。
子どもとしては大切に使っていたつもりなのに、玩具自体の耐久性が低いがために壊れてしまうようなことがあれば、子どもの喪失感は大きくなってしまうからです。
そこで「もっと大切に使わない」と叱られてしまえば、子どもも何が「大切に使う」なのかが分からなくなってしまいますよね。
「この玩具、ずっと使っていてすごいね」「大切に使ってるもんね」と褒めてもらえるような体験をすることで、子どもは、もっと大切に使おうと思えるのです。
おわりに
何事に対しても「大切にする」「優しくする」ことができるようになるためには、子ども自身が「大切に」されたり、「優しく」してもらうことが何よりも必要です。
私が臨床現場で出会う子どもたちの中には、「大切にする」という言葉の意味が分からない子どもがいます。
「自分が大切にされてこなかったから、大切にするの意味が分からない」と明確に言語化してくれた子どももいました。
もしも、物を大切にできない子どもがいたら、大人はこの子を大切にできているのかという視点からも、考えてあげてみてもらえたらと思います。