ASD・ADHDの子どもは片付けが苦手な子が多いです。
その背景は子どもの特徴や性格によって様々であり、まずは子どもが片付けられない理由を知ることが重要となります。
今回は「片付け方がわからない」「回避行動の特性」「切り替えや集中力の苦手さ」「見通しが立たない状況」「こだわりの強さ」の視点から発達障害(ASD、ADHD)の子どもがどうやったら片付けられるようになるか解説します。

執筆:いけや さき
公認心理師・臨床心理士
精神科病院、療育施設、心療内科・児童精神科クリニックなど主に医療と福祉領域にて心理士として従事。
片づけられない理由は5つある?
「早く片づけなさい!」
「なんで片づけてないの!?」
何度言っても子どもが片づけられず、イライラした経験のある保護者の方は多いかもしれません。特に発達障害の子どもは、片づけが苦手な傾向があります。
無理やり片づけさせようとして「なんで!」「嫌だ!」と子どもが怒ったり泣いたりすることもきっとありますよね。
ADHDやASD特性を持つ子ども全員が、同じ理由で片づけられないわけではありません。まずは考えられる理由の代表例5つを紹介します。
1.片づけ方がわからない
ADHDの子どもは、脳内の交通整理が苦手です。脳内の交通整理とは「何を」「どこに」「どうやって」「いつ」など、頭のなかで必要な情報を整理すること。
ADHDは、衝動性の特性もあり、必要なことをすぐやる動作が苦手な子は多いです。
ASDの子どもは、自分のタイミングで規則正しく配置したい気持ちのほかに、「自分の置きたい場所」を持っていることもあるでしょう。
大人から見た正しい片づけ方法を、発達障害の子どもは分からない場合があるのです。
関連記事:
発達障害グレーゾーンの子どもたち〜見えない困りごとと向き合う方法〜
ASD(自閉スペクトラム症)とは?特徴、診断の受け方やサポート方法について詳しく解説【小中学生編】
2.回避行動の特性
特にADHDの子どもは「回避行動」という先延ばしグセを持っています。本人からしたら、短期的なメリット(楽しい時間が続くなど)があるので、片づけたくない気持ちになるのは当然かもしれません。
ASDの場合はマルチタスクの苦手さや考えすぎが先延ばしの原因といわれています。この後に解説する「こだわりの強さ」なども参考にしてみてください。
3.切り替えや集中力の苦手さ
発達障害を持つ子どもは、実行機能の障害により、切り替えや注意集中の持続を苦手な子が多いといわれています。
ADHDの子は段取りを考えたり、計画通りに進めることが苦手なのも片づけられない原因の1つでしょう。
ASDの子は、抽象的指示の理解や見通しの立たない状況を苦手としているため、切り替えられないことがあります。
4.見通しが立たない状況
「ごはんだから片づけて」と次の予定を言っても、片づけられないことはありませんか?もしかすると、声掛けだけだと理解が難しいことが原因かもしれません。
発達障害の子どもは、感覚に優位性を持っているといわれています。優位性とは耳から聞く指示理解が得意(聴覚優位)か、目で見る情報の指示理解が得意(視覚優位)かというもので、発達検査を受けると説明される場合もあるでしょう。
優位性に応じて工夫して、本人の得意な方を活かせるといいです。
5.こだわりの強さ
「○○じゃなきゃ嫌!」
特にASDの子は物の置き場所にこだわるのも特性の1つ。本人からしたら「見える・わかる」「安心できる」場所に置いて片づけたという認識なこともあります。
一方、ADHDにもマイルールはあります。興味の移り変わりが多い反面、やりたくないことへの関心が薄いのも特性の1つ。周りが当たり前にやっていることも、発達障害の子どもには苦痛に感じる状況が多いのです。
発達障害の子どもの片づけ術
発達障害の子が、今よりも片づけられるようにコツを4つ紹介します。
コツ1.見通しを立てる工夫
療育施設に行ったことのある方は、一日の流れの表を見たことはありませんか?このあとの予定を予測できるようにすると、子どもは安心します。
小学生なら文字だけでも大丈夫な子もいますが、イラストや写真などを用いる方法は小学生にも有効です。その際、言葉でも説明してあげると、聴覚と視覚の両方から情報を伝えられます。
また、物の置き場所を決めておくのも、見通しを立てる工夫の1つです。学校から帰ったら何をするか、手洗いうがいなどのほかに「プリントを入れる場所」などを決めておくと、片づけの癖をつけられますよ。
コツ2.効果的な動機付けをする
ASDの子どもは、理由があれば納得することも多いです。大人には理解できない理由でも、本人なりに納得できれば、成功体験にもつながります。例えば「片づけたらシール」「シールがたまったら欲しいおやつ」など、小さなタスク毎のご褒美はわかりやすいでしょう。
ほかにも「4時になったら片づけよう」「これしまったら、ごはん一緒に食べよう」など、見通しが立てられる声掛けを合わせてもいいですね。
片づけられたら「ありがとう」「キレイになったね」など、前向きな言葉かけも忘れないでください。
コツ3.選択肢を減らす
発達障害の子どもには、多くの選択肢から選べない子も多いです。例えば、「1つしまうならどれ?」と片づけを前提とした声掛けをするとわかりやすいかもしれません。
ほかにも、「1つ出したら1つしまう」「ゲームの前に机の上を片づける」というルールを決めるのもいいですね。選択肢を減らす方法は、大人になってからも役立ちます。今のうちに練習しておきましょう!
コツ4.片づけを楽しむ
「ママとどっちが早いかな!」
「○○の曲が止まるまで」
など、低学年くらいまでは保護者も一緒に遊び感覚で片づける工夫も必要です。大きくなったら、タイマーを用意するなどゲーム感覚で楽しめるようにするといいかもしれません。成功体験となり、徐々に「片づけ=苦痛な作業」という認識が和らぐでしょう。
おわりに
大人も片づけが面倒に感じることってありますよね。
発達障害の子どもは、面倒に感じるよりも特性の影響が大きいです。「言うこと聞かない」と思わず、工夫をして片づけしやすい環境を作り、徐々に一人でもできるように練習していきましょう。
最初は保護者の方が大変かもしれませんが、子どもも慣れていけば、今よりできることが増えていくはずです。
参考文献
【専門家が教える】ADHDの人が「片づけられない」4つの理由|VERY
本田秀夫『「しなくていいこと」を決めると、人生が一気にラクになる』ダイヤモンド社(2021)
村田しのぶ『発達障害&グレーゾーンの子どもが「1人でできる子」になる言葉のかけ方・伝え方』日本実業出版社(2023)





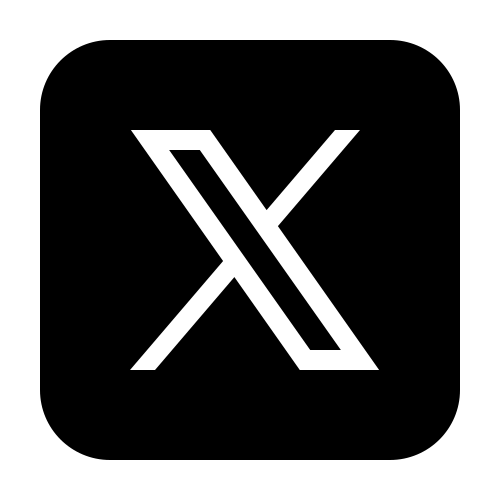




が高い子どもは育てにくい?育て方のコツ5選を心理士が解説-1.png)