2013年6月に障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、障害者差別解消法が制定されました。そこで合理的配慮が定められました。
さらに2024年4月に改正され、合理的配慮など障害のある人へのバリアを取り除くための社会的環境が緩やかながら着実に変化している状況にあります。
そのような法整備に伴い、行政や民間事業者では義務として制定され、違反が認められれば罰される世の中になってきました。
果たして学校ではどうなのか。学校内での実状と、お子さんが通っているという進行形の状況の中でどう先生との関係を築き、お子さんが学校生活を送りやすくするのか。
本記事では、考え方から先生への伝え方のヒントをお伝えできればと思います。

執筆:日塔 千裕
公認心理師・臨床心理士
発達障害や発達に心配がある子どもへの心理検査や子どもの指導、親御さん向け講座などを通して、親子をサポート。学校問題・親子関係など幅広い相談を受け、1万件を超える相談に応じる。
合理的配慮に関する法制定と実際
「合理的配慮」という言葉をご存知の方は多いと思います。2013年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、障害者差別解消法)」が制定され、その法律の中で行政機関や事業者に対して、障害者の求めに応じ合理的配慮をするものと明記されました。
当時は「法律で合理的配慮が明記されたのだから、学校でも!」と、お子さんが発達特性を有して学校生活でのつまずきに悩んでいた親御さんたちとざわついたのを記憶しています。
法律で明記されたからと言って、実践する人たちの考えや知識にすぐに変化があるわけではなく、現場としての実際場面では簡単に変わらないため、親御さんにとって非常に歯がゆい思いをした方が多いと思います。
もちろん学校の先生にとっても、今まで行ってきたこと、教員になるために学んできた内容と異なることをいきなり求められて、多くの苦労があったことと思います。
障害者差別解消法が制定されて10年が経過し、今でも思うような配慮をしてもらえず苦労している親御さん、お子さんは残念ながらたくさんいます。それでも、10年前に比べたら、多少はよくなっていて、個別の配慮を行ってくれる学校、先生はじわじわと増えてきているように感じます。
とはいえ、今、学校生活の中で苦労している親御さん、お子さんにとっては、過去と比べてマシになっていると言われても、今配慮をしてもらえなければ意味がないというのが正直なところですよね。
法律における「合理的配慮」とは…
学校への合理的配慮の求め方の前に、そもそも合理的配慮とは何かをお伝えしておきたいと思います。
今回、合理的配慮に関する内容を記載することになった理由としては、今年2024年4月1日に障害者差別解消法が改定され、合理的配慮に関する内容に一部変更があったからです。
学校という場に関しては、その改定に伴う影響は主に公立学校か私立学校かによって影響範囲は変わってきます。公立学校に在籍の場合には、今回の改定に伴う影響はほぼないと思われますが、改定されたことによる社会情勢が少しまた変わっていくことが予測されます。
2013年に制定された障害者差別解消法には、「行政機関における障害を理由とする差別の禁止」と「事業者における障害を理由とする差別の禁止」というように、行政機関と事業者が分かれて記載されています。
まず行政機関に関しては、「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」とあります。
次に事業者に関しては、「その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない」とあります。
法律の表現なので難しい言い回しも使われていますが、簡単に説明すると、障害のある人から社会的なバリアを取り除いてほしいという意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることというものになります。
行政機関と事業者で異なる点は、行政機関は「必要かつ合理的な配慮をしなければならない」という義務であるのに対して、事業者は「必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない」という努力義務だったのです。
それが、この2024年4月の改定で、事業者に対しても義務となりました。
主には国公立の学校は行政機関の区分に振り分けられるため、以前から合理的配慮が義務として位置づけられていました。一方で、主に私立学校に関しては、事業者の区分に割り振られます。
今までは努力義務であったため、「うちではできません」と言うことも可能でしたが、今回の改定で義務となったためどのように学校が変化していくか様子を伺う必要がありそうです。
私立学校は入試を突破して入学となるため、どのように学校が調整していくか、学校との話し合いをどう進めていくかなど、これからの課題はまだまだ山積みな気はします。
学校における合理的配慮は、どう求める!?
国公立が私立かということで少し法改正に伴う位置づけの違いがあるため、少し分けて記載しましたが、学校にどう合理的配慮を求めていくかというところにおいてのスタンスは基本的には変わらないと考えています。
この記事をお読みの親御さんはおそらく大丈夫だと思いますが、モンスターペアレントという言葉もでき、学校に何か言うとモンスターペアレントと思われるのではないかと恐れる親御さんも増えています。
この記事をお読みの親御さんはおそらく大丈夫と思うと伝えたのは、モンスターペアレントとなるようなコミュニケーションの取り方をしていない、そうならないようにどうしたらよいかと考えを持ちながら対応されている方ではないかと予測してのことです。
少し話が脱線しますが、モンスターペアレントと言われてしまうのは、要望の内容が無謀すぎることであることもそうですが、内容は無謀でないにしても伝え方が一方的になりすぎると、そういう視点で学校側から見られがちになります。
合理的配慮を求める権利はありますが、合理的配慮を行う側、つまりは学校が実施に伴う負担が過重ではない範囲ということが前提にあります。
そして、バリアを取り除くために必要な対応が何か、何なら学校内、クラス内で出来そうかということを対話を重ねて解決策を一緒に検討する建設的な対話が重要となります。
まず念頭に置いていただきたいのは、学校の先生も人間であるということです。こんな書き方をすると、学校の先生からは批判やお怒りを受けるかもしれませんが、学校の先生も感情を持った一人の人として伝え方には配慮が必要です。
お子さんの学年が上がれば自分の言葉で学校側に交渉するために話し合いの場に同席する場合もあると思いますが、低学年のうちはお子さんは同席せず、親御さんと先生との間で話し合いの場が設けられることが多いと思います。
実際に学校生活を送るのはお子さんなので、親御さんと先生が対立関係になってしまっては、お子さんの学校生活に影響が出てしまわないか心配です。そのような視点も持ちつつ、先生が気持ちよく動いてもらえるようにするにはどういう伝え方がよいかということを考えていくことが大切です。
合理的配慮の話をすると、よく「特別扱いはできない」などと特別扱いという言葉が出てきます。正直言って、特別扱いと合理的配慮は紙一重で、人の価値観によって、その捉え方は変わります。
親御さんにとっては自分の子どものためですが、先生は30人、40人の子どもたちを同時に一人で見ているわけです。その大変さへの理解も示しつつ、伝え方の工夫をしていくことが大切です。
先生と言っても人それぞれなので、保護者である親御さんたちと足並み揃えるように話し合いをして柔軟な対応をされる方もいれば、教師としての誇りやプライドで責任感強く、自分の考えやこれまでの経験を軸にやり方を決められる方もいらっしゃいます。
親御さんが悩むのは、おそらく後者のタイプの先生が担任の場合でしょう。前者のタイプの先生は要望も伝えやすかったり、先生の方からお子さんにあるとよいサポートをしてくれていたりとすることが多いように思います。
おわりに
教師としての誇りやプライドを高くもっているからこそ、そこを刺激せず、先生の考えも聞きながら負担が少なく対応可能な方法は何かを考えていくことが重要となります。
そして、無理に親御さんだけで先生に理解してもらおうとしすぎず、スクールカウンセラーや特別支援教育コーディネーターなど第三者も含めて代弁してもらうことも大切です。
担任との関係が難しいと感じた場合には、スクールカウンセラーや特別支援教育コーディネーターなど学校内に出入りしている別の立場の方に理解を求める働きかけをまず始めてみれるとよいでしょう。
学校内に出入りしている第三者の協力を仰ぐことが難しい場合には、学校外の機関でどのような配慮を求めることが可能か一緒にアイディアを考えてもらえるサポーターを見つけていきましょう。
参考文献
内閣府 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html
発達障害/発達凸凹とグレーゾーンに関する記事一覧はこちら。






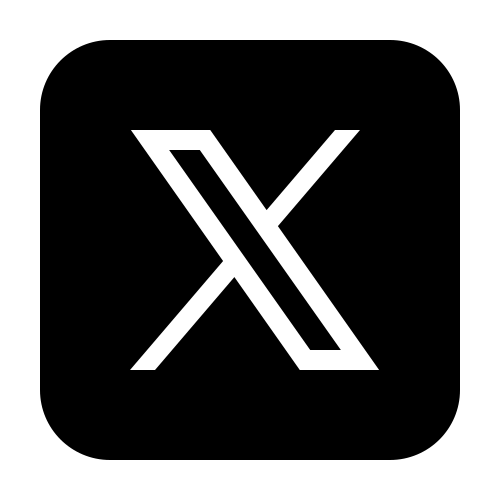




が高い子どもは育てにくい?育て方のコツ5選を心理士が解説-1.png)