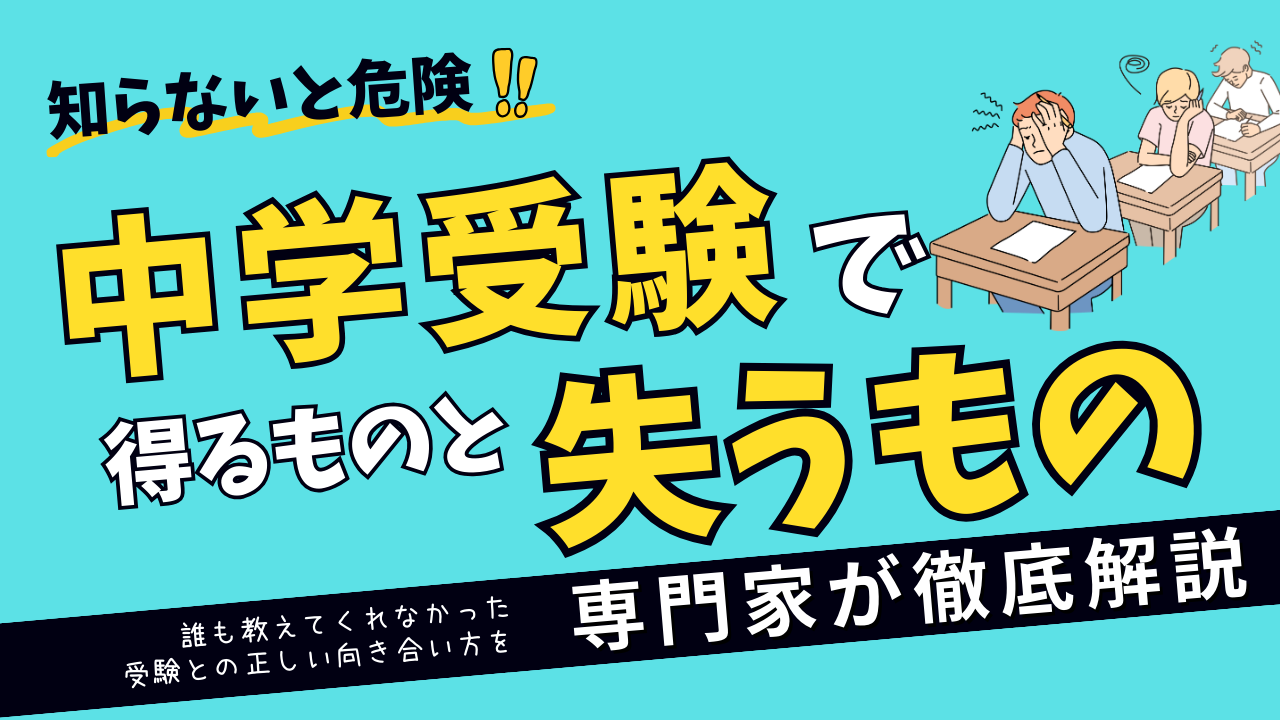中学受験者数は年々増加していると言われています。
一方で、中学受験の弊害は以前から言われていることも確かです。
そこで、この記事では、親子共に中学受験を良い経験として受け入れていくために必要なことは何か、子どもの成長発達、受験というものの特異性、家族の関係性、等の視点から専門家が解説してます。

執筆:杉野 亮介
公認心理師・臨床心理士
教育支援センター、スクールカウンセラーとして不登校支援などに携わり、児童福祉施設で心理士として20年間以上従事。発達障害児の心理的支援などを行う。
はじめに
少子化が進む中で、中学受験者数は年々増加していると言われます。
中学受験自体が悪いものとは言えませんが、その取り組み方次第では得られるものもあれば、失ってしまうものもあると言えます。
受験という以上は、合格か不合格かという結果が生じますので、もちろん合格するに越したことはありませんが、「合格=成功」とは言いきれないところもあります。
実際に、合格したのに燃え尽きてしまって学校に行かなくなったという相談を受けることもよくあります。
そこで、中学受験という体験をより実りのあるものにするためには、どう取り組んでいけば良いのか、を子育て支援をしている心理士からの視点でお話していきたいと思います。
中学受験をする時期について
あたりまえですが、中学受験というからには、11歳か12歳の子どもが受験をするわけです。
この年代というものが、子どもの成長発達において、どんな時期なのかを知ることで中学受験への向き合い方、あるいは付き合い方について考えることができるでしょう。
中学受験をする子どもの多くは、小学4年生の頃から受験勉強に取り組むと言われているそうです。
小学校高学年となると、ちょうど思春期の入口で、いわゆる「多感」な時期と言えます。
多感であることには人間の成長発達にとって意味があり、集団生活をする中で、色々なことが気になったり、悩んだりする時期です。
この時期に自分の学力だけでは無く、自分の容姿のことで悩んだり、友だちのことが気になったり、友だちと自分を比較して劣等感に悩んだり、不安になったりすることで、心が成長し強くなって行きます。
この時期に、他の刺激を遮断して、意識を勉強だけに向けて、「他のことは何も考えなくていい」「勉強だけしておけばいいんだと」となってしまうことは、心の成長にとっては非常にリスキーなことだと言えます。
心の成長という面では、この時期は、他者との比較の中から自分らしさを意識していく過程にもなり、それまで持っていた創造性やユニークさを自分らしさとして自分に落とし込んでいく過程とも考えられます。
また、この時期は第二次反抗期の入り口でもあります。
子どもは親に対して反発することで自立心が芽生えて行きます。
しかし、この時期に、「あなたは勉強だけしておけばいい」と受験勉強一本になってしまって、親が子どものサポートのためと子どもの言うことばかり聞いてしまえば、子どもの自立心は育ちません。
親子がいつまでたってもべったりということになりかねません。
なお、家族関係のことにおいてはまた後で述べます。
子どもの脳も含めて体の成長にとって、偏りなく、多様な経験をすることが何よりも必要です。
勉強、スポーツはもちろん、家族や友だちとのふれあい、自然とのふれあい、等はどれかが必要ではなく、全てが必要なことなのです。
そして、子どもの成長発達においては、ある程度、不可逆的な側面もあるのです。
もちろん、その後の人生で取り戻すこともできますが、小学校高学年のこの時期、多くの中学受験生が受験に取り組む、小学4年生から3年間という期間は、子どもの成長発達にとって非常に重要な時期であり、多様な体験を積むことが子どもの成長発達を促進するということは忘れてはいけません。
こう考えると、中学受験との向き合い方は自然と見えてくるでしょう。
勉強以外の全てを捨てて、子どもの生活を受験勉強一本に絞ることは、子どもの成長発達にとってデメリットが非常に大きいと言えます。
受験勉強と多様な体験を両立できるだけの余裕(時間的にも経済的にも)を持てるか否かという視点で、受験生活をプランニングしたり、志望校を考えられるのが良いと思います。
受験というものの特異性
入学試験という以上は、合格か不合格かという二つの結果が生まれます。
そして、その結果を出すためには、回答は正解と不正解に分別されたり、求めている回答にどれだけ近いのかということで点数化されたりします。
これはあらかじめ決まっている正解を答えたり、相手(受験校)が求めているものにいかに近づけるのかということが求められています。
このシステムは受験という枠の中では非常に合理的ですし、受験をする以上はこのシステムを受け入れるしかありません。
受験校にもよるのかもしれませんが、多くの学校の受験では、正解を回答することが求められているわけで、創造性やユニークさを発揮することは求められていません。
創造性やユニークさを評価したり、点数化することは非常に難しいからです。
つまり、その受験生の多様な側面のうちの、ごく一部の能力を測っているに過ぎないというところに、受験というシステムの特異性があります。
つまり、受験と言うシステムに対して、子どもが持つ能力や特性によって、どうしても向き不向きが出てきてしまいます。
こつこつと知識を覚えたり与えられた問題を解くことが苦手な子どもは向いていますが、誰も考えつかないようなパッと生みだすような創造性が豊かでユニークな子どもその能力を受験と言う枠組みの中では発揮しにくいので不向きと言えます。
もちろん、創造性やユニークさは受験以外のところで発揮すれば良いのですが、生活が受験勉強一本になってしまうと、創造性等もユニークさも必要とされない能力として、徐々に目立たなくなってしまうことになります。
そして、その本人も、その能力を不必要なものだと認識してしまって、周囲からみると、「あの子の良さが見られなくなってしまったな」と残念に思うこともあります。
また、とにかく点数をたくさん取る人が偉いという価値観のみに縛られてしまうと、合格した人が優れている、不合格の人が劣っているとなってしまい、不合格だった時には、「自分はダメだ」「今までやってきたこと全てが無駄になった」と思ってしまうリスクがあります。
我々の実際の生活では「多様性」という言葉が重宝されるように、多様な視点から物事を見ることが求められています。
国語は得意だけど算数は苦手、勉強は苦手だけどスポーツは得意、勉強もスポーツも苦手だけどとても優しい、どの子が良い悪いではなく、どの子も素晴らしい存在ですし、どんな子も「私は私でいい」と思えるようになっていくことが子育ての目標の一つです。
受験勉強を頑張っている子どもも素晴らしい存在ですし、受験とは無縁な生活で日々を過ごしている子どももそれだけでも素晴らしい存在であるということを忘れてはいけません。
受験は試験における得点という一つの視点からのみ評価するという非常に特異的なシステムで行われていること、一方で実際の生活では多様な視点が求められていているということを大人は自覚し、子どもにも伝えていくことが大切です。
家族の関係性について
小学校高学年の子どもが受験勉強を頑張ると言っても、そこには費用もかかりますし、塾等の送迎が必要になることも多いでしょうから、家族のサポートなしでは受験勉強は成立しないでしょう。
家族が受験生をサポートすることは何も悪いことではありません。
ただし、親や家族がサポートしてくれていることに対して「ありがとう」と子どもが言える、あるいは思える関係性であることは必要です。
もしも、親が一方的に「受験しなさい」と言って聞かせたような場合には、「受験してあげる」と考えている子どもは、親や家族にありがとうとはなかなか思わないでしょう。
そういう意味でも、あくまでも、子どもが中学受験をしたいという意思を持った上で受験勉強に取り組むことは必要だと思います。
家族の関係性を考えると、受験勉強をやっている子どもが一番偉い、となることは望ましいことではありません。
しかし、受験に合格するためにということだけに盲目になってしまうと、親も子も周りが見えなくなってしまって、とにかく受験勉強をとなってしまって、受験する子どもがヒエラルキーの一番上に立ってしまい、家族の関係性がゆがんでしまうというリスクが中学受験には大きいと言えるでしょう。
受験勉強をしている子どもが頑張っていることを認めてあげた上で、きょうだいもそれぞれ自分のことを頑張っている、親も親で頑張っている、とそれぞれを尊重できる関係性が必要です。
受験勉強をしている子どものために、残りの家族が犠牲になるということは望ましくありません。
家族間でそれぞれを尊重できる関係性がないと、思春期に子どもと親が対峙するべき時に、子どもが親の言うことを何も聞かない、となってしまいがちです。
そして、次の段階として、多くの場合は、子どもが大人の言うことを聞かなくなり、何らかの不適応を起こしていくことになります。
おわりに
中学入学までよりも、中学入学後の人生の方が遙かに長いのは言うまでもありません。
中学受験を目標の一つに設定するのは良いと思いますが、ゴールではないということを大人も子どもも自覚する必要があります。
中学受験に合格したという達成感が次の向上心につながるのか、それともそこで終わってしまうのかということを考えると、誰かにやらされた受験だったのか、自分がやりたい受験だったのかということは、非常に大切になってくるでしょう。
残念ながら合格できなかったとしても、自分がやりたいと思った受験を最後までやり遂げたことや家族がそれをサポートしてくれたことによって、良く頑張った、よい経験になった、と思えるでしょうし、家族等にも感謝の気持ちが湧いてくるのだと思います。
私は、中学受験に限らず、日々の体験が全ての子どもにとって、実りあるものであってほしいと思います。
そのためには、「中学受験合格のために、今は~を犠牲にする」という考えはやめた方が良いと思います。
全ての人の人生において一瞬一瞬が貴重な時間であり、犠牲にしても良い時間や時期はないということを、この文章から少しでも読みとっていただけたら幸いです。