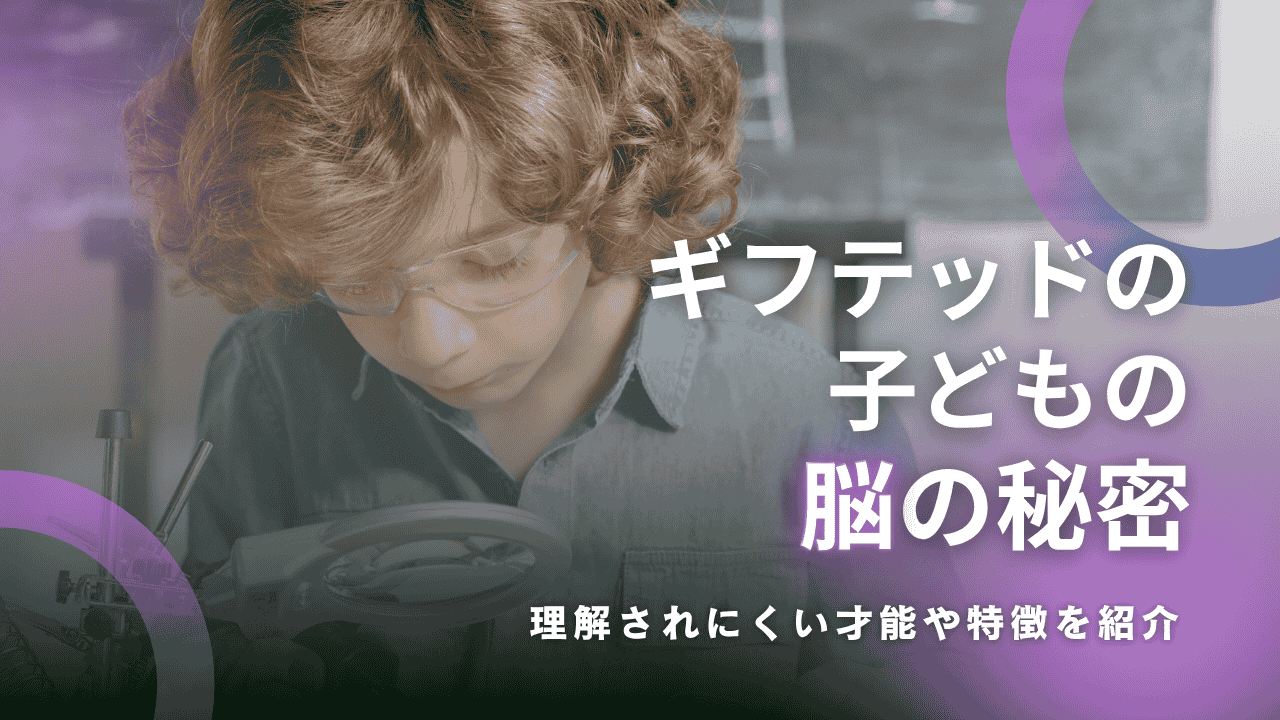発達障害のある子どもは、学校や家庭、日常生活の中でさまざまな困難に直面します。
その中でも近年注目されているのが、発達障害グレーゾーンの子どもです。
グレーゾーンとは、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如多動症(ADHD)、学習障害などの発達障害の傾向が見られるものの、心理検査や診断基準上は明確に分類されない状態を指します。
診断がつかないために、「支援が必要ないと思われる」、「周囲に理解されにくい」という問題が生じやすく、子ども本人は見えない困りごとを抱えたまま過ごしている場合も少なくありません。
この記事では、発達障害グレーゾーンの特徴・行動・困りごとを整理し、学校や家庭での接し方・対応方法・発達支援の考え方についてご紹介します。
発達障害グレーゾーンとは何か|診断基準と状態の理解
発達障害グレーゾーンとは、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、学習障害などの特徴を部分的に持ちながらも、診断基準を満たさない状態を指します。
心理検査を受けても、
- 知能指数が基準内
- 困難が一部に限定されている
- 環境によって症状が軽減する
といった理由で、発達障害として分類されない場合があります。
しかし、診断がつかない=困りごとがないわけではありません。
言葉の発達、感覚の過敏さ、不安の強さ、感情のコントロールの難しさなど、子どもの特性によって日常生活に支障が出ることもあります。
こうした様子は3歳頃から見られる場合もあり、小学生になるにつれて学校生活の中で問題として顕在化することも多いです。
発達障害グレーゾーンの子どもの特徴と傾向
ここでは、発達障害グレーゾーンの子どもの特徴と傾向や学校で起こりやすい問題と困難をご紹介します。
グレーゾーンの子どもたちは、定型発達の子どもたちの中でも日常の各タスクにうまく対処できているように見えることも多いため「普通」と見なされがちです。
また、グレーゾーンにも困りごとのレベル感にグラデーションがあるため、一概に「このパターンがグレーゾーン」というようなことも言えず、理解されにくいのです。
脳の特性によって、「みんな」(多数)ができていることができないと怒られ、問題児扱いされる子どもは、日常生活で困りごとを抱え、さらにうまく対処ができないことによって批判され、孤独感や無気力感を感じてしまうという課題に直面しています。
グレーゾーンの子どもたちは、発達障害の特性を持ちつつも、診断基準に完全には当てはまらないため、必要な支援や理解を得られにくい状況にあります。
具体的に行動面では、以下のような面が見られる場合があります。
- 感覚(音・光・触覚)に敏感で疲れやすい
- コミュニケーションが独特で誤解されやすい
- こだわりが強く、行動の切り替えが難しい
これらは子どもの脳の特性によるものであり、本人の努力や気持ちだけではコントロールが難しい場合が多いです。
学校という集団環境は、発達障害グレーゾーンの子どもにとって困難が表面化しやすい場面です。
特に学校生活だと、例えば、
- 先生の話を静かに聞き続けることが難しい
- 集団行動や一斉指示に対応できない
- 文字の読み書きや学習の一部が極端に苦手
- 片づけや準備が苦手で何度も注意される
といった行動が見られることがあります。
これらの行動は「わざと」や「反抗」ではもちろんありません。
しかし周囲からは問題行動と受け取られやすく、繰り返し叱られることで自己肯定感が低下し、気持ちの面で不安や無力感を抱えやすくなります。
なぜ発達障害グレーゾーンの子どもは理解されにくいのか
発達障害グレーゾーンの子どもが理解されにくい理由は、本人の問題ではなく、制度や大人側の認知構造にあります。
「支援の前提が診断の有無に置かれている」点にもあります。日本の教育や福祉の制度は、発達障害や知的障害といった明確な診断名があることを前提に設計されており、診断基準に満たない状態は支援の対象外とされやすい構造があります。
その結果、発達障害グレーゾーンの子どもは、実際には困りごとや困難を抱えていても、「発達障害ではない」「普通の範囲」と判断されやすく、学校や家庭で必要な配慮や発達支援につながりにくくなります。
また、グレーゾーンの子どもは、場面や環境によって行動の現れ方が大きく変わるという特徴があります。
静かな環境や興味のある活動では落ち着いて集中できる一方、集団行動や一斉指示の場面では困難が顕在化することがあります。この「できる場面」と「できない場面」の差が、「やればできるのに」「気分の問題」と誤解される要因になっています。
さらに、困りごとの程度が連続的であることも理解を難しくしています。
発達障害グレーゾーンは、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如多動症)と定型発達の間に位置する状態であり、「ある・ない」で明確に区切れるものではありません。
そのため、先生や周囲の大人が対応に迷い、「様子を見る」という判断が繰り返されやすくなります。
家庭と学校で見える姿が異なる点も、理解の妨げになります。
家庭では感情が不安定になったり、強い疲労や不安を訴えたりしていても、学校では何とか頑張っているように見える場合があります。
その結果、「家での問題は育て方の問題」「学校では問題がない」と捉えられ、子どもの負担が見過ごされてしまうことがあります。
子ども自身が困りごとを言葉で説明できないことも少なくありません。自分でも「なぜできないのか」「何がつらいのか」を理解できていない場合、周囲の大人は行動だけを見て判断しがちになります。
これが、「怠けている」「わがまま」「気持ちの問題」といった誤った評価につながる場合があります。
このように、発達障害グレーゾーンの子どもが理解されにくい背景には、制度的な問題、診断基準の厳格さ、行動の一貫性のなさ、そして大人側の認知の枠組みといった複数の要因が重なっています。
だからこそ、「診断があるかどうか」ではなく、「その子が何に困っているのか」という視点に立ち返ることが、発達支援の出発点として重要なのです。
「ニューロダイバーシティ」という考え方
近年では、「発達障害」「発達凸凹」「グレーゾーン」などではなく、「ニューロダイバーシティ(Neurodiversity)」という「脳の多様性」として捉える動きも大きくなってきました。
経済産業省でも、「イノベーション創出や生産性向上を促すダイバーシティ経営」とか「成長戦略」などと捉えてこの概念を推進しています。
“イノベーション創出や生産性向上を促すダイバーシティ経営は、少子高齢化が進む我が国における就労人口の維持のみならず、企業の競争力強化の観点からも不可欠であり、さらなる推進が求められています。この観点から、一定の配慮や支援を提供することで「発達障害のある方に、その特性を活かして自社の戦力となっていただく」ことを目的としたニューロダイバーシティへの取組みは、大いに注目すべき成長戦略として近年関心が高まっております。”
経済産業省 「ニューロダイバーシティの推進について」 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/neurodiversity/neurodiversity.html
日本を含む多くの国では、発達障害や知的障害の確定診断を受けた子どもたちに対しては、社会福祉の枠組みで比較的手厚い支援が提供されています。
しかし、グレーゾーンの子どもたちに対する理解や支援はまだ充分には行き渡っていないのが現状です。
これは、発達障害の診断基準が非常に厳格であるため、微妙な発達の違いが認識されにくいことが原因の一つと考えられます。
こうした子どもたちに対して、「ニューロダイバーシティ(Neurodiversity)」の考え方をもとに、教育現場では個別のニーズに応じた支援プランを作成し、子どもたち一人ひとりの特性に合わせた教育を提供することが大切です。
一方で、教育現場のリソースや教員の知識・スキル面の理由もあり、実際のところは個別ニーズへの対応が現実的ではない場合が大半です。
定型発達かそうでないか、での基準によって特別支援学級へ振り分けられたり、親同伴で登校を求められるなど、教育現場での脳の多様性がある子どもたちへのケアの方法は適切とは言えず、対応方法も限定的です。
発達障害グレーゾーンの子どもたちの対処法とサポート
では、発達障害の子どもたちやグレーゾーンの子どもたちへはどのようなサポートが望まれるのでしょうか。
以下では、具体的なステップをご紹介したいと思います。
個別の困りごとの理解
最初のステップは、子どもの個々の困りごとを把握することです。
教育環境におけるニーズに合わせて調整する必要があるからです。
例えば、授業中にみんなと一緒に座って静かに先生の話を聞くことが苦痛だったり、どうしても集団行動ができないなど、子どもが日常生活や学校で直面する具体的な課題を観察し、記録することが有用でしょう。
子ども自身も説明できない困りごとについても、どのようなパターンがあるか、また不適切行動の現れ方の特徴も把握することができます。
環境やツールの調整
困りごとがわかったところで、学校や家庭での環境を、子どもの困りごとを取り除いて安心して能力を発揮出来るようにしましょう。
例えば、音が苦手で集中できない子には騒音が少ない静かな学習環境を提供する、忘れ物が多い子には日常生活におけるルーティーンを作る(しなければならないことを日々の習慣として予測可能な行動にすることで、子どもにとって取り組みやすくなります)などがあります。
子どもにも認知機能、ワーキングメモリや知能面など、脳の特性から来る「取り組みやすさ/取り組みにくさ」があります。
どのような環境が子どもにとっていいか、あるいは悪いか(集中しにくい、やり方が苦痛など)を勘案した上で、それに合う環境やツールの調整をしましょう。
専門家との連携
学校のカウンセラーや教育支援専門家、発達障害を専門とする医師との連携を図ることも方法の一つです。
一方で、実際には学校から医療機関を勧められる場合、発達障害というラベリングをされやすい、ということを親御さんからよく聞きます。
不適切行動が何によって引き起こされるのかなど根気強く観察してみたり、ギフテッドの可能性はないか、普段密に関わっている親や教師が総合的に判断をした上で、教育現場や家庭で工夫できることはないかまず検討した上で、適切な第三者機関へ案内することが望ましいはずです。
深刻な他害行動などがない限り、医療機関での投薬は避けるべきという声も多いです。
ギフテッドの子どもと発達障害グレーゾーン
ギフテッドの子どもは、高い知能や突出した興味・集中力を持つ一方で、グレーゾーンと誤解されやすい特性を示すことがあります。
実際、学校や家庭で「落ち着きがない」「集団行動が苦手」「空気を読まない」といった行動が見られると、注意欠如多動症(ADHD)や自閉スペクトラム症(ASD)の傾向として捉えられる場合も少なくありません。
この誤解が生じる背景には、ギフテッドの子どもが持つ「非同期発達(asynchronous development)」という特徴があります。
これは、知的発達が非常に高い一方で、感情面や社会性、自己コントロールの発達が年齢相応とは限らない状態を指します。
その結果、知的な会話は大人顔負けであるにもかかわらず、感情のコントロールや対人関係では幼さが目立つというアンバランスさが生じます。
また、ギフテッドの子どもは興味の対象が極端に偏る傾向があり、関心のない活動や学習には強い苦手さや拒否反応を示すことがあります。
この様子は、「集中できない」「指示が通らない」と見なされやすく、グレーゾーンとして扱われる一因になります。しかし実際には、知的刺激が不足している環境そのものが、行動上の問題を引き起こしている場合もあります。
感覚の鋭さや過敏さも、両者を区別しにくくする要因です。ギフテッドの子どもは、音や光、言葉のニュアンスなどに非常に敏感で、不安や疲労を感じやすいことがあります。
これが感覚過敏や不安症状として現れると、発達障害の特徴と重なって見えることがあります。
重要なのは、「発達障害か、ギフテッドか」という二者択一で考えないことです。
ギフテッドでありながら発達障害の特性を併せ持つ子どもも存在しますし、グレーゾーンとギフテッドが重なって見える場合もあります。
ラベルに急いで当てはめるのではなく、子どもの行動がどのような環境条件で現れ、どのような支援によって軽減されるのかを丁寧に観察することが不可欠です。
知的に挑戦的な課題を与えられたときに行動が落ち着く、興味のある分野では驚くほどの集中力を発揮する、といった場合には、学習環境や教育内容の調整が有効な支援となることがあります。
ギフテッドとグレーゾーンの違いを正確に見極めることは難しいからこそ、「診断名」よりも「その子に合った環境と関わり方」を重視する視点が重要です。
発達障害グレーゾーンの子どもに本当に必要なサポートとは
子どもたち一人ひとりが抱える困りごとは、見えていたり見えなかったり、見えていても大小さまざまです。
多くの場合、「とても難しい状況の中で努力している」のに、本人の意思ではなかなか対応することが難しい、または精一杯対応している場合が多いです。
一方で、周りから見ると、「なんでこんなこともできないのか」、「何でこんな手がかかるのか」、などと捉えられることもありグレーゾーンの子ども自身にとっては精神的に辛い環境です。
周りの大人は、まずは、子供が脳の特性によって困りごとを抱えている、という可能性を考えることが大事です。
そして、子どもたちが自分の感じていることをオープンに話せる安全な環境を提供すること、彼らの困りごととそれに対する努力を認めて肯定的な見方をするようにしてください。
教育現場や家庭だけでなく、子どもたち一人ひとりの脳の特性からくる個々のニーズに対応することが、今社会でも求められています。
困りごとを理解するだけでなく、このユニークネスを活用することに繋がっていくことを期待しています。